記事
未収金はどうやって回収する?
公開. 更新. 投稿者: 7,695 ビュー. カテゴリ:薬局業務/薬事関連法規.この記事は約5分12秒で読めます.
目次
未収金はどうやって回収する?―薬局での対応と法的ポイント
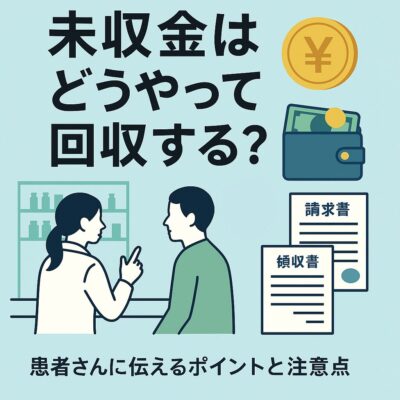
薬局で日常的に頭を悩ませる問題の一つが未収金です。
「未収金はうちではあまりない」と思っていても、保険証の期限切れや調剤報酬の再計算、急な処方変更などで、意外に発生しやすいものです。
薬局で起きる未収金の代表的なパターンと、その回収方法、さらに注意すべき法律上の問題について勉強します。
そもそも未収金とは?
「未収金」とは、すでに調剤や販売を行ったにもかかわらず、患者さんからの一部負担金の支払いが完了していない状態のことです。
調剤薬局では、調剤報酬の多くが保険者から支払われますが、患者さんにも自己負担分の支払い義務があります。この自己負担分が支払われていない場合、それが未収金になります。
多くの薬局では、1件当たりの未収金は数百円から数千円程度と比較的少額であることが多いです。しかし、放置して積み重なると管理上のリスクになるだけでなく、法的にも問題が生じる恐れがあります。
未収金が発生する主な原因
未収金は、以下のようなケースで生じることが多いです。
①現金の持ち合わせ不足
患者さんが薬を受け取った際、手元に十分な現金がなく、一部または全額を支払えないケースです。特に高額な薬剤を複数処方されたときや、月初めに自己負担額がリセットされるタイミングでは起こりがちです。
②処方内容の変更
調剤後に処方医から連絡があり、薬剤内容が変更される場合、一部負担金の金額が変わります。この場合、差額の支払いまたは返金が必要です。
③算定誤りの発覚
患者さんが帰宅した後、調剤録と処方箋を再点検して過誤が判明することがあります。例えば点数の二重計算や算定漏れが見つかった場合、修正のうえ再度請求が必要です。
④保険証の期限切れ・資格喪失
保険証の確認漏れや患者さんが期限切れの保険証を提示したことで、後から返戻(レセプト不支給)となるケースです。この場合、保険診療分も患者さんに全額請求しなければなりませんが、連絡が取れない事例も珍しくありません。
未収金を放置するリスク
「少額だし、面倒だから請求しなくてもいいか」とそのまま放置すると、思わぬ問題が発生します。
健康保険法では、療養の給付(調剤)を受けた患者には一部負担金の支払い義務があり、薬局はその支払いを受けるべく努める義務があります。
健康保険法第74条第2項
保険医療機関又は保険薬局は…一部負担金の支払を受けるべきものとし…支払を受けることに努めたにもかかわらず…支払わないときは、保険者は…徴収することができる。
つまり、きちんと徴収の努力をしている記録が必要です。
この努力を怠り、事実上「払わなくていいですよ」と免除することは、違法な減免とみなされる可能性があります。
また、監査や指導の際に「支払い督促をした記録がない」「回収の意志がない」と判断されると、処分の対象になる恐れも否定できません。
回収の基本的な流れ
未収金が発生したときの対応は、原因によって異なります。以下にケース別に整理します。
ケース①:現金の持ち合わせがない
患者さんの事情で一時的に支払いが困難な場合、以下の流れで対応します。
・支払い意思の確認
「後日お支払いいただけますか?」と意思を確認し、了承を得ます。
・書面に記録
領収書に「○月○日に一部負担金未収、支払い予定日○月○日」と明記するなど、証拠を残します。
・連絡先の確認
住所、電話番号を再確認します。
・督促
予定日を過ぎたら電話や手紙で督促します。
・根気強く追徴
患者さんに事情を説明し、支払いを促します。
これらの経緯はすべて記録に残しましょう。督促記録が、支払い努力の証拠になります。
ケース②:処方変更による差額発生
この場合、患者さんに説明すれば納得を得やすいです。
・処方変更の経緯を説明
「医師からの連絡で処方が変更になり、負担金に差額が生じました」と伝える。
・次回来局時の支払いを依頼
多くは次回の来局時に精算されます。
・領収証の再発行
必要に応じて訂正後の領収書を発行します。
ケース③:算定誤りによる差額発生
特に注意が必要なのは、調剤報酬の算定誤りが原因の場合です。
返金なら比較的スムーズですが、追徴の場合は感情的トラブルに発展しやすいです。
・誤算定をお詫び
「大変申し訳ございませんが、点数計算に誤りがありました」とまず謝罪する。
・修正後の明細書を提示
患者さんが納得できる形で修正内容を説明します。
・支払い方法を相談
一括が難しければ分割も検討します。
・記録を残す
説明日時や内容を必ず記録します。
支払い督促の実務
少額で弁護士に依頼するのが現実的でない場合は、以下の方法を順に試みます。
・電話連絡
・ハガキや封書での請求書送付
・来局をお願いする手紙の送付
・訪問(事例によって)
支払いに行きづらくなる患者心理も考慮し、督促は「冷たく一方的に請求する」より「事情を伺う形」で行う方が効果的です。
「払えないから放置している」のか、「忘れているだけ」なのかを把握し、適切に対応します。
法的な回収手段
それでも支払ってもらえない場合、法律に基づく請求が可能です。
保険者による徴収
健康保険法第74条2項の規定により、保険薬局から請求すれば保険者(協会けんぽや国保など)が徴収することができます。
具体的には、各地方社会保険事務局に相談し、必要書類を提出します。
注意:
これも「薬局が善良な管理者として徴収努力を尽くした記録」が前提です。
時効の問題
未収金はいつまで請求できるのかも重要です。
・診療報酬請求権の時効:
診療を行った翌月1日から3年で時効になります。(健康保険法)
・民法上の債権の時効:
医師・薬剤師の診療報酬債権は3年(民法第170条)。
・一般の売掛金は10年(民法第167条)。
つまり薬局で発生する未収金は、原則3年間で時効となります。
期限を過ぎると請求できなくなるため、なるべく早期に回収のアクションを起こすことが重要です。
調剤拒否との関係
「未収金が溜まっている患者には、もう調剤を拒めるのか?」
これは多くの薬剤師が悩む問題です。
薬剤師法第21条
調剤の求めがあった場合には、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
この「正当な理由」には、近年はモンスターペイシェントや悪質な未払い(頻回・高額・故意)も含まれると解釈されるようになっています。
ただし個別の事例判断が必要なので、疑問があれば保険薬局の顧問弁護士や行政に相談してください。
まとめ
未収金の発生は、薬局の経営だけでなく、法的リスクや患者さんとの信頼関係にも影響します。
対応の基本は以下の通りです。
・発生時点で事情を説明し、必ず記録を残す。
・督促は早めに行い、適切なコミュニケーションを心がける。
・長期化する場合は、保険者への徴収依頼を検討する。
・計算ミスなどは丁寧に謝罪し、誠意をもって修正を行う。
・悪質なケースは「正当な理由」として調剤拒否も視野に入れる。
少額であっても、適正な回収努力を怠ることはトラブルの火種になります。
「お金の問題だから言いにくい」と遠慮せず、粘り強く、しかし誠実に対応することが大切です。
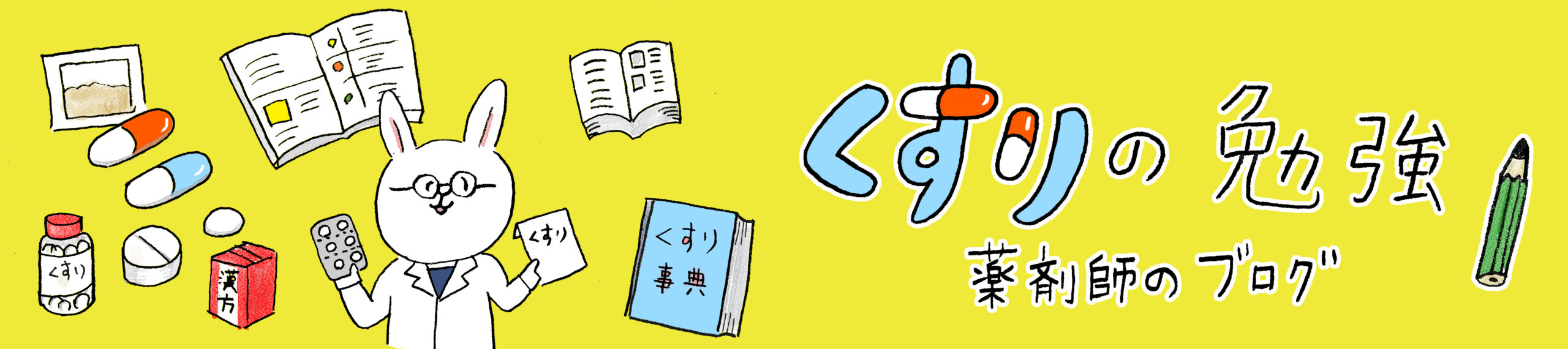


1 件のコメント
今5年じゃない?