記事
インターネット研修を受講しないとデュロテップ処方できない?
公開. 更新. 投稿者: 4,039 ビュー. カテゴリ:癌性疼痛/麻薬/薬物依存.この記事は約4分55秒で読めます.
目次
デュロテップの処方にはインターネット研修が必須?~慢性疼痛と確認書の実務的対応~
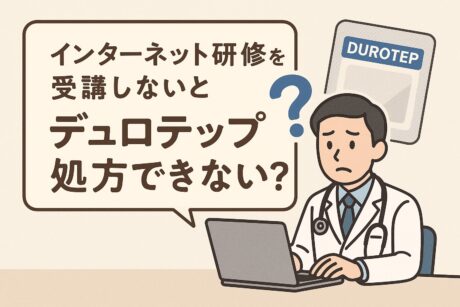
デュロテップMTパッチ(フェンタニル)は、がん性疼痛のみならず慢性疼痛にも適応拡大された貼付型の麻薬性鎮痛剤です。しかし、「慢性疼痛」に対して使用する際には特別な制限が設けられており、単に処方箋があれば薬局で調剤できるわけではありません。
デュロテップMTパッチを慢性疼痛に使用する場合のインターネット研修受講義務や、確認書の取り扱い、麻薬帳簿の記載の注意点まで、薬局で遭遇する実務的なポイントを勉強します。
慢性疼痛への処方は「インターネット研修」未受講では不可
デュロテップMTパッチは、がん性疼痛のみに使われていた時代と異なり、現在では「慢性疼痛」にも使用が可能になっています。
しかしその際には、医師、薬剤師ともに特別な条件を満たす必要があります。
■ 添付文書の承認条件(抜粋)
以下のような記載があります:
「慢性疼痛の診断、治療に精通した医師によってのみ処方・使用されるとともに、本剤のリスク等についても十分に管理・説明できる医師・医療機関・管理薬剤師のいる薬局のもとでのみ用いられ…(以下略)」
つまり、慢性疼痛に対してデュロテップを使用するには、
・処方医が「インターネット研修」を受講済みであること
・調剤薬局の管理薬剤師も同様に研修を受講していること
・調剤時には「確認書」の提示・確認が必要であること
が前提です。
これは、フェントステープ、ワンデュロパッチ、ノルスパンテープなどの慢性疼痛に使える貼付型麻薬にも共通する要件です。
それでも現場には「未受講処方」が紛れ込む
制度としては明確に「研修未受講者による処方はNG」となっていますが、実際には守られていない例も報告されています。
特に、
・最初は研修受講済みの医師が処方していたが、その後に当直医や代理医が「Do処方」を継続した場合
・確認書が1回目しか提出されず、以降の処方時に薬局側のチェックが省略された場合
など、現場では「うっかり」が起きやすい構造になっています。
しかし、薬局としては「知らなかった」では済まされません。調剤時には慢性疼痛なのか、がん性疼痛なのか、そしてその目的に応じた条件が満たされているかを確認する義務があります。
「確認書」があるのは慢性疼痛の場合のみ
デュロテップMTパッチの調剤時に「確認書」が必要なのは慢性疼痛に使用する場合のみです。がん性疼痛に対する処方では、確認書の提出は不要です。
ここで問題になるのが、患者がどちらの目的で処方されているのかを薬局がどうやって把握するかという点です。
■ 患者に直接聞いてはいけない?
「癌ですか?」などと患者本人に直接尋ねるのは、医療倫理的にも個人情報の観点からも避けるべきです。では、どうするか。
■ 処方内容・背景情報から推定
例えば以下のような情報が判断材料となります:
・同時に抗がん剤、制吐剤、オピオイド鎮痛剤などが処方されている
・他の麻薬からの切り替えでデュロテップが処方されている
・既にがん性疼痛目的のデュロテップが継続中であることが記録に残っている
このように、処方全体の文脈を見て判断することが求められます。
「確認書」は毎回確認が必要
Q:確認書の提出は初回だけでいいのでは?
A:いいえ、毎回必要です。
厚労省のQ&Aでは以下のように明記されています。
Q:確認書の確認は調剤の度に必要ですか?
A:確認書の確認は、調剤の度に行っていただく必要があります。
つまり、毎回、患者が持参する確認書を処方ごとに確認することが義務となっています。薬局側でコピーを保存していても、それは補助的資料であり、代用にはなりません。
ただし、実際の現場では「前回と同じ処方だから」「継続だから」といった理由で確認書を見ずに調剤してしまっている例も少なくありません。
しかしながら、処方医の交代や急な代診などの影響で、意図せず条件違反となるリスクがあるため、原則に則った確認体制が望まれます。
麻薬帳簿の「備考欄」記載ルール:「○慢」をつける理由
承認条件の変更に伴い、帳簿記載の運用も変更されました。
特に慢性疼痛を目的とする場合、麻薬帳簿の備考欄に「○慢」などと記載するよう求められています。
これは、
・転院時などに患者がデュロテップを持参した場合
・医療機関内で再利用される場合
に「がん性疼痛なのか、慢性疼痛なのか」が不明確にならないようにするためです。
■ 慢性疼痛=インターネット研修、確認書必須
■ がん性疼痛=研修・確認書不要
この区別を帳簿上でも明確にすることで、薬事監査などの際にも適正使用が証明しやすくなります。
まとめ:確認と対話の習慣を
デュロテップMTパッチのような麻薬性鎮痛薬は、使用管理において厳格な制度が定められており、特に「慢性疼痛」への適応拡大に伴い、薬局側の対応にも新たな責任が加わりました。
・毎回の確認書提示
・インターネット研修の有無
・処方医変更時の見落とし防止
・帳簿への「○慢」記載
など、日々の業務に忙殺される中でも見過ごしがちなポイントをあらためて共有し、チーム全体での確認体制の徹底が求められます。
薬局は単なる調剤機関ではなく、適正使用の最終チェックポイントです。
患者さんの安全を守るためにも、確認書一枚に込められた意図を理解し、慎重に取り扱うことが大切です。




