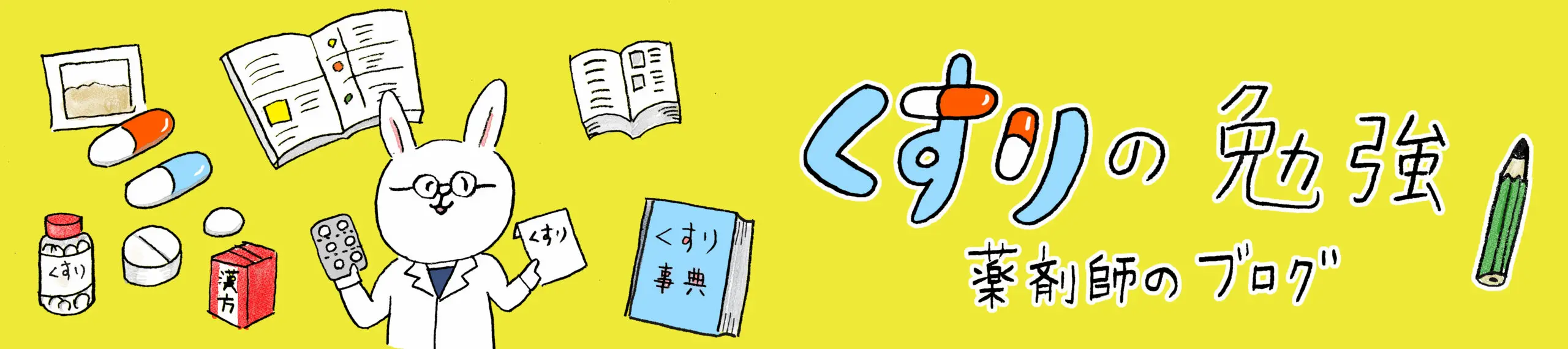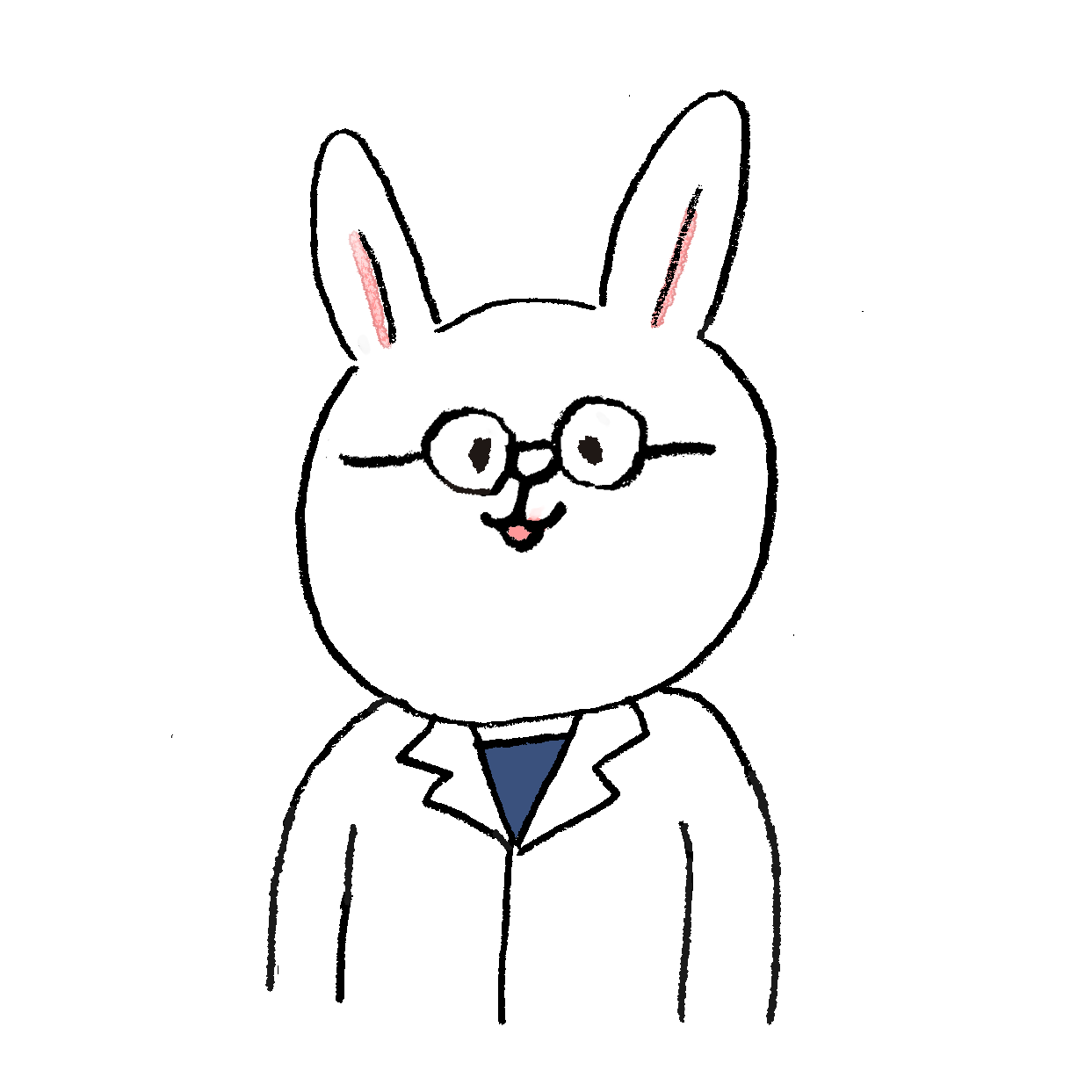記事
錐体外路症状に抗コリン薬を使っちゃダメ?
公開. 更新. 投稿者: 4,604 ビュー. カテゴリ:下痢/潰瘍性大腸炎.この記事は約6分46秒で読めます.
EPS
錐体外路症状が出現したら、副作用止めとして抗パーキンソン病薬を出すことで対応されていることが多い。
EPSが出現したら、最初に行うべきことは「抗精神病薬の減量」であり、「変更」です。
安易な抗パ薬の投与は、新たな副作用をつくります。
つまり副作用止めで副作用をつくってしまうのです。
副作用の連鎖です。
抗パ薬は統合失調症を治療する薬ではありません。
抗パ薬の多剤併用や長期使用は、精神科薬物療法のなかでいまだに続けられている誤解にもとづく処方です。
抗パ薬がEPSを軽減すると期待されて使われる薬理学的根拠は、抗コリン作用にあります。
抗コリン作用とは、アセチルコリンという神経伝達物質の作用を阻害する作用のことです。
EPSの発現機序
黒質線条体経路のドーパミン神経は、「シナプス後」でコリン神経と連絡しています。
通常ドーパミンは、コリン神経からのアセチルコリンの遊離を遮断し、アセチルコリンの活動性を抑制するようにはたらきます。
しかし、抗精神病薬によってドーパミンD2受容体が遮断され、アセチルコリンの遊離を抑制できなくなると、アセチルコリンは過活動になります。
この、ドーパミンの相対的な低下とアセチルコリンの過剰による運動の異常な亢進が、EPSの薬理学的な機序となります。
このとき、アセチルコリンの過活動を代償する方法として、アセチルコリン受容体を遮断してしまえばよいのではないか、ということで使われているのが抗パ薬なのです。
アセチルコリン
アセチルコリンは副交感神経や運動神経の末端から放出され、情報(命令)を伝える役割をしています。
ですから、アセチルコリンは全身のはたらきに関連します。
アセチルコリンがアセチルコリン受容体に結合すると、たとえば骨格筋や心筋、内臓筋の筋線維では、刺激が伝達され筋肉が収縮します。
あるいは副交感神経を刺激すると、脈拍を遅くし、唾液の産生を促す作用があります。
また脳内では記憶や認知機能と関連します。
したがって、アセチルコリンを阻害すれば、副交感神経系の作用を抑えて脈が速くなります。
目の毛様体筋の働きが悪くなり、ものが二重に見えます(複視)。
唾液の分泌が悪くなり、口が渇きます。
認知機能が低下し、物忘れがひどくなります。
これらは副作用のほんの一例に過ぎません。
アセチルコリンは全身にある神経伝達物質であり、しかも抗コリン作用には受容体に対する選択性がほとんどありません。
だからEPSを軽減する目的で投与した抗パ薬は、脳以外の全身のアセチルコリン受容体にも作用し、抗コリン作用を示します。
それで脳とは一見関連がない消化管、眼、心臓などでさまざまな副作用を起こしてしまうのです。
錐体外路症状に抗コリン薬は予め処方する?
非定型抗精神病薬や、たとえ定型抗精神病薬でも少量であれば錐体外路症状は発現し難いと考えられていますが、個人差や併用薬の問題から必ずしも防げるとは限りません。
錐体外路症状の対処方法の1つとして抗コリン性抗パーキンソン薬の投与があります。
これを予防的に処方するべきか、必要に応じて処方すべきかは議論が別れます。
前者を支持する意見の多くは、抗パ薬をあらかじめ処方することでアカシジアやジストニアのような服薬コンプライアンスに影響の出る副作用を未然に防ぐことをあげます。
しかし予防的に処方したばかりに錐体外路症状の有無にかかわらず長期間にわたり投与されていることは少なくありません。
抗パ薬の長期連用に伴う危険性として、①遅発性ジスキネジアの誘発、②尿閉、麻痺性イレウスなどの自律神経系の障害、
③記憶機能への影響、④悪性症候群様病態の誘発、⑤過剰投与による急性中毒症状の惹起、⑥依存の形成、⑦抗精神病薬の効果減弱、があります。
このことから抗パ薬の予防的処方はなるべく避け、また漫然と続くようであれば必要に応じて減量、中止を試みるべきと考えます。
錐体外路症状が出現したら、その対処法として、抗パーキンソン病薬を投与するのが一般的だと思います。
抗精神病薬によって黒質線条体のドーパミン受容体が遮断されてしまうと、アセチルコリンが過活動になります。
このアセチルコリンの過剰が、錐体外路症状発症の原因であるため、それへの対処のためにはアセチルコリン受容体を遮断すればよいのではないか、という考えで使われるのが抗パーキンソン病薬です。
古い治療論では、患者さんの服薬コンブライア ンスが下がる副作用は好ましくないので、あらかじめ予防的に抗パーキンソン病薬をセットで投与するという考え方もあったようです。
しかしながら、アセチルコリンを抑えた影響は全身に及びます。
コリン作動性神経は中枢のみに存在するのでなく、さまざまな臓器の生理的機能にかかわっているため、抗コリン薬が中枢神経以外の部位にも作用してしまい、 思わぬ二次性の障害を引き起こすのです。
抗パーキンソン病薬は使わないに越したことはない薬であり、最初から、抗パーキンソン病薬を使わなくてもすむような薬物療法を心がけるべきです。
抗パーキンソン病薬の投与はすべての方法(抗精神病薬の単剤化、用量減量、変更などによって過剰なドーパミンの遮断をやめること)を試した結果、それでも副作用が出るときの最後の切り札と考えるべきです。
やむを得ず使わなければならない場合は少量から投与し、アセチルコリンを遮断することによる二次性障害の兆候をよく観察しながら調節するべきでしょう。
なお、抗パーキンソン病薬はその止め方にも注意が必要です。
定型抗精神病薬を非定型抗精神病薬へ切り替えをするとき、副作用は軽減されるはずという考えから抗パーキンソン病薬も一挙に止めてしまう傾向があるようです。
これが、コリン作動性リバウンド症候群という、抗精神病薬の副作用とは全く違った、今までに経験したことのない症候(インフルエンザ様と称される症状)を引き起こすことがあるので注意が必要です。
しかもこの知識がないために、これが非定型抗精神病薬に切り換えたために起きたと誤って判断され、切り替えを断念してしまう残念なケースも少なくないようですから、覚えておくことが必要です。
抗コリン薬
酸分泌抑制効果は不十分で、口渇などの副作用があるため、いわゆる鎮痙薬として腹痛に対して用い、潰瘍治療薬として用いられることはほとんどない。
アセチルコリンがアセチルコリン受容体に結合するのを阻害し、副交感神経を抑制する。抗コリン薬は様々な病気に使われます。
ブスコパンやチアトンは、主に鎮痙剤として腹痛の症状を抑えるために処方されます。
チアトンは抗コリン薬の中でも、選択的ムスカリン受容体拮抗薬に分類され、胃に対する選択性が高いです。
・当初抗コリン薬は、胃酸分泌抑制薬としても使用されたが、近年、他のより効果的な胃酸分泌抑制薬の登場により、主に鎮痙薬として使用されている。
・アセチルコリンのムスカリン作用を抑制する。
・抗コリン薬は緑内障、麻痺製イレウス、重篤な心疾患、尿閉には禁忌である。
平滑筋収縮を持続的に抑制する薬剤を総称して鎮痙薬といい、鎮痙薬は抗コリン薬とほぼ同義である。
選択的ムスカリン受容体拮抗薬であるチキジウム(チアトン)は、副作用としての排尿障害が少ない。
アトロピンは中枢への移行性がよい3級アミンで、中枢への移行はアトロピンよりも容易なことから、治療量でも中枢作用が生じ眠気や無感動、健忘などの副作用が表れてしまう。
スコポラミンの中枢移行性を低くした薬剤が、4級アミンの構造を持つブチルスコポラミン臭化物(ブスコパン)です。抗コリン作用が強くなり、自律神経節遮断作用も示す。
・副作用発現時には、薬剤の中止、減量が基本であるが、拮抗薬としてコリンエステラーゼ阻害薬(ネオスチグミン)を用いる。
・感染性腸炎では、抗コリン薬の投与は菌の排出を遅延させる可能性があり注意が必要である。
・小児では、使用される鎮痙薬は限られており、プロパンテリンやブチルスコポラミンが使用される。
・相互作用:三級アミン合成抗コリン薬、四級アンモニウム塩合成抗コリン薬は三環系抗うつ薬、フェノチアジン系薬、MAO阻害薬、抗ヒスタミン薬で作用が増強。またジゴキシンの作用を増強させる。