記事
シュアポストは低血糖になりやすい?グリニド系薬の使い分け
公開. 更新. 投稿者: 3,896 ビュー. カテゴリ:糖尿病.この記事は約4分59秒で読めます.
目次
グリニド系薬の使い分け―シュアポスト・グルファスト・ファスティックを比較する―
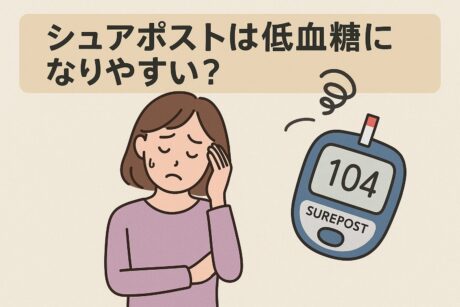
糖尿病治療薬のなかで、速効型インスリン分泌促進薬(グリニド系)は「食直前に服用し、食後の急激な血糖上昇を抑える」という特徴をもつ薬剤群です。SU薬(スルホニルウレア薬)と同じく膵β細胞からのインスリン分泌を促進しますが、作用の発現や持続時間が異なるため、「食後高血糖の改善薬」として位置づけられています。
しかし、同じグリニド系でも薬剤ごとに性質が微妙に異なり、処方頻度にも差があります。実臨床では、シュアポスト(レパグリニド)>グルファスト(ミチグリニド)>ファスティック(ナテグリニド)の順に使われることが多いのではないでしょうか。
各薬剤の薬理作用や臨床上の特徴を整理し、なぜシュアポストがよく処方されるのか、低血糖リスクとの兼ね合いはどう考えるべきかを勉強します。
グリニド系薬とは
基本的な作用機序
グリニド系薬は、膵β細胞膜上のATP感受性K⁺チャネル(KATPチャネル)に作用し、チャネルを閉鎖します。これにより細胞膜が脱分極し、Ca²⁺チャネルが開口、細胞内にカルシウムが流入し、インスリンが分泌されます。
SU薬と同じメカニズムですが、グリニド系は作用発現が速く、持続時間が短い点が特徴です。
グリニド系の位置づけ
・作用開始が速い → 食直前服用で食後血糖の上昇を抑える
・作用持続が短い → SU薬と比べ低血糖リスクが少ない
・HbA1c改善効果はやや弱め → 主に「食後高血糖の是正」に狙いを絞った薬
グリニド系薬の種類と特徴
現在日本で使用されている主なグリニド系薬は以下の3剤です。
| 一般名 | 製品名 | 作用発現 | 作用持続 | 排泄経路 | 主な特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| ナテグリニド | ファスティック、スターシス | 速い | 短い | 腎排泄 | 初期に登場。食後血糖抑制に限定。 |
| ミチグリニド | グルファスト | 速い | 比較的短い | 腎排泄 | 日本で開発。効果はマイルド。 |
| レパグリニド | シュアポスト | 速い | やや長い | 胆汁排泄 | 空腹時血糖も下げ、HbA1c改善効果が明確。 |
各薬剤の特徴と臨床評価
ファスティック(ナテグリニド)
・グリニド系の先駆けとして登場。
・作用発現が速く、食後血糖スパイクの抑制効果はある。
・しかし作用持続が非常に短く、空腹時血糖への影響は乏しい。
・HbA1c全体の改善効果が限定的なため、近年は使用頻度が低下している。
グルファスト(ミチグリニド)
・日本で開発された薬剤。
・ナテグリニドに比べるとやや持続時間が長く、効果はマイルド。
・腎排泄型のため、腎機能低下患者では血中濃度が上昇する可能性がある。
・処方はされるが、第一選択で使われることは少ない印象。
シュアポスト(レパグリニド)
・作用は速効型だが、他のグリニドより持続がやや長い。
・そのため「食後血糖」だけでなく「空腹時血糖」にも効果が及ぶ。
・HbA1c全体を下げる効果が明確で、臨床で「効きが良い」と実感されやすい。
・胆汁排泄型のため、腎機能障害のある患者でも比較的安全に使用できる。
・その反面、低血糖リスクは他のグリニドより高め。特に高齢者や食事量の不安定な患者では注意が必要。
シュアポストがよく処方される理由
① HbA1c全体を下げやすい
・グルファストやファスティックは「食後血糖の改善」に留まることが多い。
・一方、シュアポストは空腹時血糖も下げるため、HbA1c全体に寄与しやすい。
・医師にとって「効きが見えやすい」薬であることが大きい。
② 腎機能障害でも使いやすい
・糖尿病患者では腎機能低下を合併していることが多い。
・グルファストやファスティックは腎排泄型で注意が必要だが、シュアポストは胆汁排泄型で比較的安心。
③ SU薬より安全とされる
・SU薬(特にグリベンクラミド)は低血糖リスクが大きな問題。
・シュアポストは作用時間が長いとはいえSU薬ほどではなく、低血糖の深刻さは軽い。
・「SU薬を避けたいけれど、HbA1cをある程度下げたい」というケースで選ばれやすい。
デメリット:低血糖リスク
・他のグリニドに比べ、低血糖リスクは高め。
・特に 食事を抜いたとき、高齢者、腎機能低下患者では注意が必要。
・ただし、SU薬のような長時間の低血糖ではなく、比較的軽度~中等度で済むケースが多い。
・服薬指導では「食直前に必ず服用」「食事を抜くときは服用を中止」と伝えることが必須。
実際の処方傾向
実感として、処方頻度は以下の順になっているケースが多いでしょう。
シュアポスト > グルファスト > ファスティック
この傾向は、
・HbA1c全体を下げる効果の明確さ
・腎機能障害患者でも使いやすい点
・医師にとって「効きが見える」点
が理由になっていると考えられます。
低血糖リスクというデメリットはあるものの、それを上回るメリットが臨床で評価されているということです。
薬剤師としての服薬指導ポイント
食直前服用を徹底
→ 食事を抜くときは服用しない。
低血糖症状の確認
→ 冷や汗・ふらつき・空腹感などの症状が出たらブドウ糖を摂取。
他の糖尿病薬との併用時に注意
→ インスリン、SU薬、SGLT2阻害薬などとの併用でリスク増。
高齢者・腎機能障害患者には慎重に
→ 特に少食・不規則な食生活の人には注意を強調。
まとめ
・グリニド系薬は「食直前投与で食後血糖スパイクを抑える」薬。
・ファスティック(ナテグリニド)は作用が短く、近年は使用頻度が減少。
・グルファスト(ミチグリニド)はマイルドな効果だが、腎排泄型で注意が必要。
・シュアポスト(レパグリニド)は作用がやや長く、空腹時血糖も下げるため、HbA1c改善効果が明確。
・低血糖リスクは高めだが、SU薬ほど深刻ではなく、臨床では「メリットのほうが大きい」と評価されている。
結果として、「処方頻度:シュアポスト > グルファスト > ファスティック」という現状が形成されていると考えられます




