記事
腹膜透析と血液透析の違いとは?
公開. 更新. 投稿者: 2,300 ビュー. カテゴリ:腎臓病/透析.この記事は約4分30秒で読めます.
目次
腹膜透析と血液透析の違いとは?なぜ腹膜透析は普及しないのか
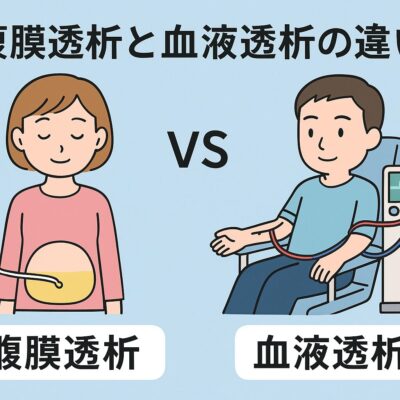
透析医療は、腎不全患者の生命を支える大切な治療法です。透析には大きく分けて「血液透析(HD)」と「腹膜透析(PD)」があります。どちらも老廃物や過剰な水分を除去する治療法ですが、その実施方法や患者の生活への影響、医療資源の利用状況に大きな違いがあります。
日本で腹膜透析が普及しない理由
日本では透析患者の約95%が血液透析を受けており、腹膜透析の普及率は非常に低い水準にとどまっています。その主な理由として以下の点が挙げられます。
●血液透析施設が多く通いやすい:
全国に血液透析を行う医療機関が多く存在し、患者が自宅近くで気軽に通院できる体制が整っています。
●腹膜透析を提供できる施設・スタッフが少ない:
腹膜透析は患者自身や家族が管理することが前提となるため、導入・指導・フォローアップを行える医療スタッフが限られています。
●医療費制度上、患者の自己負担に差がない:
血液透析も腹膜透析も医療保険が適用されており、患者の費用負担はほぼ同じです。自己負担額が同じであれば、患者が積極的に腹膜透析を選ぶ動機は弱くなります。
腹膜透析と血液透析の仕組みの違い
| 腹膜透析 | 血液透析 | |
|---|---|---|
| 場所 | 自宅・会社 | 病院・透析クリニック |
| 透析時間 | 24時間365日 交換は6~8時間ごと、1日4回程度 | 週3回 1回4~5時間 |
| 透析をする人 | 自分 | 医療スタッフ |
| 通院回数 | 月1、2回 | 週3回 |
| 手術 | 腹部にカテーテル植え込み | 腕にシャント作成 |
| 食事制限 | 塩分、水分制限 K:2.0~2.5g/日 | 厳しいK、塩分、水分制限 K:1.5g/日 |
| 合併症 | 細菌性腹膜炎 最終的には血液透析に移行 | 心臓への負荷、血管の石灰化 高K血症 抗凝固剤による出血 不均衡症候群 |
| 原理 | 患者の腹腔内に透析液を注入し、腹膜を半透膜として用い、体内で透析を行う。 | 患者の血気を体外に取り出し(脱血)、ダイアライザー(透析器)の中で透析を行い。体内に戻す(返血)。 |
| 施行方法 | ・在宅で患者自身が施行するため、厳密な自己管理が必要となる。 ・透析は体内で常時行われ、毎日数回の透析液交換を行う。 | ・医療機関で医療従事者によって施行される。 ・1回4時間ほどの透析を1週間に2~3回行う。 |
| 透析効率 | 低い | 高い |
| 全身への影響 | ・体液のバランスの乱れ、栄養状態の悪化、感染症のリスク増大、そして腹膜自体へのダメージ。 | ・透析前後で体液量や組成の変動が大きく、心血管系や腎機能に負担をかけるため、残存腎機能の低下が早い。 |
| 食事制限 | 血液透析よりはゆるい | 厳しい |
| 継続可能期間 | 腹膜の劣化や被嚢性腹膜硬化症が出現するため、治療期間は5~8年が限度 | 半永久的 |
腹膜透析のメリット・デメリット
◎ メリット
●心血管系への負担が少ない
徐々に除水・老廃物除去が行われるため、血圧や心臓への影響が比較的少ないとされています。
●通院頻度が少ない
血液透析のように週3回の通院が不要で、自己管理によって日常生活に柔軟性が生まれます。
●食事・水分制限が緩やか
毎日透析が行われるため、血液透析と比べて厳しい制限が課されにくくなります。
△ デメリット
●カテーテルの埋め込み手術が必要
腹腔にカテーテルを留置するため、導入時には手術が必要です。
●1日4回などの交換作業が煩雑
持続的に管理する必要があり、自己管理が難しい場合は不適です。
●腹膜炎などの合併症リスク
無菌操作に失敗した場合、重篤な腹膜炎に発展することがあります。
●長期使用による腹膜障害
腹膜の機能が低下し、腹膜硬化症に進展する可能性もあります。
●癒着や過去の腹部手術歴がある場合は適応困難
透析にかかる医療費と経済的負担
透析医療は医療保険が適用されており、自己負担は高額療養費制度などにより抑えられています。しかし実際には、透析1人あたり年間約500万円程度の医療費がかかるとされています。
・透析患者数:約33万人(2024年時点)
・年間医療費:約1.5兆円以上
これは、サラリーマンの平均年収より高額であり、20年以上透析が必要な場合は生涯で1億円近いコストがかかる計算になります。国民皆保険制度のもと、これらの医療費は社会全体で負担していることになります。
透析患者に必要な検査値の管理
透析患者では、血液中のリン(P)、カルシウム(Ca)、副甲状腺ホルモン(PTH)のコントロールが重要です。特にリンはもっとも優先して管理すべき項目です。
検査項目と目標値
・血清P値 3.5~6.0 mg/dL
・血清補正Ca値 8.4~10.0 mg/dL
・血清PTH値 60~240 pg/mL
・管理優先度 P > Ca > PTH
リンの蓄積は血管の石灰化や二次性副甲状腺機能亢進症を引き起こし、生命予後を悪化させるため、リン吸着薬などを活用して厳密に管理されます。
透析患者に使用される主な薬剤
透析患者は、腎機能が低下していることに加え、合併症を多数抱えているため、多くの薬剤が必要になります。
症状・疾患と主な治療薬
・腎性貧血:エリスロポエチン製剤、鉄剤
・高血圧:ARB、ACE阻害薬、Ca拮抗薬、β遮断薬
・透析中の低血圧:ミトドリン、ドロキシドパ
・虚血性心疾患:抗血小板薬(アスピリン、チクロピジンなど)
・高P血症:リン吸着薬(炭酸Ca、炭酸ランタン、セベラマー)
・二次性副甲状腺機能亢進症:活性型ビタミンD、シナカルセト
・高K血症:ポリスチレンスルホン酸塩製剤(カリメート等)
・皮膚掻痒症:抗ヒスタミン薬、ナルフラフィン
・栄養障害:エンシュア、IDPN等
注意点として、分子量が大きい薬物や蛋白結合率が高い薬は透析で除去されにくいため、ジゴキシンやアマンタジンなどは少量投与や慎重なモニタリングが必要です。
まとめ:腎臓を守ることが最大の予防
透析は、命を支える重要な医療技術ですが、経済的にも身体的にも大きな負担を伴います。高血圧、糖尿病といった腎障害のリスク因子に早くから介入し、腎臓を守ることが何よりの予防策です。
また、透析患者の生活の質を上げるには、血液透析・腹膜透析の選択を患者のライフスタイルに合わせて柔軟に行える医療体制の整備も求められています。腹膜透析の利点を活かせる患者には、もっと積極的に選択されてもよい時代かもしれません。





1 件のコメント
人工透析はそんなに負担増にはなりません。月額1万円くらいです。(週三回、1回あたり5時間)また障害年金2級ももらえます。