記事
漢方薬はお湯に溶かして飲まなきゃダメ?
公開. 更新. 投稿者: 7,179 ビュー. カテゴリ:漢方薬/生薬.この記事は約6分41秒で読めます.
目次
漢方薬はお湯に溶かして飲む?
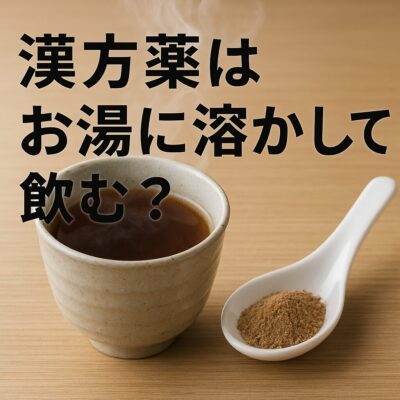
漢方薬と聞くと、昔ながらの「煎じて飲む薬」というイメージを持つ方も多いでしょう。
一方、現在私たちが病院や薬局で受け取るのは、スティック状の顆粒や粉末――いわゆるエキス顆粒剤が主流です。
このエキス顆粒剤、実は「お湯に溶かして飲んだ方がよい」という話を耳にしたことがあるかもしれません。
果たしてそれは本当なのでしょうか? また、なぜお湯に溶かすことが推奨されるのでしょうか?
漢方薬の基本:煎じ薬とエキス剤の違い
もともと漢方薬は、生薬(しょうやく)と呼ばれる植物・鉱物・動物由来の天然物を、煎じて(煮出して)服用するものでした。
この煮出した液体こそが「湯液(とうえき)」であり、葛根湯・小青竜湯・麻黄湯など、「~湯」と名のつく処方名の由来でもあります。
しかし、煎じ薬は以下のような課題がありました。
・調製に時間がかかる(30分〜1時間以上)
・煮出し器具が必要で、外出先では服用しにくい
・保存が効かず、毎回煎じ直す必要がある
そこで登場したのが、エキス顆粒剤です。
これは煎じ薬を一度煎じて、その液体(エキス)を乾燥粉末化したもの。水に溶けやすく、持ち運びにも便利です。
医療機関で処方される「ツムラ」や「クラシエ」などの漢方薬は、このエキス顆粒剤が一般的です。
エキス剤は煎じ薬と同じ効果があるのか?
多くの患者さんが気になるのが、「煎じ薬とエキス剤は同じ効果なのか?」という点でしょう。
この問いに対する答えは、「基本的な薬効は同じだが、完全に同一ではない」です。
なぜなら、煎じ薬では煮出しの温度・時間・水量などによって抽出成分が微妙に変わるのに対し、
エキス剤は製造工程で標準化されており、一定の濃度に調整されています。
つまり、煎じ薬は個別最適化、エキス剤は規格化された漢方薬といえます。
一方で、煎じ薬特有の「香り」「温度」「湯気」などは、エキス顆粒剤では得にくい部分でもあります。
この感覚的な要素が薬効に関係していると考える医師や薬剤師も少なくありません。
「~湯」とつく処方はお湯に溶かして飲むのが理想
「葛根湯」「麻黄湯」「小青竜湯」など、処方名に「湯」がつく漢方薬は、
そもそもお湯で煎じて飲む薬として作られたものです。
したがって、エキス顆粒剤であっても、お湯に溶かして服用するほうが本来の形に近いといえます。
温かいお湯で溶かすことで得られるメリットは以下の通りです。
香り成分(揮発性成分)の再現
温めることで、生薬に含まれる精油成分や芳香成分が立ち上り、鼻やのどの粘膜に直接作用します。
特に風邪薬や鼻炎薬など、呼吸器系の漢方薬ではこの作用が重要です。
味覚・嗅覚刺激による消化促進効果
漢方薬には苦味・辛味・芳香性成分が多く含まれ、これらが胃液分泌や腸蠕動を促す作用を持ちます。
温かい状態で摂取することで、こうした生理的反応がより引き出されます。
吸収促進と胃腸へのやさしさ
温かい湯液は胃腸への刺激が少なく、冷たい水よりも薬効成分の吸収が良いとされます。
特に高齢者や胃腸が弱い方では、お湯で溶かすことで安全性が高まります。
実際の服用方法:お湯の温度と溶かし方
では、実際にどのようにお湯で飲むのが良いのでしょうか。
以下に実践的な方法を紹介します。
標準的な飲み方
・コップに少量(100mL程度)の熱湯またはぬるま湯を入れる
・漢方エキス顆粒を入れてよくかき混ぜる
・香りを感じながら、ゆっくりと服用する
※熱湯すぎると香りが飛んでしまうため、70〜80℃程度が目安です。
※水から電子レンジで温めてもOK。薬局では「湯薬に戻す」と表現することもあります。
ただし注意点も:飲みづらさとコンプライアンス
お湯で溶かすと香りが立ち、味も強く感じられます。
これが苦手な方にとっては、かえって服薬のハードルが上がる場合があります。
実際、漢方エキス剤の添付文書には「お湯で溶かして服用」との記載は明記されていません。
「水または湯で服用」とされており、どちらでも問題はない設計になっています。
そのため薬剤師は、患者の嗜好と継続性(コンプライアンス)を考慮して指導します。
・味や香りが苦にならない → お湯に溶かして飲むよう指導
・飲みにくさを訴える患者 → 顆粒のまま水で服用してOK
つまり、「正しい飲み方」は一律ではなく、続けられる方法がベストということです。
味や香りも薬効の一部
漢方薬の世界では、「五味五性」「気・血・水」「陰陽」などの概念がありますが、
その中でも味と香りは薬理作用と密接に関係しています。
・苦味:鎮静・抗炎症・健胃作用
・辛味:発汗・血行促進・鎮痛作用
・甘味:緩和・滋養作用
・芳香:健胃・駆風作用(お腹の張りを和らげる)
これらの味覚刺激は舌だけでなく、自律神経やホルモン分泌にも影響を与えます。
したがって、味や香りを感じながら飲むこと自体が、漢方の一部の治療行為といえます。
科学的にも理にかなっている「お湯で服用」
実験的にも、お湯に溶かして服用することには一定の科学的根拠があります。
温度によって成分の溶解性や吸収率が変化することが知られています。
具体的には:
・有機酸(酸性成分)は温かい環境で脂溶性が上がり、吸収が促進される
・塩基性成分(麻黄や附子などのアルカロイド)は、温度が高いと脂溶性が下がり、吸収が抑えられる
つまり、「必要な成分を効率よく吸収し、刺激性の強い成分を抑える」方向に働くため、
特に高齢者や体力の低い方にとっては安全で穏やかな服用法といえます。
「湯気」も薬効のうち? 鼻や喉に届く生薬成分
風邪薬として有名な「葛根湯」や「小青竜湯」は、呼吸器系の疾患に使われます。
これらをお湯で飲むと、湯気とともに揮発成分が立ち上り、吸い込むことで鼻腔や咽頭に直接作用します。
これはまさに吸入療法的な側面を持つ漢方薬の特徴です。
たとえば:
・桂皮(けいひ:シナモンの樹皮)には血行促進・発汗作用
・生姜(しょうきょう)には抗炎症・鎮咳作用
・麻黄(まおう)には気道拡張作用
これらの成分は、鼻や喉の粘膜を通しても吸収されやすいことが知られています。
湯気を吸い込むことが、薬効発現の助けになるのです。
「冷たい水で飲む」はダメ?
結論からいえば、冷水で飲んでも薬効が消えるわけではありません。
ただし、胃腸が冷えることで一時的に吸収が遅れたり、苦味成分の感じ方が鈍くなったりする可能性があります。
特に胃腸虚弱・冷え性・高齢者では、温かいお湯で服用するほうが無難です。
逆に、熱があるときや夏場などは、ぬるめの水でも構いません。
現場での薬剤師の対応:個別指導の大切さ
薬局では、患者の症状・体質・嗜好を踏まえて服用法を調整します。
たとえば:
・苦味が強くて飲みにくい → ジュースや蜂蜜に混ぜる(ただし一部処方は不可)
・咽頭炎・鼻炎など → 湯気を吸いながらお湯で服用
・胃腸虚弱 → ぬるま湯でゆっくり服用
重要なのは「毎回続けられること」です。
一時的に頑張っても、苦痛でやめてしまえば意味がありません。
薬剤師はそのバランスを見極めて、最適な服薬方法を提案します。
まとめ:お湯で飲む理由は「昔の名残」ではなく「理にかなった方法」
「漢方薬はお湯で飲むべき」と聞くと、古風で非科学的な印象を持つ方もいるかもしれません。
しかし、実際には科学的にも理にかなった飲み方であり、味や香りを含めて漢方の薬効を最大限に引き出す方法なのです。
ポイントまとめ
・「~湯」とつく漢方薬は、もともと温かい煎液を飲む薬
・お湯に溶かすことで、香りや味が復元し、吸収も良くなる
・特に呼吸器疾患や胃腸系疾患では、湯液の形が理想的
・ただし、飲みにくい場合は無理せず顆粒のままでもOK
・続けられる飲み方が、最も効果的な服用法
漢方薬は「温故知新」の薬です。
古来の知恵を現代の生活に合わせて取り入れることで、その力をより自然に、やさしく体に届けることができます。




