記事
魚を食べると頭がよくなる?長生きする?DHA・EPAの効果
公開. 更新. 投稿者: 2,199 ビュー. カテゴリ:血液/貧血/白血病.この記事は約4分9秒で読めます.
目次
魚を食べると頭がよくなる?長生きする?
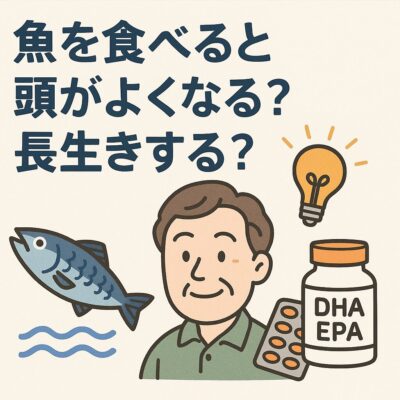
「肉より魚のほうが体にいいんですか?」
薬局の窓口でこんな質問を受けることがあります。確かに健康意識の高い人の間では「魚=健康によい」「頭がよくなる」といったイメージが根強くあります。背景には、魚に多く含まれるDHAやEPAといった“オメガ3脂肪酸”の存在があります。
しかし、その健康効果はどこまで科学的に証明されているのでしょうか?また、サプリメントや医薬品としてのDHA・EPAは、食品と何が違うのでしょうか?
DHA・EPAとは何か?―不飽和脂肪酸の基礎知識
DHA(ドコサヘキサエン酸)とEPA(エイコサペンタエン酸)は、いずれもオメガ3系の多価不飽和脂肪酸(PUFA)に分類されます。
・DHAは主に脳や神経、網膜などに多く含まれ、神経機能や視覚機能との関係が注目されています。
・EPAは主に血液中に存在し、炎症抑制や血液の流動性の向上に関わるとされます。
どちらも体内ではほとんど合成できないため、「必須脂肪酸」として食品から摂取する必要があります。
なぜ魚に多いのか?
海水魚は、冷たい水温の中でも油を固まらせないよう、融点の低い脂肪酸を体に多く蓄えています。これは、不飽和脂肪酸の特徴の一つです。一方で、牛や豚などの陸上動物は、体温が高く、飽和脂肪酸を多く持っています。これが、動物性脂肪と魚油の「質」の違いです。
イヌイットの事例―EPAの注目のきっかけ
EPAが注目されるきっかけとなったのは、北極圏に住むイヌイット(エスキモー)の食生活に関する研究でした。
・イヌイットは魚やアザラシなどEPAを豊富に含む食材を多く摂取
・野菜や穀物が乏しいにも関わらず、動脈硬化や心疾患が少ない
これが、「魚に含まれるEPAが血液をサラサラにして心疾患を防いでいるのでは?」という仮説につながりました。実際、EPAには血小板凝集を抑制し、血液の流動性を高める作用があるとされます。
医薬品とサプリメントのEPA・DHAの違い
◆医薬品のEPA(例:エパデール):
医薬品としてのEPA製剤(エパデールなど)は、純度が高く、用量・効果・副作用の管理が可能です。高脂血症や動脈硬化性疾患に対して保険適用されており、医師の管理下で使用されます。
●副作用としては以下が知られています:
・出血傾向(歯茎からの出血、皮下出血など)
・胃腸症状(吐き気、下痢など)
●注意点: ワルファリンなどの抗凝固薬との併用は要注意です。
◆サプリメントのDHA・EPA:
一方で、サプリメントは食品扱いのため、「健康の維持をサポートする」といった表現は可能ですが、「病気が治る」「頭がよくなる」などの表現は、薬機法上の問題があります。
また、サプリメントの品質や含有量は製品によって大きく異なります。医薬品レベルの品質管理がされていない点には注意が必要です。
DHAで「頭がよくなる」は本当か?
DHAは「脳の栄養素」ともいわれ、脳の神経細胞膜の構成成分でもあります。そのため、「DHAを摂ると頭がよくなる」といった話は広まりました。
しかし、科学的には冷静な評価が必要です。
・1995年の日本脂質栄養学会では、高校生にDHAを補給しても学力向上効果は認められなかったと報告
・一方で、乳幼児の脳発達期におけるDHAの重要性は比較的多くの研究で支持されています
つまり、「成長期には有効かもしれないが、大人が飲んでも劇的な効果は期待できない」というのが現時点での科学的な見解です。
統合失調症とEPAの関係
近年、精神科領域でもEPAの研究が進んでいます。
・統合失調症患者の中には、脳のリン脂質異常が指摘される例がある
・EPA補給により、陽性症状(幻覚や妄想など)が改善する例があると報告
ただし、全例に有効とは限らず、補助療法としての位置づけであることは押さえておきましょう。EPA製剤(エパデール)が処方されている患者を見かけたら、背景に精神科領域での使用があるかもしれません。
明らか食品と薬機法の境界線
「魚を食べると頭がよくなる」「納豆で血液サラサラ」といった表現は、店頭やメディアでもよく見かけます。これらは違法ではないのでしょうか?
実は、薬機法では「明らか食品」という概念があります。
・野菜・魚などの見た目で明らかに食品とわかるものには、ある程度の健康効果を謳っても問題ない
・ただし、加工食品やサプリメントになると、効能・効果を標榜することはできない(虚偽・誇大広告に該当)
つまり、「魚を食べて頭がよくなる」といった表現は、魚売り場でならセーフだが、DHA入りジュースで同じことを言うとアウト、というわけです。
薬剤師としてのアドバイス
●健康な人には食品からの摂取が基本
・日常的に青魚(サバ、イワシ、サンマなど)を摂っていれば、必要量のDHA・EPAは自然に補えます。
●医薬品を服用している人は相互作用に注意
・特に抗凝固薬を使用している人では、EPAの出血傾向リスクに要注意。
●サプリメントを過信しない
・サプリはあくまで“補助”であり、疾患治療や予防を保証するものではありません。
●「頭がよくなる」への過度な期待は禁物
・DHAの摂取で学力が急上昇するというデータは存在しません。栄養、睡眠、学習環境などの総合的な要因が重要です。
まとめ
魚に含まれるDHAやEPAは、確かに体によい成分です。特に動脈硬化や高脂血症の予防、補助療法としての可能性は注目に値します。ただし、それを薬のように信じて摂取しすぎるのは逆効果になりかねません。
薬剤師としては、「食品として適量を継続的に摂ること」が最も自然で安全なアプローチであり、「症状や目的に応じて医薬品としてのDHA・EPAを使うべきか」を判断することが大切です。




