記事
女性ホルモンと癌のリスク
公開. 更新. 投稿者: 5,016 ビュー. カテゴリ:月経/子宮内膜症.この記事は約4分43秒で読めます.
目次
女性ホルモンとがんのリスク
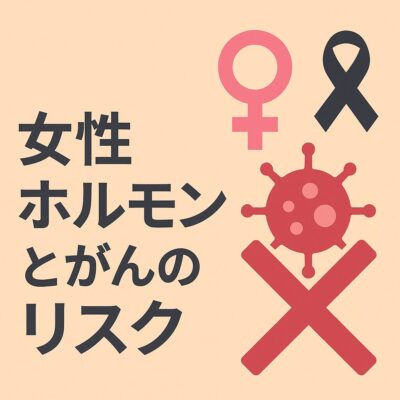
女性の健康に深く関わる女性ホルモン。特にエストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)は、月経や妊娠、骨の健康、美肌などに大きな影響を与える一方で、がんとの関連がたびたび議論されています。この記事では、乳がん・子宮体がん・卵巣がんをはじめとする女性特有のがんとホルモンの関係、さらにホルモン補充療法(HRT)やピルなどとの関連性について、最新の知見も交えながら解説します。
ホルモン感受性のがんとは?
乳がん、子宮体がん(子宮内膜がん)、卵巣がんの多くは、エストロゲンの影響を受けて増殖する性質を持っています。これを「ホルモン感受性のがん」と呼びます。
・乳がん:全体の6〜7割がホルモン受容体陽性(エストロゲンやプロゲステロンに反応)
・子宮体がん:特に閉経後の女性でエストロゲン単独による刺激が長期間続くとリスク上昇
・卵巣がん:排卵の繰り返しによる卵巣上皮の損傷と修復がリスク要因とされ、ピルの使用による排卵抑制でリスク軽減が期待される
エストロゲン製剤の添付文書(例:プレマリン)にも「エストロゲン依存性腫瘍(乳がん・子宮体がん)には禁忌」と記載されています。
乳がんのリスクとホルモン
乳がんリスクを高める要因には、エストロゲン曝露期間の長さが関与しています。
▶ リスクを高める因子:
・初経年齢が早い
・閉経年齢が遅い
・出産経験がない/初産年齢が遅い
・授乳経験が少ない
・閉経後の肥満(脂肪組織からのエストロゲン産生)
・ホルモン補充療法(HRT)の長期使用
▶ 予防因子:
・妊娠・授乳(エストロゲンに拮抗するホルモンが増えるため)
・母乳育児の長期化(疫学的にリスク低下が確認されている)
・ピルの使用による排卵抑制
子宮体がんとホルモン
子宮体がんの約8割はエストロゲンの過剰刺激が原因とされ、特に以下の因子でリスクが上昇します:
・エストロゲン単独のHRT(プロゲステロン併用でリスク低減)
・出産経験がない
・閉経年齢が遅い
・閉経後の肥満
一方、ピルの長期使用は子宮体がんのリスクを明確に減少させることが示されています。
卵巣がんと排卵の関係
卵巣がんは、排卵を繰り返すことで卵巣の表面が損傷し、それが修復される過程で異常が生じやすくなるとされています。そのため、
・ピルによる排卵の抑制
・妊娠・授乳による排卵の中断
が、卵巣がんのリスク低下に寄与すると考えられています。
ホルモン補充療法(HRT)とがんの関係
更年期症状を緩和するために行われるHRTは、エストロゲンとプロゲステロンを外から補充する治療法です。
▶ WHI試験とその誤解
2002年、アメリカで行われたWomen’s Health Initiative(WHI)という大規模臨床試験で、「HRTにより乳がん・心筋梗塞のリスクが増える」と報道され、HRTへの信頼が一時揺らぎました。
しかしこの試験では、
・対象者の平均年齢は63歳(本来の開始時期より高齢)
・肥満者や持病持ちが多かった
といったバイアスがあり、閉経直後の50代前半で開始した場合にはリスクはむしろ小さいことが後に判明しています。
▶ HRTの安全な活用には:
・50代前半での開始が望ましい
・5年以内の短期間使用が基本
・乳がん検診の併用が必須
・経皮剤(貼付剤)で乳がん・血栓リスク低下も期待
HRTの乳がんリスクはフライドポテトと同程度?
HRTによる乳がんリスクは、数字だけを見ると「26%の増加」と言われることがありますが、これは相対リスクの話です。実際には以下の通り:
・WHI試験では、HRT(併用型)5年間の使用で乳がん発症が年間1万人中 8人→11人に増加(+3人)
・絶対リスクでは 年間0.03%の上昇 にとどまります
この程度のリスクは、以下の生活習慣と同等またはそれ以下とも言われます:
要因と乳がん相対リスク
・閉経後の肥満:+20~40%
・飲酒(1日1杯):+10~15%
・運動不足:+15~20%
・フライドポテト多食:+5~15%程度
「フライドポテトと同程度」との表現はインパクトがありますが、患者に伝えるときには絶対リスクと併せて、冷静に説明することが大切です。
ホルモン療法と乳がん治療
乳がんのうち、ホルモン感受性乳がん(ER/PgR陽性)に対しては、ホルモン療法が有効です。
・閉経前:LH-RHアゴニストやタモキシフェンなど
・閉経後:アロマターゼ阻害薬(アナストロゾールなど)
ホルモン受容体陰性の乳がん(特にトリプルネガティブ乳がん)には効果が乏しく、化学療法や分子標的治療(HER2陽性例)などが選択されます。
まとめ
女性ホルモンは、女性の身体にとって欠かせない存在である一方、がんとの関係性も無視できません。しかし、それは「ホルモン=がんになる」という単純な話ではなく、「どう使うか」「どんな条件で使うか」によって、その作用は大きく異なります。
正しい知識を持ち、必要に応じて医師や薬剤師と相談しながら、自分の体に合った選択をしていくことが重要です。




