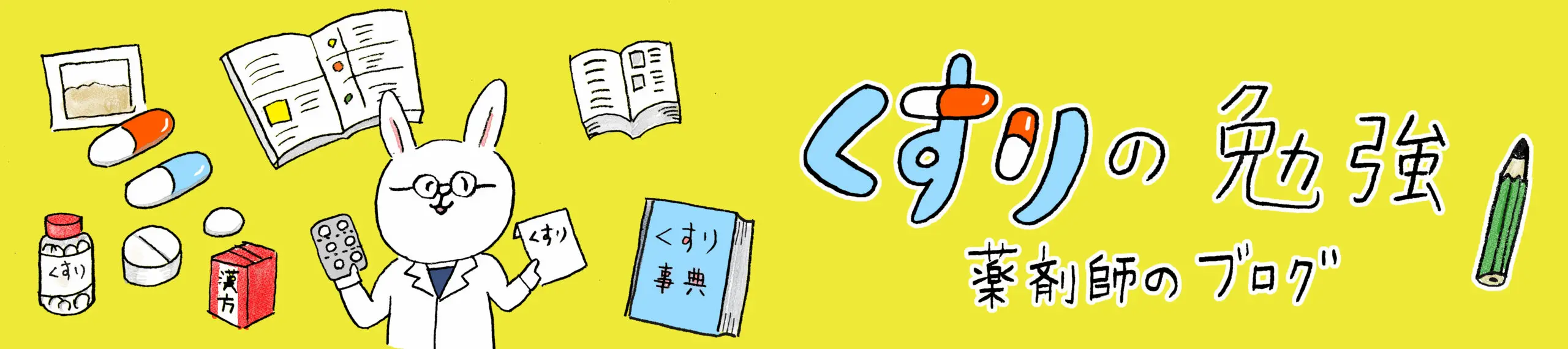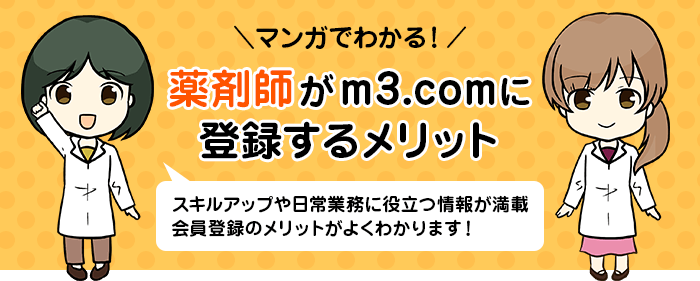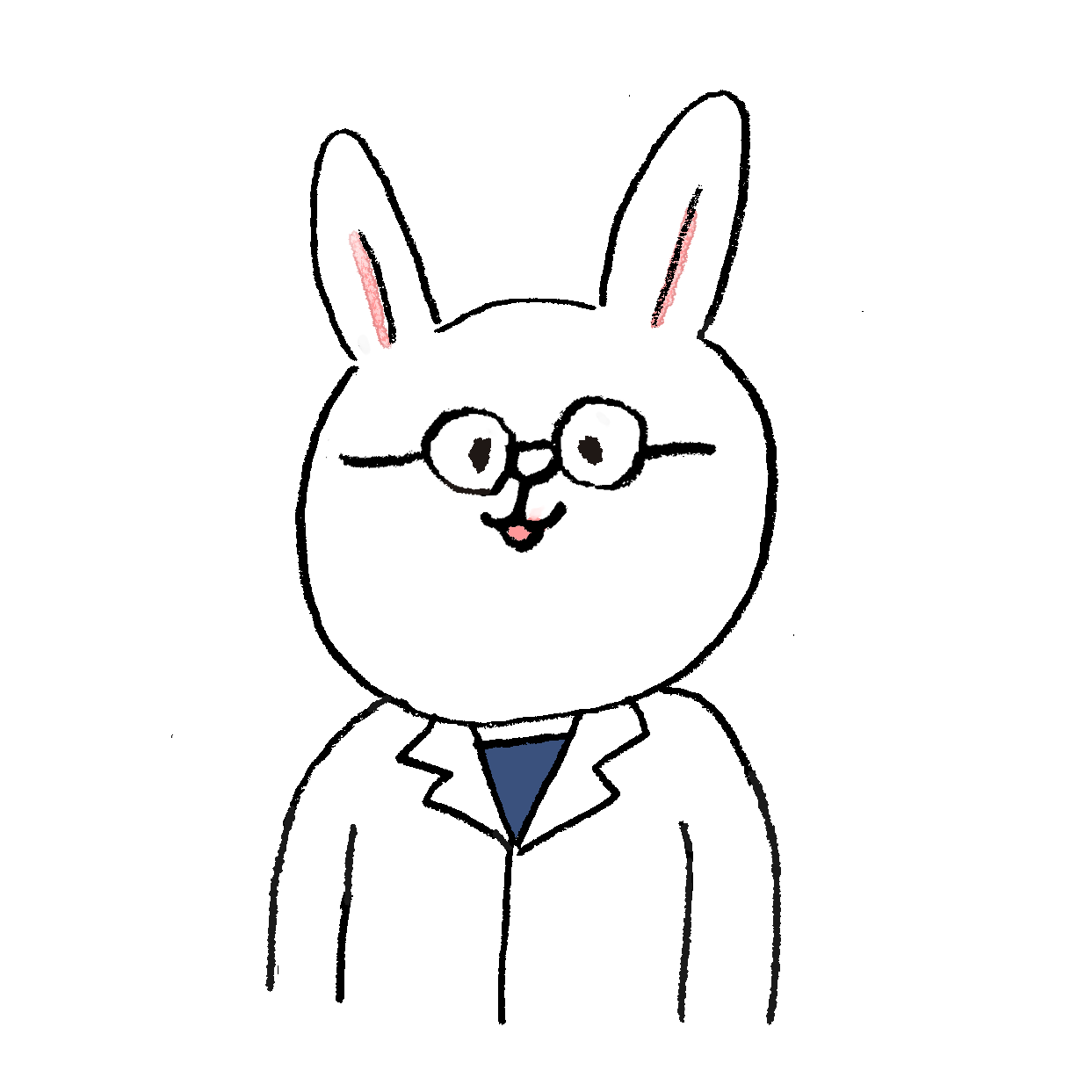記事
ペンタサ錠とペンタサ注腸の併用はOK?―潰瘍性大腸炎治療における位置づけと保険請求の考え方
公開. 更新. 投稿者: 4,982 ビュー. カテゴリ:下痢/潰瘍性大腸炎.この記事は約3分13秒で読めます.
目次
ペンタサ錠とペンタサ注腸の併用はOK?

潰瘍性大腸炎(ulcerative colitis, UC)は、直腸から連続的に口側へ炎症が進展していく慢性の炎症性腸疾患です。症状は血便・下痢・腹痛など多彩で、再燃と寛解を繰り返すことが特徴です。治療の中心となる薬剤のひとつが「メサラジン(5-ASA)」であり、日本ではペンタサ®(mesalazine)をはじめ、アサコール®やリアルダ®などが広く用いられています。
その中でもペンタサは錠剤・顆粒・注腸液・坐剤と複数の剤形を持ち、病変の部位や重症度に応じて組み合わせて使用されることがあります。では、ペンタサ錠とペンタサ注腸を併用することは保険診療上認められるのでしょうか。
ペンタサの剤形と特徴
まず、ペンタサの各剤形の特徴を整理しておきます。
錠剤・顆粒
・経口投与により、小腸から大腸全体に広く薬剤を送達できる。
・ただし、直腸やS状結腸の末端まで十分な濃度が届かないことがある。
注腸液
・肛門から注入することで、下行結腸~直腸に直接作用。
・「脾湾曲部より口側の炎症には効果が期待できない」と添付文書に記載されている。
坐剤
・直腸炎に適応。直腸局所に高濃度で作用。
潰瘍性大腸炎は「直腸からびまん性に炎症が広がる」という特徴があるため、病変部位に応じた剤形選択が極めて重要です。
ペンタサ錠と注腸の併用が検討される場面
全大腸炎型や左側大腸炎型のUCでは、内服だけでは十分に炎症コントロールできないことがあります。特に遠位大腸(直腸~下行結腸)に強い活動性病変がある場合、経口剤のみでは薬剤到達が不十分です。
そのため、全身的なコントロールを目的とする内服療法に、局所の炎症抑制を目的とした注腸や坐剤を併用する戦略が推奨されます。
保険請求上の取り扱い
「支払基金における審査の一般的な取扱い(医科)」では、潰瘍性大腸炎治療におけるメサラジン製剤の内服+局所投与併用について明記されています。
左側あるいは全大腸炎型で遠位大腸の活動性がある場合には、内服療法に加えて局所投与の併用が望ましいとされており、原則として併用は認められています。
つまり、ペンタサ錠と注腸の併用は「保険請求上も正当」と判断できます。
治療指針における位置づけ
厚生労働省研究班(鈴木班)による「潰瘍性大腸炎・クローン病診断基準・治療指針(平成27年度改訂版)」でも、次のように記されています。
寛解導入療法
・軽症・中等症の左側大腸炎型、全大腸炎型においては、内服と注腸の併用で効果増強が期待できる。
・重症例でも注腸の追加が認められている。
寛解維持療法
・内服と注腸の併用は有用であり、再燃抑制に寄与する。
このように、診療ガイドライン上でも 内服+注腸の併用は科学的根拠に基づいて推奨されていることが分かります。
実際の臨床現場での意義
・経口薬だけでは直腸炎症が残存しやすい → 注腸・坐剤を追加することで局所寛解が得られやすい。
・注腸単独では口側病変のコントロールが不十分 → 錠剤との併用で全体をカバー。
つまり、「内服は全体を、注腸は末端を」という補完関係にあります。
他剤との比較と応用
アサコール®(mesalazine腸溶錠)やリアルダ®(MMX製剤)も存在しますが、いずれも経口剤であり、局所送達には限界があります。
そのため、たとえば「アサコール錠+ペンタサ坐剤」などの組み合わせも臨床的には行われ、保険請求上も合理的と解釈されるケースがあります。
保険請求と疑義照会の実務
薬局実務では、ペンタサ錠+注腸の処方を見た際に「重複投与ではないか?」と疑義照会を検討することもあります。しかし、上述の通り 併用は治療指針上推奨され、支払基金でも認められているため、原則的には問題ありません。
むしろ、こうした事例は広く周知されるべきであり、不必要な疑義照会を減らすことにつながります。
まとめ
・ペンタサには錠剤・顆粒・坐剤・注腸液があり、作用部位が異なる。
・潰瘍性大腸炎は直腸から口側に広がるため、病変部位に応じて剤形を組み合わせる必要がある。
・支払基金の審査取扱いや厚労省研究班の治療指針では、内服と注腸の併用が原則認められ、推奨されている。
・保険請求上も妥当であり、不必要な疑義照会は避けられる。
・今後はアサコールやリアルダなど他のメサラジン製剤との併用パターンについても整理し、薬剤師として正しく対応することが重要。