記事
細胞壁を持つ菌・持たない菌・細胞内寄生菌
公開. 更新. 投稿者: 2,700 ビュー. カテゴリ:皮膚感染症/水虫/ヘルペス.この記事は約3分23秒で読めます.
目次
細胞壁を持つ菌・持たない菌・細胞内寄生菌─抗菌薬との関係と治療戦略
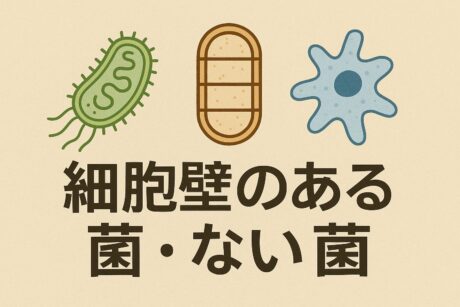
「抗生物質が効かない」と聞くと、多くの人が“耐性菌”を思い浮かべるかもしれません。しかし、それ以前の問題として「そもそも効く構造を持っていない」微生物も存在します。
たとえば、「細胞壁がない」「細胞内に寄生する」といった特徴を持つ病原微生物に対して、効果を発揮できない抗菌薬もあります。
抗菌薬の基本分類と作用機序
抗菌薬は、その作用機序により次のように分類されます:
| 分類 | 作用対象 |
|---|---|
| 細胞壁合成阻害薬 | ペニシリン系、セフェム系など |
| 細胞膜機能阻害薬 | ポリミキシン、アムホテリシンBなど |
| タンパク合成阻害薬 | マクロライド系、テトラサイクリン系など |
| 核酸合成阻害薬 | キノロン系、リファンピシンなど |
| 葉酸合成阻害薬 | スルファ薬、トリメトプリムなど |
とくに「細胞壁合成阻害薬」は、細胞壁を持つ細菌に選択的に作用する代表的な抗菌薬群です。細胞壁は細菌の構造的な特徴であり、哺乳類細胞には存在しないため、副作用が少ない“選択毒性”が得られるというメリットがあります。
細胞壁を持つ菌と持たない菌の違い
● 細胞壁を持つ代表的な細菌
・グラム陽性菌(例:黄色ブドウ球菌、レンサ球菌など)
・グラム陰性菌(例:大腸菌、緑膿菌など)
・結核菌(ミコール酸を含む特殊な細胞壁)
これらの菌は、ペプチドグリカンという構造を細胞壁に持っており、βラクタム系抗菌薬(ペニシリン系、セフェム系など)はこの合成を阻害します。
● 細胞壁を持たない細菌:マイコプラズマ属
マイコプラズマは、細胞壁を持たない非常に小型の細菌です。細胞膜だけで生存しているため、細胞壁合成阻害薬は無効です。代わりに、マクロライド系やテトラサイクリン系のようなタンパク合成阻害薬が有効とされます。
細胞内寄生菌:薬剤が届きにくい敵
一部の細菌は、ヒトの細胞の中に入り込んで増殖します。これが「細胞内寄生菌」です。
● 主な細胞内寄生菌
・クラミドフィラ属(旧クラミジア)
・リケッチア属
・レジオネラ属
これらの菌は、一見通常の細菌と同じように見えますが、宿主細胞の中に身を隠すことで、抗菌薬や免疫の攻撃から逃れます。
● 細胞内寄生菌にβラクタムが効きにくい理由:
βラクタム系抗菌薬は、細胞壁合成を阻害しますが、細胞の外側に作用する薬剤であり、ヒト細胞の中まで浸透しづらいという欠点があります。
一方、マクロライド系(クラリスロマイシンなど)は細胞内移行性が良く、細胞内寄生菌に効果を発揮します。よって、非定型肺炎などでは、マクロライド系やニューキノロン系が第一選択となります。
真菌と細菌の違い:細胞壁構造と抗真菌薬の標的
真菌は真核生物であり、細菌(原核生物)とは根本的に構造が異なります。
● 真菌の特徴
・真核生物であり、核を持つ
・細胞壁を持つ(主要成分はβ-D-グルカン、キチン)
・細胞膜の主成分はエルゴステロール
この点が、人間と共通する構造を持つ真菌に対して選択的に効く薬を開発する難しさにもつながっています。
● 抗真菌薬の選択毒性
抗真菌薬は、ヒトと真菌の違いをターゲットにします。
・アゾール系:エルゴステロールの合成阻害
・ポリエン系:細胞膜のエルゴステロールに結合
・キャンディン系:1,3-β-D-グルカンの合成阻害
とくに、1,3-β-D-グルカン合成酵素はヒトには存在せず、抗真菌薬の選択毒性を生む“理想的な標的”とされています。
水虫はなぜ治りにくいのか?
水虫の原因は皮膚に感染する真菌(白癬菌)です。中でもよく知られるのが:
・トリコフィトン・ルブラム
・トリコフィトン・トンズランス(新型水虫菌)
・カンジダ属
白癬菌はケラチンを栄養源とし、皮膚の角質層、爪、毛髪に感染します。とくにトンズランス菌は、頭部や体部への感染を起こしやすく、重症化すると脱毛や膿瘍の原因となることもあります。
柔道やレスリングなど皮膚接触の多い競技では、この新型菌の感染が集団発生するケースも報告されています。
ウイルス・真菌・細菌:何が違う?
以下のように、病原微生物は構造的に大きく異なります。
| 微生物 | 核を持つ | 細胞壁 | 細胞内寄生 | 抗菌薬の効果 |
|---|---|---|---|---|
| 細菌 | × | 〇 | 一部〇 | 効果あり |
| 真菌 | 〇 | 〇(βグルカン) | × | 抗真菌薬のみ有効 |
| ウイルス | × | × | 必須(細胞寄生) | 抗菌薬無効(抗ウイルス薬) |
この違いを理解しておくと、どの薬がどんな病原体に効くのかが見えてきます。
細胞壁と治療戦略の関係性
抗菌薬が効くかどうかは、病原体の細胞構造に大きく左右されます。
・細胞壁がある:βラクタム系が有効
・細胞壁がない:細胞膜・タンパク合成阻害薬が有効
・細胞内に潜む:細胞内移行性のある薬剤が必要
・真菌:βグルカンやエルゴステロールを標的とした抗真菌薬が必要
水虫などの真菌感染症は「治りにくい」と言われますが、その背景には「人間の細胞と似ているために薬が効きにくい」という構造的な問題があります。
一方で、細菌感染症では「どの構造を標的とするか」によって薬剤選択が大きく変わるため、正確な診断と薬剤選定が必要です。




