記事
医薬分業が医療費増加の原因?
公開. 更新. 投稿者: 1,103 ビュー. カテゴリ:調剤報酬/レセプト.この記事は約3分44秒で読めます.
目次
医薬分業が医療費増加の原因?
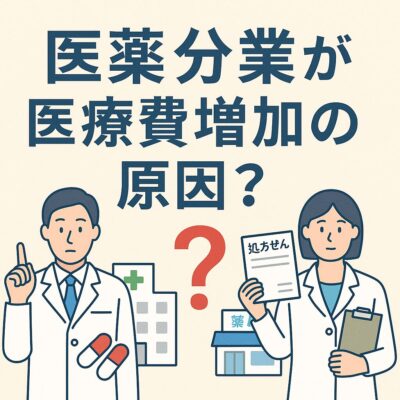
医薬分業には、賛否両論が根強く存在しています。院内処方の方が費用が安く済む場合があることから、医薬分業によって医療費が増大しているという見方もあります。逆に、安全性や適正使用の観点から医薬分業を支持する声もあります。本記事では、そうした医薬分業の現状と問題点を、制度の原点に立ち返って冷静に検証します。
院内処方と院外処方:何が違う?
院内処方とは、医療機関内で診察から薬の受け取りまでを一括して行う方式。一方、院外処方とは、医師が発行した処方せんを持って、外部の調剤薬局で薬を受け取る方式です。
患者の自己負担額に注目すると、院内処方の方が安価に感じられることがあり、そのために「分業はコスト増につながっている」との批判が根強くあります。
しかし、両者の費用差は診療報酬制度に基づいて調整されているものであり、制度改定によって増減可能な構造です。費用だけに注目するのではなく、その背景や設計意図を理解することが重要です。
医薬分業の本来の目的
医薬分業の核心は、「診療と調剤を分離することで安全性を高める」ことです。診察した医師と、薬を調剤・監査する薬剤師がそれぞれの立場で薬剤を確認することで、ダブルチェックが働き、
・重複投薬
・相互作用
・投与量ミス
などを防ぐ機能があります。
また、かつて問題とされた「薬価差益」の抑制も大きな目的の一つでした。医師が安価に薬を仕入れ、高額な薬価で収益を上げる構造を排除するため、薬の流通に透明性を求めた結果が医薬分業です。
では薬局は儲かっているのか?
かつては調剤薬局にも薬価差益が存在しましたが、度重なる薬価改定によって、その利益幅は縮小し、現在ではほぼゼロに近い水準となっています。在庫の期限切れや返品不可のリスクを考えると、マイナスになることすらあります。
そのため薬局は現在、
・調剤技術料
・服薬指導料
・地域支援体制加算
など、薬剤師による対人業務で評価される体制へと移行しています。
人件費と薬局経営の現実
薬局経営において、薬剤師の人件費は重要なコスト項目です。経営分析では「労働分配率」が目安とされ、これは
労働分配率 = 人件費 ÷ 総利益 × 100
で示されます。
また、会計上は薬の在庫が利益として計上されるため、実際に売れていない薬でも税負担が生じます。このため、多くの薬局では適正在庫や在庫回転率を重視した運営が求められます。
今後の薬局に求められる役割
調剤薬局は今、単なる薬の供給拠点から、
・服薬アドヒアランスの支援
・残薬管理
・在宅医療連携
といった「患者支援機関」へと進化しています。厚生労働省も「かかりつけ薬剤師・薬局」の普及を推進しており、処方監査だけでなく生活に寄り添う健康支援が求められています。
医薬分業は医療費を押し上げているのか?
医薬分業が医療費の増大に寄与している側面があることは否定できません。しかし、単にコストだけを見て「悪」とするのは早計です。
本質的な問題は、
・薬局の乱立と立地バランス
・分業の名の下に生まれる実態なき提携
・対物業務に偏重した評価体制
など、制度運用や構造的な課題にあります。
まとめ
・医薬分業には、薬の安全使用と透明性の確保という明確な意義がある。
・一方で、制度運用の課題や経済的側面からの再検討も必要。
・薬局は今後、「対人業務」重視の方向へと舵を切る必要がある。
・医療提供体制全体として、医師・薬剤師・患者の連携が重要。
医薬分業は制度的な完成形ではなく、常に見直しと改善を必要とする「進化途上の仕組み」です。医療費、患者利便性、薬剤の適正使用という複数の視点を持って、冷静に評価していくことが求められています。




