記事
スティグマをなくすためにアドボカシーに取り組む?
公開. 更新. 投稿者: 712 ビュー. カテゴリ:服薬指導/薬歴/検査.この記事は約4分53秒で読めます.
目次
スティグマをなくすためにアドボカシーに取り組む?
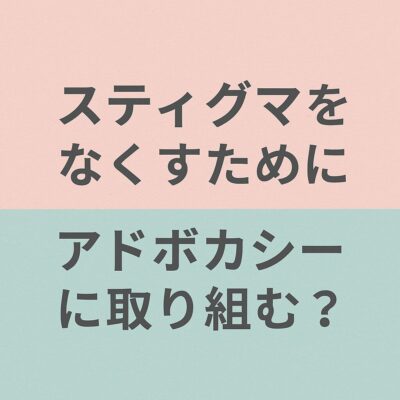
近年、医療現場や学会、そして行政の資料などでも「スティグマ」「アドボカシー」という言葉を耳にする機会が増えてきました。しかし、薬局で日常的に使う言葉かといえば、まだまだ馴染みが薄いのが現状です。
「難しい横文字はちょっと苦手」「実際の業務とどう関係あるの?」と感じる薬剤師も少なくないでしょう。
実際に薬局における疾患別対応マニュアル(糖尿病の章)にも、「『スティグマ』や『アドボカシー』という言葉を聞くが、どういう意味か」というQ&Aが掲載されています。これはまさに、現場で働く薬剤師にとって「用語の理解が十分でない」というニーズを反映しているといえます。
スティグマとは何か?
定義
「スティグマ(stigma)」とは、日本語で「烙印」「汚名」「偏見」と訳されることが多い言葉です。医学・医療の文脈では、ある病気や状態を持っていることによって社会から差別や偏見を受けることを指します。
糖尿病とスティグマ
糖尿病の患者さんは「生活習慣が悪いから病気になった」と思われやすく、その結果として偏見や差別を受けることがあります。
たとえば:
・「自己管理できないから糖尿病になったのだ」という決めつけ
・インスリン注射をしている姿を見られると「重症だ」とレッテルを貼られる
・糖尿病患者=甘いものが好き、太っている、という安易なイメージ
こうした認識は、患者の自己肯定感を下げ、治療意欲の低下を招きます。これがまさに「スティグマ」です。
スティグマが生む悪循環
スティグマがあると、患者は病気について周囲に打ち明けにくくなり、治療や相談を避ける傾向が強まります。結果として病状が悪化し、さらに「やっぱり糖尿病は怖い病気だ」という偏見を助長する——。この悪循環が社会の中で繰り返されてしまいます。
アドボカシーとは何か?
定義
「アドボカシー(advocacy)」は直訳すると「権利擁護」「代弁」「政策提言」などの意味を持ちます。医療現場で使われるときには、患者やその家族が持つ権利を守り、声を社会や行政に届ける活動を指します。
糖尿病とアドボカシー
糖尿病に関しては、日本糖尿病協会や患者団体が「スティグマをなくそう」というキャンペーンを展開しています。これはまさにアドボカシー活動の一環です。
・糖尿病患者は怠け者ではない
・適切な治療と支援があれば社会で十分に活躍できる
・偏見をなくし、患者が暮らしやすい社会をつくる
こうしたメッセージを発信することが「アドボカシー」であり、社会の意識変容を目指す取り組みです。
薬局におけるスティグマとアドボカシー
では、薬局に勤める薬剤師にとって、これらの概念はどのように関わってくるのでしょうか。
言葉づかいに気を配る
服薬指導の中で、何気ない一言が患者にスティグマを与えてしまうことがあります。
「この薬はあなたの怠けた生活習慣のせいで必要なんですよ」
「こんなに血糖値が高いなんて、自分でコントロールできなかったんですね」
こうした言葉は患者を深く傷つけます。薬剤師は「あなたは病気のせいで大変な思いをしているが、治療によって良くできる」という寄り添うメッセージを意識する必要があります。
患者の声を代弁する
患者が医師に言えなかった悩みを薬局で打ち明けることはよくあります。
「インスリン注射を会社で打つのが恥ずかしい」「薬を飲んでいると同僚に知られるのが嫌だ」など、これはまさにスティグマの表れです。
薬剤師はその声を受け止め、医師にフィードバックしたり、生活上の工夫を一緒に考えたりすることが「小さなアドボカシー」です。
情報発信の担い手になる
薬局は地域住民にとって身近な医療資源です。待合室の掲示物や薬局のホームページで「糖尿病は正しく管理できる病気」「糖尿病患者への偏見をなくそう」と発信することもアドボカシー活動のひとつです。
他疾患におけるスティグマ
糖尿病に限らず、さまざまな疾患にスティグマが存在します。
・精神疾患(うつ病=弱い人間という偏見)
・HIV感染症(「自己責任」論による差別)
・がん(死を連想される)
・肥満(だらしないというイメージ)
薬剤師は、こうした疾患に対しても偏見を助長しない言葉づかいを心がけ、患者を支える立場であることが求められます。
薬剤師に求められる姿勢
スティグマとアドボカシーという概念は、単なる横文字ではありません。日々の薬局業務の中に直結しています。
知識を持つこと
スティグマやアドボカシーの意味を理解し、患者に説明できる。
態度に表すこと
偏見を生まない言葉を選び、患者に安心を与える。
地域に発信すること
ポスター、薬局だより、Web発信などを通じて啓発活動を担う。
こうした積み重ねが、薬局薬剤師としてのアドボカシー活動につながります。
まとめ
・スティグマとは、病気に対する偏見や差別のこと。
・アドボカシーとは、その偏見をなくし、患者の権利を守るための活動。
・糖尿病をはじめ、さまざまな疾患にスティグマが存在する。
・薬剤師は言葉づかいに注意し、患者の声を代弁し、地域に発信することでアドボカシーを実践できる。
「スティグマをなくすためにアドボカシーに取り組む」——これは大きな社会運動に限らず、薬局での小さな一歩から始められることです。日々の服薬指導が、そのまま患者の尊厳を守り、地域に希望を広げるアドボカシーになるのです。




