記事
奏効率と生存率の違い ―「腫瘍が小さくなった=延命」ではない
公開. 更新. 投稿者: 905 ビュー. カテゴリ:癌/抗癌剤.この記事は約4分45秒で読めます.
目次
奏効率と生存率の違い ―「腫瘍が小さくなった=延命」ではない
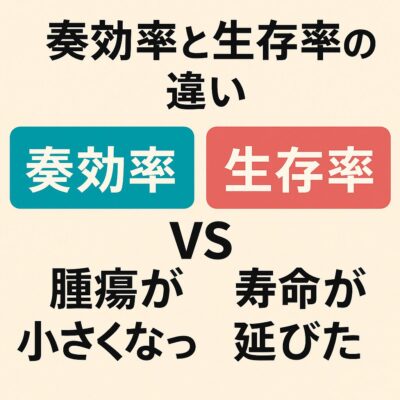
抗がん剤や新しい治療薬の効果を説明するときに、「この薬で腫瘍が小さくなった」とか「効いている人が◯割いた」という言葉を耳にすることがあります。医療関係者であっても、こうした表現を聞くと「良い薬なんだ」と直感的に思いやすいでしょう。
しかし、腫瘍が縮小した割合(奏効率)と、実際に患者さんの寿命を延ばす(生存率)ことは必ずしも一致しません。
奏効率とは?
定義
奏効率(Response Rate, RR)とは、抗がん剤などの治療を受けた患者のうち、腫瘍が一定以上縮小した患者の割合を指します。
腫瘍の縮小効果は国際的に RECIST基準(固形がんの効果判定基準)に従って判定されることが多く、以下のカテゴリーに分類されます。
・CR(Complete Response/完全奏効):腫瘍が完全に消失した状態
・PR(Partial Response/部分奏効):腫瘍径が基準より一定割合以上縮小した状態(通常30%以上縮小)
・SD(Stable Disease/不変):腫瘍が増大も縮小もしていない状態
・PD(Progressive Disease/進行):腫瘍が一定割合以上増大、または新たな病変が出現した状態
そして、
奏効率(ORR)=CR+PRの割合
として表されます。
生存率とは?
一方、生存率(Survival)とは、患者がどれだけ長く生存できるかを示す指標です。
・OS(Overall Survival/全生存期間):治療開始から死亡までの期間。最も重要なアウトカム。
・PFS(Progression-Free Survival/無増悪生存期間):がんが進行せずに維持できた期間。
生存率は「腫瘍が縮小したかどうか」ではなく、患者の命の長さに直結する指標です。
奏効率と生存率の関係
「腫瘍が縮小すれば、当然生存期間も延びるのでは?」と思うかもしれません。確かに、奏効率と生存率が一致する場合もあります。
しかし現実には、
・奏効率は高いが、生存期間が延びない薬
・奏効率は低いが、生存期間が延びる薬
も存在します。
奏効率が高いのに生存率が改善しない場合
例:ベバシズマブ(アバスチン®)
ベバシズマブは血管新生阻害薬として知られ、がんの進行を抑える効果が期待されて導入されました。
・奏効率や無増悪生存期間(PFS)は改善するものの、
・全生存期間(OS)には有意な延長が認められない試験結果も多いのです。
実際、乳がんに対する適応は米国では撤回されました。日本では大腸がんや肺がんなどに使われていますが、「腫瘍縮小=延命」とは限らない代表例といえます。
なぜか?
・腫瘍の縮小が一時的で、すぐ再増大する
・強い副作用で治療継続が困難になる
・腫瘍の性質により、生存そのものには結びつかない
奏効率は低いが生存率が改善する場合
例:免疫チェックポイント阻害薬(オプジーボ®、キイトルーダ®)
ニボルマブ(オプジーボ®)、ペムブロリズマブ(キイトルーダ®)などの免疫チェックポイント阻害薬は、日本でも承認され広く使われています。
これらは奏効率は20〜30%程度と決して高くありません。
しかし、奏効した患者では効果が長期間持続することが多く、結果として全生存期間(OS)の改善が示されました。
つまり「一部の患者にしか効かないが、効いた人は長く生きられる」という特徴があります。
奏効率と生存率のズレをどう理解すべきか
短期 vs 長期
奏効率は「短期的な腫瘍縮小」を見る指標。生存率は「長期的な生命予後」を見る指標。
部分集団への効果
奏効率が高くても、その効果が長続きしないならOSは改善しない。
逆に奏効率が低くても、長期生存が得られる患者がいればOSは改善する。
副作用やQOLも影響
腫瘍が縮小しても、副作用が強く生活の質や全身状態を損ねれば、結果的に生存期間は延びない。
医療者が注意すべき点
・「奏効率が高い=良い薬」と短絡的に考えないこと
・最終的に重要なのはOS(生存期間)とQOL(生活の質)
・薬の評価は「ORR(奏効率)」「PFS(無増悪生存期間)」「OS」「QOL」を総合的に見て判断する必要がある
患者への説明の工夫
患者さんや家族から「この薬は効くんですか?」と聞かれたとき、医療者はどう説明すべきでしょうか。
「効く」という言葉を「腫瘍が小さくなること」と解釈する人もいれば、「長生きできること」と解釈する人もいます。
そのため、「腫瘍が小さくなる人はいますが、それが必ずしも長生きにつながるわけではありません」と伝えることが大切です。
治療のゴールは「延命」や「症状緩和」であることを共有する必要があります。
まとめ
・奏効率(ORR)=腫瘍縮小効果を示す短期的な指標
・生存率(OS)=命をどれだけ延ばせるかを示す究極の指標
・奏効率が高くてもOSが延びない薬(例:ベバシズマブ)、逆に奏効率が低くてもOSを延ばす薬(例:免疫チェックポイント阻害薬)も存在する
・薬の評価や患者説明では、「腫瘍が小さくなる=生存が延びる」とは限らないことを理解し、複数の指標を見て総合的に判断する必要がある




