記事
レキサルティが認知症に効く?
公開. 更新. 投稿者: 1,934 ビュー. カテゴリ:認知症.この記事は約6分20秒で読めます.
目次
- 1 レキサルティと「アルツハイマー型認知症に伴う焦燥・易刺激性・興奮」の適応
- 2 適応の中身を整理する:対象は「アルツハイマー型認知症」限定
- 3 用法・用量:ゆっくり始め、必要最小限で
- 4 有効性エビデンスの位置づけ
- 5 安全性:ブラックボックス相当の警告と「慎重投与」の原則
- 6 「国内初のBPSD適応」の意味
- 7 どんな患者に向く?:適応と現場感のすり合わせ
- 8 使い方の実際:開始から評価、減量・中止まで
- 9 服薬指導・家族への説明のポイント(薬剤師向け)
- 10 他剤との位置づけ:これまでと何が違う?
- 11 よくある疑問Q&A
- 12 まとめ:レキサルティは「BPSD薬」ではなく、ADの特定症状に対する“慎重な選択肢”
レキサルティと「アルツハイマー型認知症に伴う焦燥・易刺激性・興奮」の適応
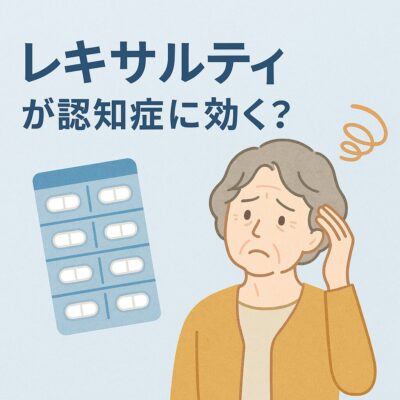
2024年9月、抗精神病薬レキサルティ(ブレクスピプラゾール)の効能・効果に、日本で新しい適応が追加されました。内容は、「アルツハイマー型認知症に伴う焦燥感、易刺激性、興奮に起因する、過活動又は攻撃的言動」に対する治療です。これは日本で初めて、いわゆるBPSD(行動・心理症状)に対して明確に適応を取得した薬剤になります。
この承認により、これまで非薬物的介入を基本とし、薬物はやむを得ない場合に「適応外使用」に頼ることが多かった日本の臨床現場に、適応に沿った選択肢が加わりました。なお米国では2023年に、同薬が「アルツハイマー病による認知症に関連するアジテーション(agitation)」でFDAの承認を受けており、日本の承認はこれに続く形と言えます。
適応の中身を整理する:対象は「アルツハイマー型認知症」限定
添付文書では、今回の適応はアルツハイマー型認知症(AD)に限ることが明確に示されています。レビー小体型認知症や前頭側頭型認知症など他の認知症に伴う同様の症状については、有効性・安全性は確立していません。したがって「認知症全般」ではなくADに限定される点は、服薬指導や問い合わせ対応で重要です。
さらに、過活動や攻撃的言動が「焦燥・易刺激性・興奮」に起因していることを確認し、非薬物的介入で十分な効果が認められない場合に限って投与を開始する、と手順が定義されています。適応の射程と使用条件がかなり具体的に書き込まれているのが特徴です。
用法・用量:ゆっくり始め、必要最小限で
ADに伴う焦燥・易刺激性・興奮に対するレキサルティの開始用量は1日0.5mg、1週間以上の間隔をあけて1mg/日へ増量、忍容性に問題がなく効果不十分なら最大2mg/日まで検討できます(いずれも1日1回投与)。過量投与を避け、最小有効量を探る姿勢が求められます。
CYP2D6/CYP3A阻害薬併用時の用量調整や、2mgへ増量後のアカシジア等の錐体外路症状のモニタリング強化など、実施上の注意も細かく規定されています。高齢者・多剤併用という現場の現実を踏まえ、相互作用チェックは必須です。
有効性エビデンスの位置づけ
今回の日本の審査は、国際老年精神医学会(IPA)が定義するアジテーション(Agitation)を満たす患者を対象とした国内第Ⅱ/Ⅲ相試験等の成績に基づいています。日本の審議結果報告書や添付文書の「臨床成績」には、対象症状の定義・組入れ基準・評価指標が明記され、有効性と安全性のバランスに関する判断材料が示されています。
海外では、FDAが2023年に「ADに伴うアジテーション」として承認し、その後も延長試験の事後解析などが報告されています。これらは主に興奮・怒り・落ち着きのなさ・攻撃性といった介護負担の大きい症状に対し、臨床的に意味のある改善を示すという文脈で共有されています。
安全性:ブラックボックス相当の警告と「慎重投与」の原則
「高齢認知症患者における抗精神病薬投与で死亡リスクが増加する」との海外報告は、レキサルティでも例外ではありません。国内プラセボ対照試験でも、関連は明確でないものの死亡例が本剤群のみで報告されています。このため、患者選択は慎重に、投与中は状態を注意深く観察するよう強く求められています。
そのほか、錐体外路症状(アカシジア、パーキンソニズム、遅発性ジスキネジアなど)、起立性低血圧、糖代謝異常、鎮静・傾眠など、第二世代抗精神病薬で注意すべき副作用は共通です。脳血管イベント(脳卒中等)についても、抗精神病薬全般で高齢者にリスク増加が示唆されている点を念頭に、投与量・期間は必要最小限、効果再評価を定期的に行うのが基本です。
「国内初のBPSD適応」の意味
これまで日本では、BPSDに対して適応外で抗精神病薬や抗うつ薬、睡眠薬が用いられてきました。実臨床のガイドラインでも、非薬物的介入を第一選択、薬物は限定的にという立場が一貫していました。今回、レキサルティが「ADに伴う焦燥・易刺激性・興奮に起因する過活動・攻撃的言動」で国内初の適応を得たことは、薬物療法の位置づけが“ゼロから一に”変化したことを意味します。とはいえ、適応はAD限定、実施条件も非薬物介入の不十分が前提であり、「何でも薬で」という方向転換ではありません。
BPSD対応の最新版ガイドラインも、環境調整・心理社会的介入を土台にしつつ、症状・重症度・危険性に応じて薬剤を慎重に追加するという基本を堅持しています。
どんな患者に向く?:適応と現場感のすり合わせ
向きやすいケース(例)
・診断がアルツハイマー型認知症である
・焦燥・易刺激性・興奮が明らかで、そこから過活動や攻撃的言動が反復している
・非薬物的介入(環境調整、介護者教育、疼痛・便秘・睡眠障害など身体要因の是正)を行っても不十分
・転倒・虐待・離院リスクなど切迫した安全上の懸念がある、または介護崩壊が迫る重症度
慎重にすべき・適さないケース(例)
・AD以外の認知症(DLB、FTD等)
・せん妄や急性身体疾患による行動異常が疑われる
・抗精神病薬で過去に重篤な副作用歴がある
・脳血管イベントの既往、重度の起立性低血圧、重篤な代謝性疾患などリスクが高い
これらは適応と添付文書の注意を臨床的にかみ砕いたものです。「誰に」「いつ」「どれくらいの期間」という見極めが成否を分けます。
使い方の実際:開始から評価、減量・中止まで
1.ベースライン評価
NPI/NPI-Qなどで標的症状を定量化(家族・介護者評価を含む)。身体要因(疼痛、便秘、尿閉、睡眠障害、感染、脱水、薬剤性)を是正。
2.非薬物的介入の徹底
刺激過多/不足の調整、見当識サポート、日中活動、睡眠衛生、コミュニケーション介入を行う。
厚生労働省
3.レキサルティ導入(やむを得ない場合)
0.5mg/日で開始、≥1週間観察し1mg/日へ。効果不十分で忍容性に問題がなければ2mg/日まで検討。増量後は副作用モニタリングを強化。
4.追跡評価
2〜6週ごとに症状・副作用・介護負担を再評価。効果が乏しければ見直し、効果があれば最小有効量で維持。
5.中止の検討
症状が安定し環境が整ったら、漸減中止を計画。長期連用でのベネフィット/リスクは常に再評価。
服薬指導・家族への説明のポイント(薬剤師向け)
・適応はADに限定、他の認知症では適応外であることを最初に説明する。
・非薬物的介入が基本であり、本剤はそれでも不十分な場合の補助であることを伝える。
・日中の眠気、ふらつき、筋固縮、落ち着きのなさ(アカシジア)などの早期発見を家族と共有。転倒・誤嚥の予防策を具体化する。
・他剤との相互作用(CYP2D6/3A)に注意。新規処方・OTC・サプリの追加時は必ず相談してもらう。
・急な増量・自己中止は避ける。効果・副作用は1〜2週間単位で見ていくことが多いと説明。
・介護者負担の軽減も評価指標。NPI-Qなど簡便な尺度の利用を勧める。
他剤との位置づけ:これまでと何が違う?
従来、日本のガイドラインはリスクと有効性のバランスから、抗精神病薬の使用を最小限・短期間に限定する姿勢でした。今回の承認はその原則を崩すものではなく、適応に沿った「選択肢の明確化」と捉えるのが妥当です。つまり、適応外依存からの脱却・薬物療法の透明性向上が主眼であり、「安易に使いやすくなった」という意味ではありません。
よくある疑問Q&A
Q1:アルツハイマー型以外の認知症にも使えますか?
A:適応外です。AD以外の認知症に伴う同様の症状に対する有効性・安全性は確立していません。
Q2:どれくらいで効きますか?
A:臨床試験の評価は数週間単位で行われています。開始・増量後に1〜2週で初期の変化を、4〜6週で再評価し、最小有効量を見極めるのが一般的です(個別差あり)。
Q3:長期に続けても大丈夫?
A:漫然投与は避け、定期的に中止可能性を検討します。高齢認知症患者では死亡リスク増加の海外報告があるため、必要最小限の用量・期間が原則です。
Q4:まず何から始めるべき?
A:非薬物的介入(環境調整、身体要因の是正、介護者教育)が基本。薬はそれでも危険や困難が残る場合の追加です。
まとめ:レキサルティは「BPSD薬」ではなく、ADの特定症状に対する“慎重な選択肢”
・2024年9月、レキサルティは日本で初めて、ADに伴う焦燥・易刺激性・興奮に起因する過活動/攻撃的言動への適応を取得。
・適応はADに限定、非薬物的介入が不十分な場合に限って使用する。開始0.5mg/日 → 1mg/日、必要に応じ最大2mg/日まで。
・死亡リスク増加報告を含む安全性上の注意は厳重。最小有効量・最短期間、定期的な再評価が不可欠。
・位置づけは「適応外依存からの一歩前進」。ただし、非薬物介入を土台とする原則は変わらない。




