記事
アトロピン点眼液0.25%ってあるの?
公開. 更新. 投稿者: 5,471 ビュー. カテゴリ:眼/目薬/メガネ.この記事は約4分48秒で読めます.
目次
アトロピン点眼液0.25%は必要なのか?添付文書記載と現場運用のギャップ
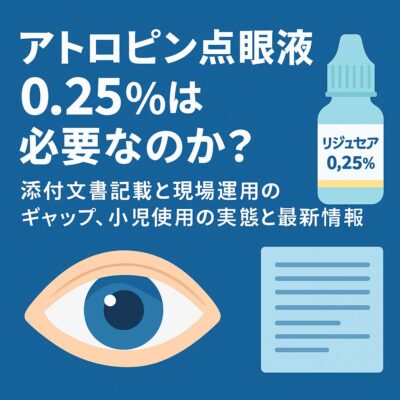
眼科で子どもの屈折検査や弱視・斜視の治療をする際、アトロピン点眼液は不可欠な薬剤です。しかし、その添付文書には、思わず戸惑う記載が目を引きます。
「小児には0.25%液を使用することが望ましい」
こうした一文を読むと、「0.25%の製剤が存在するのだろう」と考える人が多いでしょう。
ところが実際には、長らく国内で市販されているのは1%製剤だけで、調べても0.25%規格は見つかりません。この「推奨と現実の乖離」は現場でしばしば混乱を招いてきました。
さらに2025年には、低濃度アトロピン製剤リジュセアミニ点眼液が発売され、状況は一層複雑化しています。
アトロピン点眼液とは?
アトロピンは、ベラドンナアルカロイド系の抗コリン薬(副交感神経遮断薬)です。点眼により次の作用を示します。
●散瞳
・瞳孔を拡げる
●調節麻痺
・水晶体のピント合わせを止める
このため、以下の目的で使用されます。
・正確な屈折検査(調節麻痺検査)
・弱視・斜視の治療(調節緊張の緩和)
・近視進行抑制(低濃度長期投与)
添付文書の「0.25%液を使うことが望ましい」という表現の意味
日本の「日点アトロピン点眼液1%」添付文書には以下の記載があります。
「全身の副作用が起こりやすいので、幼児・小児には0.25%液を使用することが望ましい。」
一見すると、0.25%製剤が存在するかのように読めます。しかし実際は市販製剤としては1%のみ。
この記載が何を意図しているのか、筆者自身もメーカーに確認を行いました。その回答は次のようなものでした。
・副作用軽減の目的で記載している
・濃度設定に強い根拠はない
・運用は医療機関で判断する
つまり、「0.25%液を使うことが望ましい」とはあくまで一つの目安に過ぎず、どの濃度を使うかは施設や医師の裁量に任されているのが実態です。
そのため「0.25%が強く推奨される根拠はない」と判断し、必ず希釈するわけではなく、そのまま1%を使う例も少なくないのが現状です。
小児アトロピン使用に関する研究報告
添付文書記載の背景にあると思われる調査も紹介します。
2008年から2011年に行われた報告(387例)によると、
使用濃度と副作用発現率
0.5%:212例 5.7%
1%:114例 5.3%
注目すべきは、
・0.5%と1%で副作用発現率に有意差なし
・副作用は開始4日以内に集中
・夏に発熱・顔面紅潮の頻度が増加
という結果です。
つまり、濃度を半分に下げても副作用頻度が大幅に減るわけではないことが示唆されています。
では、なぜ「0.25%」という記載が残るのか?
この点についてメーカー担当者からは、
「歴史的に海外で低濃度使用の報告があったことと、副作用リスクを下げる可能性に配慮して記載しているが、実際の濃度設定は施設次第」
という回答を得ています。
さらに2025年にリジュセアミニ点眼液が発売され、「低濃度アトロピン」の選択肢は増えましたが、これは近視進行抑制目的の長期使用を想定した製剤です。
リジュセアミニ点眼液の特徴
リジュセアミニ点眼液の使用目的は「近視進行抑制」であり、この製剤は散瞳や調節麻痺作用はごく軽度で、屈折検査用には適しません。
現場の運用:どう判断する?
アトロピンを小児に使う場合、次の考え方が必要です。
●屈折検査用
→ 調節麻痺の強さを優先し、1%を慎重投与
(必要に応じて院内希釈で0.5%や0.25%にする場合も)
●近視進行抑制
→ リジュセアミニを長期投与
添付文書だけを見て「0.25%を作らなければならない」と思い込むのは誤解です。
医師の処方意図を確認し、目的と使用方法を整理することが大切です。
小児アトロピン点眼の安全管理ポイント
以下のような工夫で副作用リスクを減らせます。
・最少回数・最短期間で投与
・点眼後に涙嚢圧迫(目頭を押さえ鼻涙管吸収を減らす)
・夏期は特に注意(発熱が増える傾向)
・保護者への十分な説明
副作用が出やすいのは投与開始4日以内なので、保護者に観察を依頼します。
よくある質問
Q. 小児に1%は禁忌?
→ 禁忌ではなく、慎重投与が求められます。目的と副作用管理が大事です。
Q. 0.25%は必ず希釈するべき?
→ 必須ではありません。希釈は施設ごとの判断です。
Q. 低濃度アトロピン(リジュセアミニ)は屈折検査に使える?
→ 散瞳・調節麻痺は極めて軽度で、検査には不十分です。
まとめ
アトロピン点眼液1%は、小児眼科で長年使用されてきた重要な薬剤です。「0.25%液を使うことが望ましい」という添付文書の一文は、あくまで副作用軽減の参考にすぎず、必ずしも全ての現場で希釈を行う根拠にはなりません。
実際には、
・医療機関が院内希釈しているケース
・そのまま1%を使用しているケース
・リジュセアミニを近視抑制用に使うケース
など、運用は多様です。
医師の指示内容、目的、副作用リスクを把握し、必要なときは疑義照会や情報収集をためらわない姿勢が大切です。
参考文献
1)アトロピン点眼液 添付文書




