記事
ウェアリング・オフとオン・オフ現象の違いは?
公開. 更新. 投稿者: 14,818 ビュー. カテゴリ:パーキンソン病.この記事は約2分56秒で読めます.
ウェアリング・オフとオン・オフ現象の違いは?
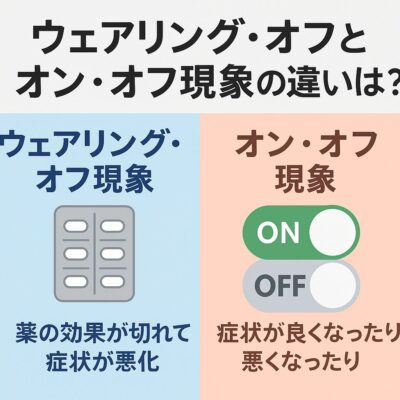
パーキンソン病の患者さんに使われるレボドパ(L-dopa)製剤。
長期的に服用していると、「効いている時間が短くなってきた」「突然、体が動かなくなる」などの症状が現れることがあります。
これらは「ウェアリング・オフ現象」と「オン・オフ現象」と呼ばれ、どちらも薬の効果時間や症状の安定性に関わる副作用です。
名前が似ていて混同されがちですが、意味合いは異なります。以下に詳しく解説します。
ウェアリング・オフ現象とは?
ウェアリング・オフ(wearing-off)現象は、薬を服用してから時間の経過とともに効果が切れていく現象です。
患者さんからは次のような訴えがあります:
「レボドパを飲んで3~4時間は動けるけど、その後はまた震えやこわばりが戻る」
「次の服薬までがつらい」
これは、薬の持続時間が短くなっているサインで、脳内ドパミンの貯蔵能力が低下していることが背景にあります。病気の進行とともに、この現象は出やすくなります。
オン・オフ現象とは?
オン・オフ(on-off)現象は、薬を飲んだ時間とは無関係に、突然症状が良くなったり悪くなったりする現象です。スイッチのように急に切り替わるため、患者の生活に大きな支障をきたします。
「さっきまで普通に歩けていたのに、急に動けなくなった」
「薬を飲んでも効果が出るときと出ないときがある」
これは薬の吸収や脳内での利用が不安定になっていることに加え、レボドパの効果に対する反応性のバラツキが影響しています。
違いをまとめると
| 比較項目 | ウェアリング・オフ現象 | オン・オフ現象 |
|---|---|---|
| 発生時期 | 服薬の数時間後(時間依存) | 服薬に関係なく突然(時間非依存) |
| 特徴 | 徐々に症状が戻る | 突然、症状が良くなったり悪くなったり |
| 原因 | 血中濃度の低下・持続性不足 | 中枢感受性・吸収ばらつき |
| 対応策 | 投与回数を増やす、徐放化 | 安定的な製剤、ドパミンアゴニスト併用 |
・安易な増量には注意
「効かない=もっとレボドパ」と考えがちですが、増量すれば副作用(ジスキネジアなど)も増えるリスクがあります。
・血中濃度を安定させる工夫
投与間隔を短くする(例:1日3回→4回など)
徐放性製剤に切り替える
貼付剤(例:ニュープロパッチ)やドパミンアゴニストの追加で安定性を確保
・食事の影響にも注意
レボドパはアミノ酸と競合して吸収が阻害されるため、高たんぱく食との同時摂取は避けるよう指導が必要です。
ウェアリング・オフは「効果が切れてくる」現象、オン・オフは「効いたり効かなかったりがバラバラ」な現象。
患者さんのQOLを大きく左右する問題であり、薬剤師としては症状のパターンを丁寧に聴き取り、服薬スケジュールや剤形の調整提案を行うことが重要です。
「この時間になると動けなくなる」「さっきまで大丈夫だったのに…」という患者の声を、ただの副作用と片付けず、病態進行と薬剤反応性の変化を見極める視点が求められます。




