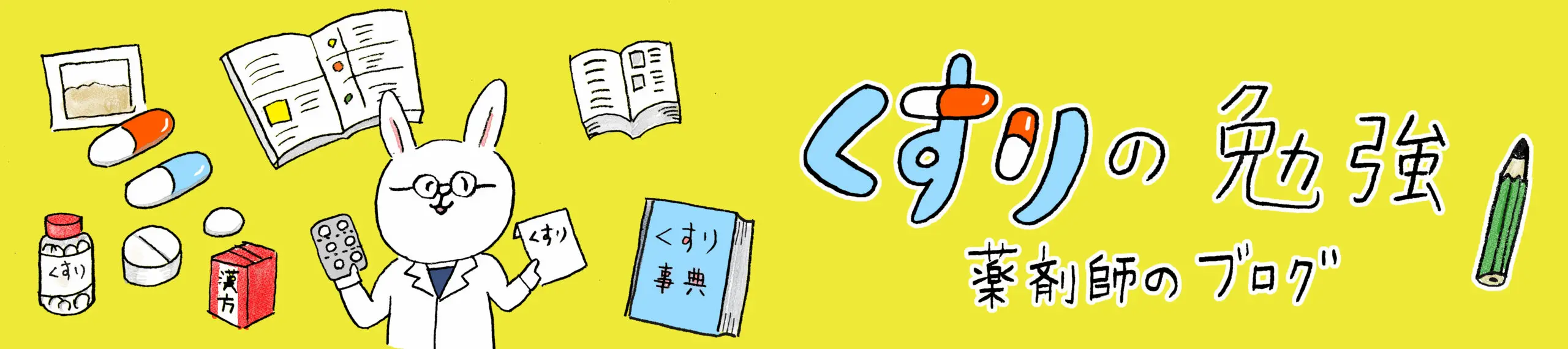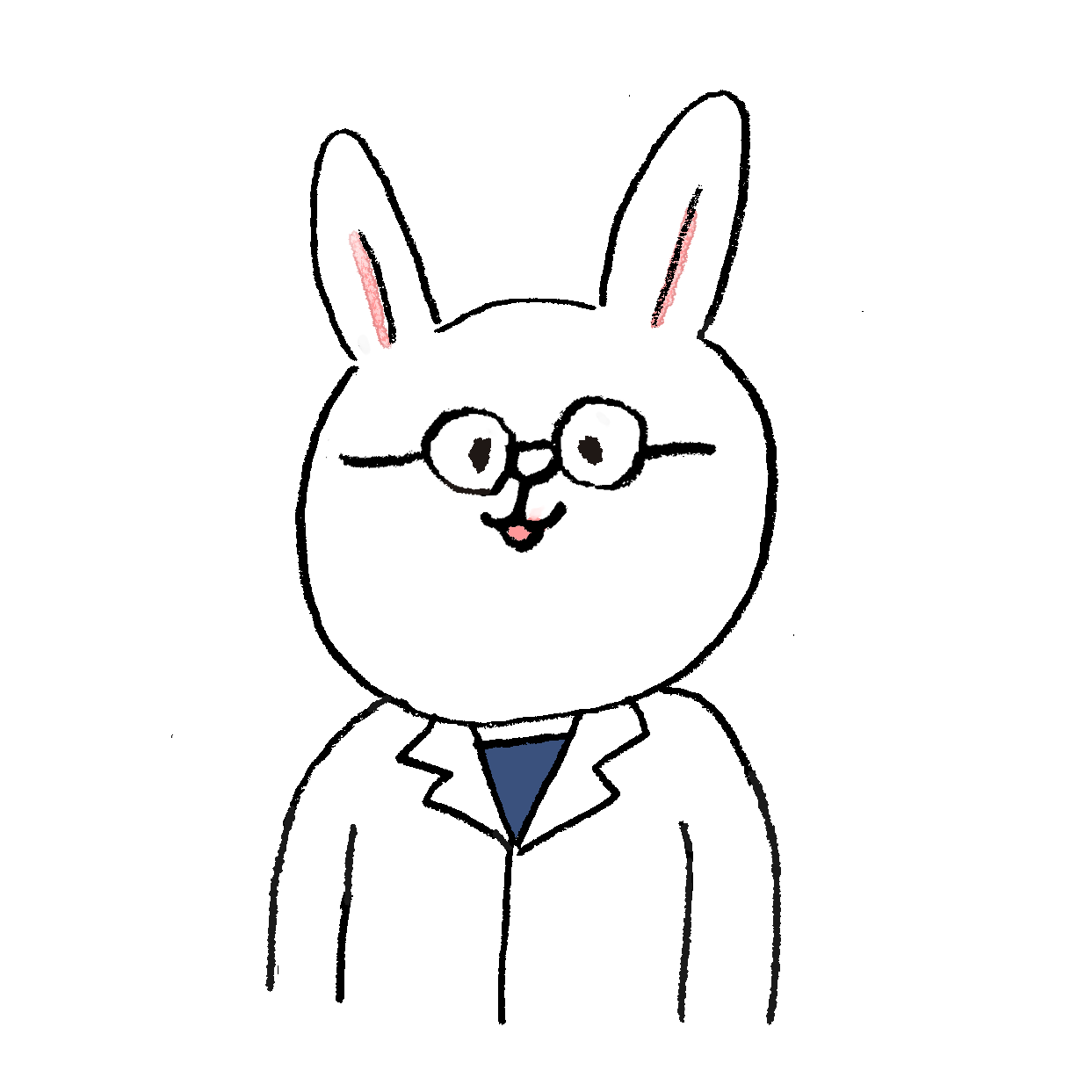記事
ステロイドの作用機序は?
公開. 更新. 投稿者: 22,529 ビュー. カテゴリ:免疫/リウマチ.この記事は約8分59秒で読めます.
ステロイドの働き
ステロイドっていろんな働きがあるよね。
いろんな副作用も。
ステロイドの効果としては、抗炎症作用と免疫抑制作用を期待して処方されることが多い。
近年、ステロイドの強力な抗炎症・免疫抑制作用の機序の1つとして、遺伝子の転写抑制による作用機序が注目されている。
けがや病気などにより細胞に炎症刺激が加わると、NF(nuclear factor)κBやAP(activation protein)-1などの炎症性転写因子が核内のゲノムDNAに作用し、炎症性サイトカインやケモカインなどの炎症・免疫関連蛋白の発現が増加する。
一方、この状態にステロイドを投与すると、ステロイドが細胞膜を通って、糖質コルチコイド受容体(GR)と結合し、ステロイドーGR複合体となって核内へ移行する。
この複合体が炎症性転写因子に直接結合して、遺伝子の転写調節を阻害し、その結果、炎症性サイトカイン産生などが抑制される、という機序が考えられている。
<抗炎症作用>
この作用を知るためにはアラキドン酸カスケードを知る必要があります。
炎症反応が起こると、細胞膜のリン脂質に結合しているアラキドン酸という物質から、酵素を介してロイコトリエン、プロスタグランジンという生理活性物質が作られ、それらの作用で痛みや炎症などの症状が起こります。
炎症を抑える成分のうち、非ステロイド性抗炎症成分はプロスタグランジンを作る過程を、ステロイドはその前のアラキドン酸の働きを抑えるので、ステロイドの方が非ステロイド性抗炎症成分よりも強力な抗炎症作用を発揮します。
ステロイド-ステロイド受容体複合体は、 リポコルチンの産生を促進することでホスホリパーゼA2(PLA2)を抑制し、アラキドン酸カスケードを抑制するという説から、 ホスホリパーゼA2を直接抑制しているという説に移行しつつあるが、PLA2抑制という本質は変わらない。
炎症部位で誘導されてくるCOX-2(シクロオキシゲナーゼ-2)の誘導を抑制することでPG類による血管拡張、血管透過性亢進から起こる白血球の遊走→炎症反応や ブラジキニン増強作用による痛みを抑制します。
<免疫抑制作用>
ステロイド-ステロイド受容体複合体は、CBP(cAMP responsive element binding protein[CREB] binding protein)と結合し、AP-1の結合を競合的に阻害、もしくはAP-1のロイシンジッパー部分に直接結合し 、サイトカインの合成を阻止する。
核内には、転写調節因子と相互作用して転写を促進的に調節するコアクチベーターと抑制的に調節するコリプレッサーが存在し、CBPはリン酸化されたCREBと相互作用して転写活性を上昇させるコアクチベーター である。
このCBPをコアクチベーターとして利用する転写調節因子はAP-1、NF-κB、GRなど多数あり、CBP量に制約があるため、ステロイドの存在はGR量が増してCBPの競合(奪い合い)が起こることになる。
また、NF-κBに直接結合して転写活性を失わせる、もしくはIκBを合成し、再びNF-κBと結合させることでNF-κBを不活性状態に戻す。
簡単に言えば、 マクロファージの活性を抑制しIL-1を抑制、さらに、IL-2産生を抑制することにより、Th1の細胞障害性T細胞(感作T細胞)への分化を抑制し、 マクロファージの貪食能、NK細胞活性に伴う遅延型アレルギーを抑制することで、それらが産生する炎症性サイトカイン(IL-1,6,8)が起こす炎症を止めます。
IL-2はB細胞が抗体産生細胞へ分化するのに必要なことから、抗体産生能(IgEなど)も抑制します。ただし、TNF、TGFは抑制されない。
ステロイドの副作用
ステロイドの副作用として、まず骨粗鬆症。
<骨に対する作用>
コルチゾールは骨芽細胞のアポトーシスを誘導するとともに、骨芽細胞の寿命の短縮、機能の抑制により骨代謝マーカーである オステオカルシン、アルカリホスファターゼ、Ⅰ型プロコラーゲンC末端ペプチドの低下が起こり骨形成能が低下します。
加えて、 腸管からのカルシウム吸収を抑制し体内のカルシウム量を減少させたり、尿中への排泄を促進する作用を持つ。
ムーンフェイス。
<脂質代謝に対する作用>
脂肪組織に作用して脂肪の分解を促進し、血中遊離脂肪酸とグリセロール濃度を上昇させます。
ただし、一部の組織では逆に脂肪合成が上昇します。
この結果、四肢では脂肪が減少し、背中、頸部、顔では脂肪が増加します。 これにより野牛肩や満月様顔(クッシング症候群)が生じます。
皮膚萎縮。
<タンパク代謝に対する作用>
タンパク質を分解・代謝することで、アミノ酸の血中濃度を上昇させ、アミノ酸の糖新生を促進します。
また、肝細胞以外の臓器でのアミノ酸取り込みを阻害し、血中アミノ酸濃度を上昇させます。
タンパク質の分解により皮膚が正常に再生されず皮膚の萎縮(薄くなる)という副作用が起こります。
糖尿病。
<糖代謝に対する作用>
コルチゾールは肝臓に働いてアミノ酸やグリセロールから糖新生(アミノ酸からブドウ糖を作る過程)を促進し、また、他の器官での糖利用を抑制することで血糖値を上昇させます。
この目的は主にストレス時の脳の機能低下を防ぐことにありますが、インスリンの作用と拮抗するということもあり、糖尿病の危険性が増します。
ステロイドの作用機序から、副作用を思い浮かべられるようになろう。
グルココルチコイド受容体
抗炎症の目的で使うステロイド薬は、副腎皮質ステロイドの一種で、糖質代謝に関与するグルココルチコイド(糖質コルチコイド)です。
血糖値のコントロールを行うだけでなく、炎症やアレルギーにも関与しており、これらの情報の入口はグルココルチコイド受容体というステロイド受容体に属するタンパク質です。
通常は細胞質に存在しますが、ステロイドホルモンと結合すると核内に移行して遺伝子発現を調節するようになります。
アレルギー反応が生じるメカニズムは、私たちの身体を守る免疫機構が関与しており、それが働きすぎた場合に現れるものです。
ステロイド薬は抗体産生を抑制することで、アレルギーが生じるメカニズムを根本から遮断する効果をもっています。
ステロイド薬の抗炎症作用は「リポコルチン」と呼ばれるタンパク質によって媒介されます。
これが細胞内のホスホリパーゼA2の活性化を阻害することにより、炎症反応が抑制されることになるのです。
ステロイドとNSAIDsの違い
ステロイド薬は、炎症反応のほぼ全過程を強力に抑制するので、アスピリンなどの非ステロイド系抗炎症薬(NSAIDs)とは異なった特徴をもつことになります。
たとえば、炎症の初期には血管透過性が冗進したり血管自体が拡張したりするのですが、ステロイド薬はこれを強く抑制します。
これは、カテコールアミンの感受性を増強させることで血管収縮作用が現れたものです。
また、細胞膜を安定化させる作用ももっているので、白血球の遊走能などの抑制も起こり、炎症反応を軽減させる作用ももっています。
さらに、線維芽細胞の増殖を抑制する作用もあることから、肉芽形成を阻害することも期待できるのです。
ステロイドの使い分け
通常は、まずプレドニゾロンやメチルプレドニゾロンの使用を考えます。
これらは、浮腫や高血圧、心不全を導くナトリウム貯蔵能が弱いため副作用が起こりにくいからです。
一方、抗炎症作用がもっとも強く速効性のあるものは、デキサメタゾンやベタメタゾンです。
これらは基準となるヒドロコルチゾンの力価の25倍の強さをもつのですが、副腎機能を低下させやすいので長期使用には適しません。
副作用には、食欲冗進や体重増加、満月顔(ムーンフェイス)、骨量減少などが起こりやすいことからも、急を要する場合の一時的な使用が望ましいものです。
副腎皮質ステロイドホルモン
ステロイド。副腎皮質ホルモン製剤。
副腎皮質ホルモン製剤は、炭素原子21個からなる合成ステロイド薬である。
副腎皮質ホルモンは、鉱質コルチコイドと、糖質コルチコイドとに大別されるが、合成ステロイド薬としては糖質コルチコイドが用いられる。
ステロイド薬の薬理作用は多彩であるが、とくに抗炎症、免疫抑制などの目的で使用されることが多い。
ステロイド薬はこの他、糖代謝、脂質代謝、電解質代謝などに影響を与え、また造血系、神経系、循環器系、消化器系、内分泌系、結合組織系などにも広く作用する。
ステロイド薬の主な副作用は、糖尿病、消化器潰瘍、骨粗鬆症、無菌性骨壊死、感染症の誘発、中枢神経障害、高血圧、白内障、緑内障などがある。
これらの副作用は、ステロイド薬投与継続により生命予後に影響をもたらすため、major side effectとも呼ばれる。
したがって、このような副作用が出現したときは、ステロイド薬は減量あるいは中止の適応となる。
これに対して、ステロイド薬投与によって起こる多毛、ざ瘡、満月様顔貌、皮下溢血、紫斑などの副作用は、minor side effectと呼ばれる。
これらの副作用が出現しても、必ずしも減量あるいは中止の適応とはならない。
ステロイド薬の効力を高め、かつその副作用を最小限にするために、薬剤の種類、投与法、用量などを十分に考慮することが大切である。
副腎皮質ステロイドホルモンは、左右の腎臓の上部にあるわずか5g程度の副腎から分泌される。
通常は、コルチゾールとして約10mg/日が体内で作られ、代謝や電解質の調節に関わる。
また、けがや病気などのストレス下では、ときに通常の10~20倍もの量が作られ、抗炎症作用、免疫抑制作用、中枢神経系の作用を示して環境の変化に体を適応させる役割を果たしている。
この作用を治療に応用するために人工的に合成されたのが、プレドニゾロンやメチルプレドニゾロン、デキサメタゾン、ベタメタゾンなど医薬品の経口ステロイドです。
これらは副腎皮質ホルモンのうち、電解質代謝に関わる鉱質コルチコイド作用を抑えて、糖質コルチコイド作用の力価を高めたものです。
抗炎症作用や免疫抑制作用といった糖質コルチコイドの生理作用を利用し、多様な疾患の治療に威力を発揮する。
経口ステロイドは、成分によって抗炎症作用(糖質コルチコイド作用)や鉱質コルチコイド作用、生物学的半減期などに応じた特徴がある。
中でも、生物学的半減期が12~36時間の中間作用型のステロイドであるプレドニゾロンは、作用時間が適度であり漸減や離脱なども行いやすい。
そのため、外来診療で最もよく処方されており、ステロイドの力価はプレドニゾロンを基準に計算される(プレドニゾロン換算)。
通常、成人では約10mg/日のコルチゾールが作られるが、これはプレドニゾロン2~2.5mg/日に当たる。
一方、デキサメタゾンやベタメタゾンは、生物学的半減期が36~72時間と長い。
鉱質コルチコイド作用が少ない為ステロイドを大量投与するパルス療法には適するものの、副腎機能抑制作用が強いなどの弱点がある。
臨床現場ではベタメタゾンと抗ヒスタミン薬のd-クロルフェニラミンマレイン酸塩との合剤であるセレスタミンがアレルギー疾患などに広く使われているが、安易な長期投与を懸念する声もある。