記事
入院中に投与開始すべき薬の一覧
公開. 更新. 投稿者: 2,510 ビュー. カテゴリ:服薬指導/薬歴/検査.この記事は約4分34秒で読めます.
目次
「入院下で投与を開始すること」と書かれた薬の意味
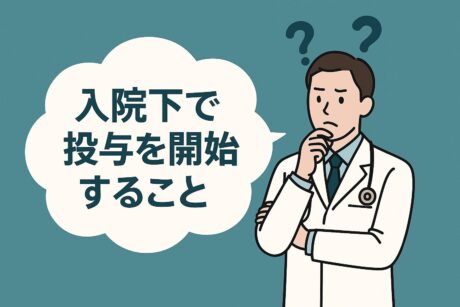
日々の調剤や疑義照会の中で、添付文書に書かれた「入院中に使用を開始すること」「入院下で投与を再開すること」という文言を目にすることがあります。薬剤師としてこの指示をどう解釈し、どう行動すべきなのか。そこには、単なる注意喚起ではない“重み”のある警告が込められています。
入院中に投与開始すべき薬一覧
| 医薬品名 | 添付文書の記載 |
|---|---|
| アムノレイク | 本剤による治療は危険性を伴うため、投与期間中は入院又はそれに準ずる管理のもとで適切な処置を行うこと。 |
| アルンブリグ | 治療初期は入院又はそれに準ずる管理の下で、間質性肺疾患等の重篤な副作用発現に関する観察を十分に行うこと。 |
| アレセンサ | 治療初期は入院又はそれに準ずる管理の下で、間質性肺疾患等の重篤な副作用発現に関する観察を十分に行うこと。 |
| アンカロン | 本剤の使用に当たっては、患者又はその家族に本剤の有効性及び危険性を十分説明し、可能な限り同意を得てから、入院中に投与を開始すること。 |
| イレッサ | 急性肺障害や間質性肺炎が本剤の投与初期に発生し、致死的な転帰をたどる例が多いため、少なくとも投与開始後4週間は入院またはそれに準ずる管理の下で、間質性肺炎等の重篤な副作用発現に関する観察を十分に行うこと。 |
| オータイロ | 治療初期は入院又はそれに準じる管理の下で、間質性肺疾患等の重大な副作用発現に関する観察を十分に行うこと。 |
| クロザリル | 無顆粒球症等の血液障害は投与初期に発現する例が多いので、原則として投与開始後18週間は入院管理下で投与を行い、無顆粒球症等の重篤な副作用発現に関する観察を十分に行うこと。 |
| ザーコリ | 間質性肺疾患が本剤の投与初期にあらわれ、死亡に至った国内症例があることから、治療初期は入院又はそれに準ずる管理の下で、間質性肺疾患等の重篤な副作用発現に関する観察を十分に行うこと。 |
| サムスカ | 本剤投与により、急激な水利尿から脱水症状や高ナトリウム血症を来し、意識障害に至った症例が報告されており、また、急激な血清ナトリウム濃度の上昇による浸透圧性脱髄症候群を来すおそれがあることから、入院下で投与を開始又は再開すること。 |
| サレド | 本剤の投与開始時及び増量後の一定期間は、重篤な不整脈等への適切な処置が行える入院管理下で投与すること。 |
| ジオトリフ | 治療初期は入院又はそれに準ずる管理の下で、間質性肺疾患等の重篤な副作用発現に関する観察を十分に行うこと。 |
| ジカディア | 治療初期は入院又はそれに準ずる管理の下で、間質性肺疾患等の重篤な副作用発現に関する観察を十分に行うこと。 |
| タグリッソ | 特に治療初期は入院又はそれに準ずる管理の下で、間質性肺疾患等の重篤な副作用発現に関する観察を十分に行うこと。 |
| タルセバ | 国内臨床試験において、間質性肺疾患により死亡に至った症例があることから、治療初期は入院又はそれに準ずる管理の下で、間質性肺疾患等の重篤な副作用発現に関する観察を十分に行うこと。 |
| ビジンプロ | 治療初期は入院又はそれに準ずる管理の下で、間質性肺疾患等の重篤な副作用発現に関する観察を十分に行うこと。 |
| ラズクルーズ | 特に治療初期は入院又はそれに準ずる管理の下で、間質性肺疾患等の重篤な副作用発現に関する観察を十分に行うこと。 |
「入院下で投与を開始」とはどういう意味か?
添付文書に「入院下で投与を開始」と明記されている場合、それは重篤な副作用が投与初期に集中して発現することを意味しています。投与を始めて数日〜数週間以内に、
・呼吸困難を伴う間質性肺疾患
・意識障害や中枢神経症状
・無顆粒球症や血球異常
・急激な電解質変動による神経障害
・不整脈やQT延長
といった、生命にかかわる重篤な副作用が起こり得る薬剤が該当します。
これらの副作用は、予測が難しく突然発現することが多く、迅速な医療対応を要するため、あらかじめ管理体制の整った入院環境で投与開始するよう指示されているのです。
添付文書の表現の違いと、その“重み”
添付文書上の文言には強弱があり、薬剤師としてはそのニュアンスの違いを読み取る必要があります。
◆強い指示
「入院下で投与を開始または再開すること」
「本剤の使用開始は入院管理下で行うこと」
→ 実質的に外来処方不可。違反すれば医療事故に直結。
◆中程度の指示
「入院またはそれに準ずる管理の下で観察を行うこと」
「治療初期は入院が望ましい」
→ モニタリング体制の整った外来・在宅医療でも可だが、リスク評価が必須。
◆比較的弱い指示
「治療初期には十分な観察が必要」
「初回投与時には慎重な投与が望ましい」
→ 入院までは求めないが、副作用が出やすい薬剤であり要注意。
つまり、「入院下」とは単なる場所指定ではなく、医療者の即時対応が可能な体制という意味でもあります。
なぜ“投与初期”なのか?:副作用が集中する理由
副作用の中でも、特に投与初期に集中して現れる傾向があるものには、以下のような特徴があります:
・免疫系を介したアレルギー・過敏反応(薬剤性肺炎など)
・血液系への障害(好中球減少、無顆粒球症)
・電解質や体液バランスの急変(ナトリウム濃度上昇など)
・中枢神経系への影響(意識障害、けいれん)
・致死的不整脈(QT延長、トルサード・ド・ポアン)
これらは一度発現すれば急速に進行し、外来レベルでは対処困難であることが多いため、予め入院中に投与を開始することが推奨されています。
「再開時も入院下」という文言に注意
一部の薬剤、特に電解質異常を引き起こす薬(例:トルバプタン)では、再開時にも入院下が必要という記載があります。
一度中止していた薬を再開した場合、体内環境や代謝が変化しており、副作用リスクが初回投与以上に高くなることがあるためです。
薬剤師としては、「この患者は再開かどうか?」を確認し、再投与が外来で行われている場合には、添付文書に従っているか疑義照会するのが望ましい対応です。
薬剤師としての実務対応:どのように関わるか?
◆処方時のチェックポイント
・初回投与か?再開か?
・投与開始の背景(緊急、慢性疾患、代替薬の不在など)
・患者の状態(高齢、併用薬、既往歴)
◆疑義照会すべきケース
・外来から初回処方されているのに、「入院管理下」が添付文書にある場合
・投与再開なのに入院せずに処方されている場合
・患者や家族が副作用のリスクを理解していない様子がある場合
◆薬歴・記録で残すべきこと
「初回投与のため、入院下での使用確認済」
「再開処方のため、入院管理必要性を確認」
「添付文書記載に基づき疑義照会を実施し、医師指示に従い処方継続」
よくある疑問とその対応
Q. 「入院下で使用」の薬を、施設や在宅で使ってはいけないの?
A. 一律にNGとは言えません。
「それに準ずる管理体制」が整っており、かつ観察・対応が迅速に行える体制であれば、実質的に添付文書の趣旨を満たしていると判断されることもあります。ただし、十分な体制整備と医師の判断が前提です。
Q. 添付文書に記載があっても、外来処方している医師を見たことがあるけど?
A. 現場での判断はさまざまですが、薬剤師としては添付文書の警告に従い疑義照会する責任があります。最終判断は医師であっても、薬剤師が黙認することは患者安全上のリスクになります。
結論:「入院下開始」はリスクを先取りして管理するための“盾”
添付文書の「入院下で使用開始」という記載は、単なる注意ではありません。
それは、副作用が出る可能性が“特に高い”と製造販売業者やPMDAが判断した薬剤であるという印です。
薬剤師としてこの文言を軽く受け止めてはいけません。
調剤、疑義照会、服薬指導の場でこの記載を正しく読み解き、患者の安全を守る最後の砦としての役割を果たすことが求められています。




