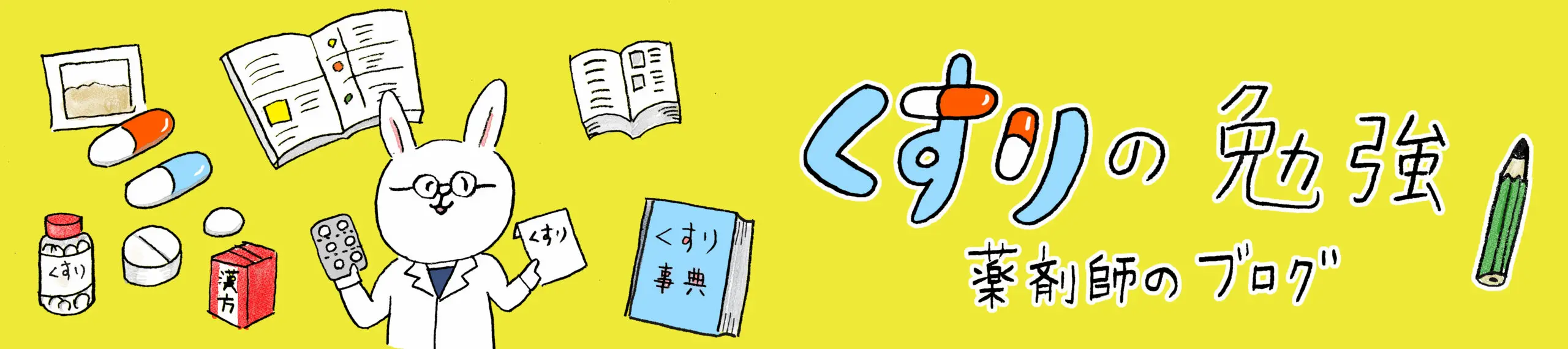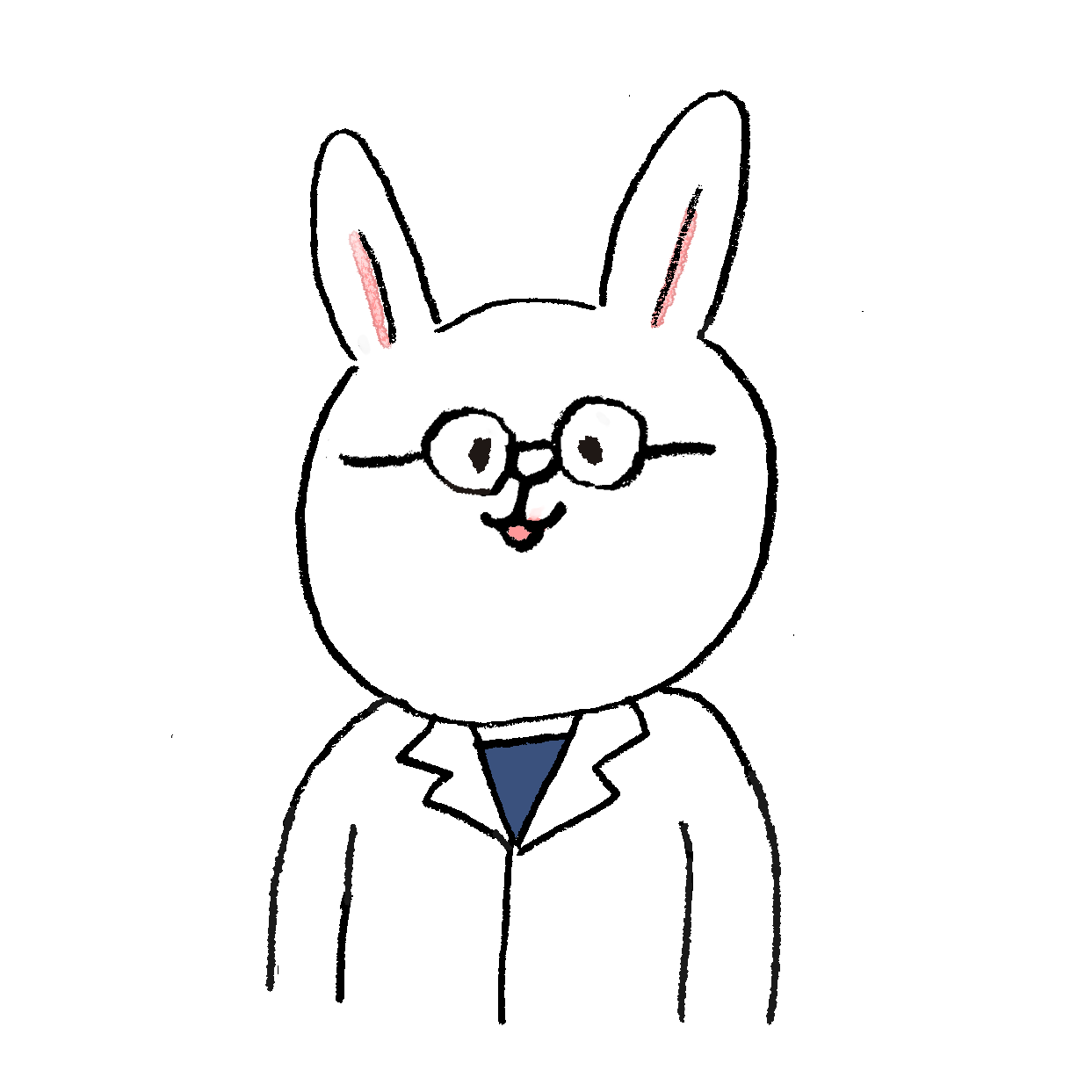記事
抗ヒスタミン薬は痙攣閾値を低下させる
公開. 更新. 投稿者: 10,553 ビュー. カテゴリ:てんかん.この記事は約3分14秒で読めます.
熱性痙攣とヒスタミン
熱性痙攣の誘因となる薬物として、テオフィリンや抗ヒスタミン剤が挙げられています。
ヒスタミンは痙攣を抑制する働きがあるらしく、そのヒスタミンの働きをブロックする抗ヒスタミン剤が熱性痙攣を誘発する。
抗ヒスタミン薬は、痙攣の閾値を下げる可能性があるため、熱性痙攣やてんかんの既往には注意が必要。
抗ヒスタミン作用がある抗アレルギー薬や古典的な抗ヒスタミン薬は、動物実験のみならず、疫学的にも、けいれんを起こしやすくしたり、けいれん重積を惹起する。
とくに、ウェスト症候群発症の報告がある抗ヒスタミン作用をもつ抗アレルギー薬は、乳児には、きわめて慎重に投与する。
熱性けいれん診療ガイドラインではえ、抗ヒスタミン薬服用中の症例では、発熱からけいれん発症までの時間が短縮されたり、発作持続時間が延長されたりすることが報告されています。
ただし、現時点では、抗ヒスタミン薬自体が熱性けいれんの発症率、再発率を上昇させたというデータはありません。
そのため、熱性けいれんの既往のある小児における抗ヒスタミン薬の使用に関して、ガイドラインでは「熱性けいれんの既往のある小児に対しては発熱性疾患罹患中における鎮静性抗ヒスタミン薬の使用は熱性けいれんの持続時間を長くする可能性があり推奨されない。抗ヒスタミン薬の投与量、投与期間、薬剤別の使用者数を明示したものはなく不十分な検討であるが、熱性けいれん自体がけいれん準備性の高さから発症するとすれば少しでもその特性に影響を与える可能性がある薬剤には、「Do no harm(害を及ぼさない)」の原則に従い注意すべきである」としています。
風邪のときの鼻水ならある程度はガマンさせたほうがいいと思います。
かゆみどめとして使う分には、発熱は無いと思うので問題ないでしょう。
熱性痙攣を誘発する薬剤
熱性痙攣を誘発し得る薬剤としてよく知られているのは気管支拡張薬のテオフイリンだが、抗ヒスタミン薬も原因薬剤となることは、1940年代から報告されていた。
機序は、ヒスタミンが中枢神経系で神経伝達物質として作用しており、ヒスタミンH1受容体を介して痙攣の抑制に関与しているといわれている。
また、抗ヒスタミン薬などヒスタミンH1受容体桔抗作用を持つ薬剤を服用すると、この抑制機構が阻害されて、痙攣発作を起こしやすくなることが分かってきた。
ザジテンと痙攣
ザジテンの禁忌に「てんかん又はその既往歴のある患者〔痙攣閾値を低下させることがある。〕」という記載がある。
抗ヒスタミン薬が脳内に入ると、眠くなる、痙攣閾値が低下する、つまり痙攣が起こりやすくなるという。
第二世代抗ヒスタミン薬であるザジテンは第一世代抗ヒスタミン薬よりも、眠気など中枢神経系の副作用は少ないので、安心して使えそうだが、てんかんに禁忌となっている抗ヒスタミン薬はザジテンだけである。
その代わり、第一世代の抗ヒスタミン薬は、「低出生体重児・新生児」に禁忌となっており、乳幼児には使いづらくなっている。
抗ヒスタミン薬と中枢神経系
第一世代抗ヒスタミン薬や鎮静性抗ヒスタミン薬など血液ー脳関門を通過しやすい薬剤は、中枢神経系への影響の懸念があります。
抗ヒスタミン薬には、抗コリン作用や鎮静作用が比較的強い第一世代と中枢神経系に対する作用が極めて小さく抗コリン作用のない第二世代抗ヒスタミン薬があり、市販された時期を目安として分類されています。
第一世代
第一世代の抗ヒスタミン薬は、脂溶性で血液ー脳関門を通過し中枢神経系に作用します。
通常値領域での中枢抑制作用と中毒息での中枢興奮作用がみられ、脳内ヒスタミン神経がH1受容体を介して痙攣の抑制系として作用するため、小児では成人に比べて鎮静作用などの中枢抑制作用よりも、痙攣や興奮などの中枢興奮作用に注意が必要です。
第二世代
第二世代は第一世代に比べ、血液ー脳関門を通過しにくいといわれています。
そのため眠りにくいなど、副作用が少ないといわれています。
中枢移行性による鎮静の程度による分類では、非鎮静性(脳内H1受容体占拠率20%以下)、軽度鎮静性(脳内H1受容体占拠率20~50%)、鎮静性(脳内H1受容体占拠率50%以上)の3つに分類されます。
第二世代抗ヒスタミン薬でもオキサトミド、ケトチフェンは鎮静性に分類されますが、小児でも使用可能なため注意が必要です。
特に、ケトチフェン(ザジテン)は、脳内のH1受容体占拠率を比較したなかで最も強力な鎮静作用をもつとされています。