記事
漢方薬に含まれる芒硝は塩類下剤?
公開. 更新. 投稿者: 1,692 ビュー. カテゴリ:漢方薬/生薬.この記事は約3分28秒で読めます.
芒硝は塩類下剤?
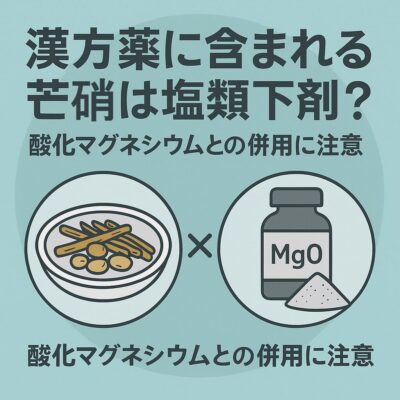
便秘治療の現場では、漢方薬と西洋薬の併用が行われることも多くなっています。
その中で、「芒硝(ぼうしょう)」という漢方生薬が含まれる処方と、「酸化マグネシウム」などの塩類下剤の併用について、薬剤師として押さえておきたい知識があります。
芒硝とは何か?
芒硝は「硫酸ナトリウム十水和物(Na₂SO₄・10H₂O)」を主成分とする鉱物性生薬です。
天然に存在する無機塩類で、古来より瀉下薬(しゃげやく)として利用されてきました。
現代薬理では以下のような特徴があります:
・主に硫酸イオン(SO₄²⁻)が吸収されにくいため、腸管内の浸透圧を高める
・腸内に水分を引き込むことで便を軟化させる
・塩類下剤として分類される
・大量経口投与(5〜15g)で明確な下剤効果を示す
しかし、漢方薬に含まれる芒硝の量は一般に1日1〜2g程度と少量であり、単独で下剤としての有効量に達するものではありません。
芒硝を含む代表的な漢方薬
芒硝は、大黄(だいおう)とセットで用いられることが多く、以下のような瀉下系漢方処方に含まれます:
| 漢方製剤名 | 配合の特徴 |
|---|---|
| 大承気湯 | 大黄+芒硝+枳実+厚朴 |
| 桃核承気湯 | 桃仁+桂皮+大黄+芒硝+甘草 |
| 通導散 | 多数生薬+大黄+芒硝 |
| 大黄牡丹皮湯 | 大黄+芒硝+牡丹皮など |
| 防風通聖散 | 芒硝+大黄+清熱利湿薬など |
| 調胃承気湯 | 大黄+芒硝+甘草 |
これらの処方では、
・芒硝が便を軟化
・大黄が大腸を刺激して排便を促進
という相乗効果が期待されています。
特に「大承気湯」や「桃核承気湯」は、「熱+便秘+腹部膨満感」のような病態に対して瀉下作用を強く求める処方設計になっています。
現代医療での芒硝(硫酸ナトリウム/硫酸マグネシウム)
現代西洋薬で「塩類下剤」といえば、真っ先に挙げられるのが酸化マグネシウム(MgO)ですが、
芒硝(硫酸ナトリウム)も薬理的には同様に「塩類下剤」としての性質を持ちます。
さらに、芒硝にはしばしば硫酸マグネシウムが混在しており、便通改善における作用に関しては、
・ナトリウムよりも硫酸イオンの浸透圧効果
・マグネシウムイオンによる腸運動促進効果
など、複数の側面があるとされています。
実際、硫酸マグネシウムは、
・産科領域では子宮収縮抑制薬として使用
・経口では1回5〜15gの高用量で下剤効果あり
という“両面性”を持つ薬剤です。
芒硝と酸化マグネシウムの併用
ここで問題となるのが、「芒硝を含む漢方薬と酸化マグネシウムの併用」です。
両者ともに塩類下剤であり、併用することで以下のようなリスクが考えられます:
腸管への過剰な浸透圧負荷:
・水分の引き込みが過剰になると、下痢や腹痛、脱水を引き起こす可能性
・特に高齢者や腎機能が低下している患者では要注意
マグネシウム過剰による副作用:
・酸化マグネシウムの服用量が多い場合、芒硝のマグネシウム分とあわせて高マグネシウム血症のリスク
・倦怠感、筋力低下、不整脈、徐脈、意識障害などを引き起こす可能性
作用の強さの見極めが難しくなる:
・「どちらが効いているか」がわからなくなり、薬効評価が困難に
・便通過多を「効いている」と誤認してしまうケースも
医療用漢方製剤の芒硝含有量は微量?
では、漢方薬に含まれる芒硝の量は具体的にどれくらいなのでしょうか。
例として、「ツムラ大承気湯エキス顆粒(医療用)」の成分をみると、
・芒硝:0.9g(1日量中)
同じく「防風通聖散」では、
・芒硝:0.3g前後
一方、塩類下剤として硫酸マグネシウムを使用する際の成人用量は5〜15gとされています。
このため、漢方薬に含まれる芒硝単体では明確な瀉下作用を狙えるほどの量ではないのが実情です。
しかし、「大黄との併用」「他の補助成分との相乗作用」「慢性投与」などによって、
結果として便通改善効果が強まる可能性があるため、臨床では注意が必要です。
併用されがちなケース
・「便秘が強くて酸化マグネシウムでは効果が弱い」と訴える患者に、医師が防風通聖散や桃核承気湯を追加
・「肥満+便秘+冷え」の症状に対し、西洋薬と漢方薬の併用で体質改善を狙う処方
チェックすべき観察ポイント
・排便回数や便の性状の変化
・下痢・腹痛などの過剰反応
・高齢者や腎機能が低い方への投与
・服薬指導での「併用薬の自覚の有無」
特に「市販のマグネシウム系整腸薬」と「漢方薬」の自己併用がある場合、
患者が「両方下剤とは気づいていない」こともあるため、丁寧なヒアリングが重要です。
・芒硝は塩類下剤として分類されるが、漢方製剤中では微量
・大黄との併用により相乗的な便通作用を示す
・酸化マグネシウムなどとの併用には注意が必要
・腸管負担・高マグネシウム血症・脱水などの副作用を予防するための配慮が大切
「漢方はやさしい薬」と思われがちですが、
適応や体質を見誤れば、西洋薬と同様に強い薬理作用を持ちうることを忘れてはなりません。
薬剤師としては、成分の重複と作用の加算に気づき、
処方提案や服薬指導を通じて安全な薬物治療を支えていく必要があります。




