記事
出席停止期間一覧
公開. 更新. 投稿者: 1,831 ビュー. カテゴリ:抗菌薬/感染症. タグ:薬剤一覧ポケットブック. この記事は約2分30秒で読めます.
学校において予防すべき伝染病
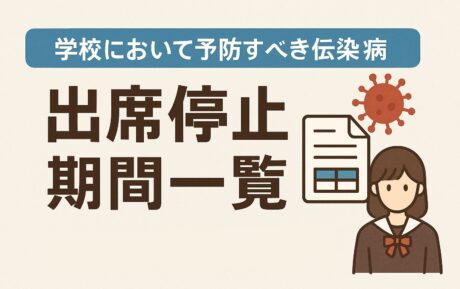
例えば、インフルエンザにかかった患者から、「何日間休めばいいですか?」といったことを聞かれることがある。学校の出席停止期間は、学校保健安全法施行規則第19条の「出席停止の期間の基準」に記されている。この学校保健安全法「学校において予防すべき感染症」の第1種、第2種、第3種を、感染症予防法の1類、2類、第3種と混同する人がいるが、異なるので注意する。
では、学校を休む期間ではなく、仕事を休む期間は何日間か?「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の第18条に「就業期間」について記されている。
「都道府県知事は、一類感染症の患者及び二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者に係る第十二条第一項の規定による届出を受けた場合において、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該者又はその保護者に対し、当該届出の内容その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知することができる。」
つまり、3類感染症までは就業制限があるが、4類や5類には就業制限はない。そのため、インフルエンザにかかった従業員を休ませる日数に明確な基準はない。とはいえ、企業には安全配慮義務があるので、社内で感染を広げないような対応が必要となる。そのため、多くの企業では、学校保健安全法の「出席停止の期間の基準」に準じた就業規則を定めている。
最近では、令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の法律上の位置づけが変わり、感染症法では「新型インフルエンザ等感染症(2類相当)」から「5類感染症」に変更となり、学校保健安全法では「第1種感染症」から「第2種感染症」に変更となった。それに伴い濃厚接触者に対する外出制限もなくなったが、感染不安を根強くもつ患者、従業員もいるので丁寧な説明が必要である。
▶出席停止期間一覧(学校保健安全法)
| 分類 | 考え方 | 病名 | 出席停止期間 |
|---|---|---|---|
| 第1種感染症 | 感染症予防法の一類感染症及び二類感染症(結核を除く) | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MARS)、特定鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア | 治癒するまで |
| 第2種感染症 | 空気感染または、飛沫感染する感染症で児童生徒の罹患が多く、学校に おいて流行を広げる可能性の高いもの | インフルエンザ | 発症後5日を経過し、解熱後2日(幼児は3日)を経過するまで |
| 百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または5日間の抗菌薬による治療が終了するまで | ||
| 麻疹 | 解熱後3日を経過するまで | ||
| 流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | ||
| 風疹 | 発疹が消失するまで | ||
| 水痘 | すべての発疹が痂皮化するまで | ||
| 咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | ||
| 新型コロナウイルス感染症 | 発症後5日を経過し、かつ症状軽快後1日を経過するまで | ||
| 結核 | 症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで | ||
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | |||
| 第3種感染症 | 学校において流行を広げる可能性があるもの | コレラ | 症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで |
| 細菌性赤痢 | |||
| 腸管出血性大腸菌感染症 | |||
| 腸チフス | |||
| パラチフス | |||
| 流行性角結膜炎(はやり目) | |||
| 急性出血性結膜炎(アポロ病) | |||
| 第3種感染症(その他の感染症) | 条件によっては出席停止の措置が考えられるもの | 溶連菌感染症 | 適正な抗菌剤治療開始後24時間を経て全身状態が良ければ登校可能 |
| ウイルス性肝炎 | A型・E型:肝機能正常化後登校可能 B型・C型:出席停止不要 |
||
| マイコプラズマ感染症 | 急性期は出席停止、全身状態が良ければ登校可能 | ||
| 感染性胃腸炎 (流行性嘔吐下痢症) | 下痢・嘔吐症状が軽快し、全身状態が改善されれば登校可能 | ||
| 手足口病 | 発熱や喉頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う急性期は出席停止、治癒期は全 身状態が改善すれば登校可 |
||
| ヘルパンギーナ | 発熱や喉頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う急性期は出席停止、治癒期は全 身状態が改善すれば登校可 |
||
| 伝染性膿痂疹(とびひ) | 出席可能(プール、入浴は避ける) | ||
| 伝染性軟属腫(水いぼ) | 出席可能(多発発疹者はプールでのビート板の共用は避ける) | ||
| アタマジラミ | 出席可能(タオル、櫛、ブラシの共用は避ける) | ||
| 伝染性紅斑 (りんご病) | 発疹(リンゴ病)のみで全身状態が良ければ登校可能 | ||
| その他 | 突発性発疹 | 解熱し、一般状態良好になるまで。 | |
▶感染症予防法による分類
| 分類 | 感染症名 |
|---|---|
| 1類感染症 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱 |
| 2類感染症 | 急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9) |
| 3類感染症 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス |
| 4類感染症 | E型肝炎、A型肝炎、黄熱、Q熱、狂犬病、炭疽、鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く)、ボツリヌス症、マラリア、野兎病 【政令】ウエストナイル熱、エキノコックス症、オウム病、オムスク出血熱、回帰熱、キャサヌル森林病、コクシジオイデス症、サル痘、ジカウイルス感染症、重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る)、腎症候性出血熱、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、チクングニア熱、つつが虫病、デング熱、東部ウマ脳炎、ニパウイルス感染症、日本紅斑熱、日本脳炎、ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、鼻疽、ブルセラ症、ベネズエラウマ脳炎、ヘンドラウイルス感染症、発しんチフス、ライム病、リッサウイルス感染症、リフトバレー熱、類鼻疽、レジオネラ症、レプトスピラ症、ロッキー山紅斑熱 |
| 5類感染症 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)、ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く)、クリプトスポリジウム症、後天性免疫不全症候群、性器クラミジア感染症、梅毒、麻しん、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 【省令】アメーバ赤痢、RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症、急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く)、感染性胃腸炎、急性出血性結膜炎、急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く)、クラミジア肺炎(オウム病を除く)、クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、細菌性髄膜炎(髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く)、ジアルジア症、侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症、水痘、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、先天性風しん症候群、手足口病、伝染性紅斑、突発性発しん、播種性クリプトコックス症、破傷風、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、百日咳、風しん、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ肺炎、無菌性髄膜炎、薬剤耐性アシネトバクター感染症、薬剤耐性緑膿菌感染症、流行性角結膜炎、流行性耳下腺炎、淋菌感染症 |




