記事
リボフラビンは着色料?
公開. 更新. 投稿者: 3,322 ビュー. カテゴリ:栄養/口腔ケア.この記事は約4分46秒で読めます.
目次
リボフラビンは着色料?医薬品・食品添加物としての役割
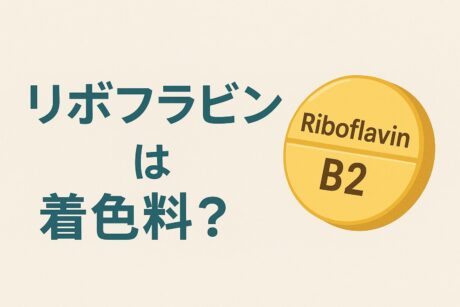
薬局で調剤をしていると、患者さんから「この薬、なんで黄色いんですか?」と聞かれることがあります。特にシナール配合錠のように明るい黄色をした薬を見ると、「ビタミンCだから黄色いの?」と思う方も少なくありません。ところが実際には、添加物としてリボフラビン(ビタミンB2)が入っているために黄色くなっているケースが多いのです。
リボフラビンといえば「皮膚や粘膜のビタミン」「口角炎や肌荒れの予防」といった効能が思い浮かぶでしょう。しかし医薬品の錠剤や食品に含まれている場合、それは必ずしも栄養素としての目的ではなく、着色料として使用されている場合も多いのです。
リボフラビン(ビタミンB2)とは?
基本情報
・水溶性ビタミンのひとつ(ビタミンB群)
・補酵素型(FAD, FMN)として細胞のエネルギー代謝に必須
・「発育のビタミン」「皮膚のビタミン」とも呼ばれる
生理作用
・糖質・脂質・タンパク質の代謝に関与
・皮膚・粘膜の健康維持
・抗酸化作用に間接的に寄与
欠乏症
・口角炎、口唇炎、舌炎、皮膚炎
・目の充血、羞明(まぶしさ)
・成長障害(小児)
過剰症
・通常の食事やサプリメントではほとんど起こらない
・尿が黄色くなるのは排泄によるもので無害
医薬品に含まれるリボフラビン
シナール配合錠の場合
シナールは「ビタミンC(アスコルビン酸)+パントテン酸カルシウム」が主成分ですが、添加物の欄にはリボフラビンが記載されています。
ここで重要なのは、有効成分として含まれているのではなく、添加物として配合されているという点です。つまり「薬効を狙った量」ではなく、「着色や識別のため」に加えられているに過ぎません。
実際、厚生労働省の「食品添加物リスト」や「医薬品添加物リスト」にもリボフラビンは着色料として収載されています。添加量の上限も特に定められていません。
他の黄色い薬にも使われる
シナール以外にも、黄色い錠剤の多くにリボフラビンが使われています。
・カルスロット錠(マニジピン)
・セルシン5mg(ジアゼパム)
・ミノマイシン錠(ミノサイクリン)
錠剤の色合いから「ビタミンが入っているのですか?」と尋ねられることもありますが、薬効とは無関係です。
リボフラビンは着色料?
結論からいえば、医薬品や食品で使用される場合、リボフラビンは「着色料」として分類されることが多いです。
●なぜリボフラビンが使われるのか?
・天然由来で安全性が高い
人工合成のタール系色素より安心感がある。
・鮮やかな黄色が得られる
医薬品を区別しやすくするために便利。
・安定性が比較的高い
光や熱で分解しやすい欠点はあるが、錠剤の識別には十分。
つまり、「薬効は期待せず、あくまで見た目のために入っている」というのが正しい理解です。
食品添加物としてのリボフラビン
使用例
・清涼飲料水(黄色系のジュース)
・即席めんのスープ粉末
・お菓子類(ビスケット、スナックなど)
法規制
食品添加物としてのリボフラビンは、使用基準(最大量規制)がありません。つまり必要に応じて着色目的で使うことができるという扱いです。
安全性
・動物実験や疫学調査で毒性は認められていない
・サプリメントとしても利用されている
「ビタミンが入っているから体に良い」と言っていいのか?
ここが薬剤師として悩ましいポイントです。
たしかにリボフラビンは体に必要な栄養素ですが、添加物として含まれる量はごくわずかで、薬効や栄養補助としての意味はほとんどありません。
したがって、患者さんに説明する際は次のように伝えるのが適切です。
「黄色いのはビタミンB2(リボフラビン)が着色料として入っているからです」
「栄養的な効果を期待できるほどの量ではありません」
「見た目の識別のためなので、薬効には関係ありません」
リボフラビンを含む健康食品やサプリメントとの違い
・サプリメントや栄養剤:有効成分として「リボフラビン〇mg」と明記。栄養補給目的。
・医薬品添加物:ごく微量。目的は着色。栄養効果はほぼゼロ。
この違いを理解していないと、「薬にビタミンが入っているから肌にいいはず」と誤解してしまう患者もいるので注意が必要です。
薬剤師視点でのまとめ
・リボフラビンは「皮膚や粘膜の健康維持に必須のビタミン」
・医薬品に含まれている場合、ほとんどは着色料としての添加
・栄養効果を期待できる量ではない
患者説明では「黄色=ビタミンB2由来だが、薬効には関係ない」と伝えるのが正しい
まとめ
リボフラビンは確かに体に大切なビタミンですが、医薬品や食品に添加されている場合は、多くの場合「着色料」としての利用です。薬効や栄養効果を期待してはいけません。
むしろ「天然由来の着色料で安全性が高い」という点に意義があります。薬局で「なぜ薬が黄色いのか?」と聞かれたときには、「識別のためにビタミンB2を少し入れているんですよ」と説明すれば、患者さんの安心感につながるでしょう。
薬の色や形は「服薬コンプライアンスを高めるための工夫」の一つでもあります。リボフラビンはその裏方として、医薬品の世界で活躍している存在なのです。




