記事
微量元素の必要量とその重要性
公開. 更新. 投稿者: 3,862 ビュー. カテゴリ:栄養/口腔ケア.この記事は約4分3秒で読めます.
目次
微量元素の必要量とその重要性〜見落とされがちな小さな栄養素たち〜
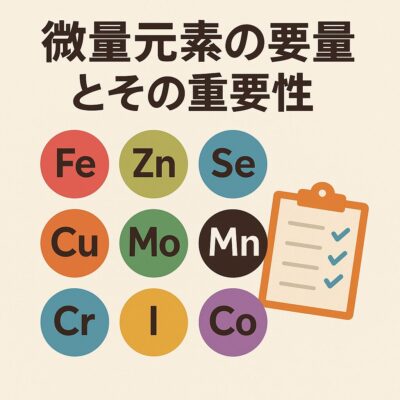
ナトリウムやカリウム、カルシウムといった電解質は、医療現場でも日常的に測定され、栄養管理に欠かせない存在です。しかし、人体の健康を維持するためには、それらの「主要ミネラル」だけでなく、「微量元素(トレースエレメント)」と呼ばれる栄養素の存在も非常に重要です
微量元素とは、体内にごく微量しか存在しないにもかかわらず、欠乏すると特定の症状や障害が現れる栄養素のことを指します。鉄や亜鉛、セレン、モリブデンなどが代表的ですが、その必要量の少なさと、症状の非特異性から一般にはあまり意識されていません。
微量元素の種類、必要量、欠乏による影響、栄養剤における配合の有無などを整理しながら、日常的な栄養管理の中での重要性を勉強します。
微量元素とは?——定義と分類
微量元素(trace elements)は、体内に存在するミネラルのうち、必要量が1日あたり100mg未満のものを指します。厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」でも、微量ミネラルは明確に分類されています。
主な微量元素の分類(ヒトに必須とされるもの)
・鉄(Fe):ヘモグロビン・ミオグロビンの構成要素
・亜鉛(Zn):酵素活性、免疫、創傷治癒
・銅(Cu):酸化還元酵素の補因子
・セレン(Se):抗酸化酵素(グルタチオンペルオキシダーゼ)に関与
・クロム(Cr):インスリン作用の補助
・モリブデン(Mo):酸化還元酵素の補酵素
・ヨウ素(I):甲状腺ホルモンの構成成分
・マンガン(Mn):酵素活性、骨代謝
このほかにも、コバルト(ビタミンB₁₂の構成要素)など、限られた量ながら生体機能に不可欠な元素も含まれます。
必要量と生理的役割
微量でも不可欠な理由
例えばモリブデンは、体内で硫黄を含むアミノ酸を代謝する際に必要な「キサンチンオキシダーゼ」「アルデヒドオキシダーゼ」などの酵素の補因子として機能します。必要量は1日あたり数μg程度と微々たるものですが、欠乏すると尿酸代謝異常や神経症状が出現する可能性があります。
食事摂取基準(例:成人男性)
元素名と推奨量または目安量(2020年版)
・鉄:7.5mg
・亜鉛:10mg
・銅:0.9mg
・セレン:30μg
・クロム:10μg(目安量)
・モリブデン:25μg
・ヨウ素:130μg
・マンガン:4.0mg(目安量)
これらはあくまでも「健康な個人」を対象としたものであり、疾患や経静脈栄養(TPN)を行う患者に対しては、異なる基準や慎重な管理が必要です。
欠乏によって生じる症状
微量元素の欠乏症は、多くが非特異的な症状を示します。そのため、診断が遅れたり見逃されたりすることも少なくありません。
例:微量元素の欠乏症とその症状
・鉄:鉄欠乏性貧血、倦怠感、集中力低下
・亜鉛:味覚障害、皮膚炎、創傷治癒遅延、免疫低下
・セレン:心筋症(Keshan病)、免疫低下、甲状腺機能低下
・銅:貧血、白血球減少、神経障害
・モリブデン:まれだが、硫黄アミノ酸代謝異常、神経症状など
・ヨウ素:甲状腺腫、クレチン症(小児)、低代謝性症状
・クロム:耐糖能異常、インスリン抵抗性
栄養剤に含まれる微量元素とその意図
経口栄養剤(ONS)や経管・静脈栄養剤には、製品ごとに微量元素の含有量が異なります。たとえば、医療用の経口栄養剤である「エンシュア・リキッド」や「ラコール」「メイバランス」なども製品ごとに含有微量元素は異なります。
エンシュア・リキッドの場合(1缶250ml中)
・鉄:2.5mg
・亜鉛:2.3mg
・銅:0.25mg
・セレン:含まれていない(要補足)
・モリブデン:含まれていない(要補足)
※エンシュアHやエンシュアリキッドは長期使用における微量元素欠乏の報告もあるため、必要に応じて微量元素製剤の併用が推奨されるケースもあります。
一方、静脈栄養(TPN)では、微量元素製剤(マルチトレースやテプレノン、ゾビニンなど)を別途追加する必要があり、各病院では欠乏症リスクを見越してルーチンで補充する体制がとられています。
微量元素は「摂取しなくてもすぐには死なない」が「不足すれば困る」
ビタミンや電解質と異なり、微量元素の欠乏症は進行が緩徐で、かつ非特異的な症状のため、長期間見逃される可能性があります。しかし、慢性的な欠乏は免疫力の低下、代謝異常、成長障害、創傷治癒遅延、さらには神経障害や心筋症といった重大な疾患を招くこともあります。
実際、TPN長期施行中にセレン欠乏による心筋症を発症した例や、亜鉛欠乏により難治性の褥瘡が治らなかった例など、医療現場で微量元素の重要性が再認識されつつあります。
日常生活における注意点
一般的なバランスの取れた食生活をしている限り、微量元素の欠乏は稀です。ただし、以下のような状況では注意が必要です。
・偏食や極端なダイエット
・消化管障害(吸収不全、短腸症候群など)
・高齢者や経口摂取量の少ない方
・長期の栄養療法(経管・静脈)
・特定の薬剤(キレート作用をもつ薬など)の長期服用
微量元素はサプリメントなどでも補えますが、過剰摂取は逆に有害となるため、医師や薬剤師の指導のもとで使用することが望まれます。
まとめ
微量元素は、文字どおり「微量」であるがゆえに見落とされがちですが、ヒトの生命活動において不可欠な存在です。必要量はきわめて少なく、日常的な食事で充分に摂取できることが多い一方で、長期の栄養療法や吸収障害など、特定の状況では欠乏症が深刻な問題となります。
医療者はもちろん、一般の方々にとっても「微量元素」の知識は、栄養管理の精度を高め、健康維持に貢献する基礎知識となるでしょう。




