記事
一包化の予製は違法か?
公開. 更新. 投稿者: 3,946 ビュー. カテゴリ:調剤/調剤過誤.この記事は約4分47秒で読めます.
目次
処方箋がまだ出ていないのに準備していいのか?
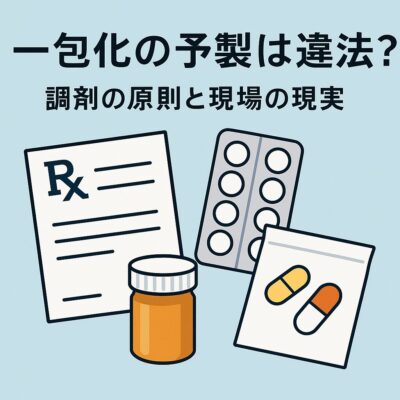
「また来月、あの患者さんが来るから、一包化を前もってしておこう。」
そんな判断をしたことがある薬剤師は、決して少なくないはずです。
しかし、それって法律的にOKなのでしょうか?
「調剤」とは、処方箋が交付された後に行うのが原則です。処方箋がない状態で薬を準備するのは、厳密には“調剤前行為”ではなく、違法な“未承認調剤”と解釈されるリスクもあるのです。
「調剤」とは何か?
まず原則を確認しましょう。
■ 薬剤師法第23条の規定
薬剤師は、処方箋により調剤を行わなければならない。
つまり、処方箋が無い状態で薬を調製・分包していると、そもそも調剤行為ではないということになります。
極端にいえば、それは無資格者でもできる作業と見なされる可能性があるということです。
「予製」とは何か? 一包化と予製剤の違い
■ 一包化の予製とは?
特定の患者が「同じ薬を毎回処方されている」ことを前提に、処方箋が出る前に一包化しておく行為
調剤の準備をしておくことで、来局時の待ち時間短縮を目的とする
これは法律的に極めてグレーな行為で、保健所の監査で指摘されるリスクがあります。
■ 一方で「予製剤」は?
不特定多数の患者に使用することを目的として、あらかじめ軟膏を混合したり、錠剤を半錠に割っておいたりする行為
これは調剤報酬上も「予製」として20%減点で算定可能なため、認められた行為といえます。
したがって、予製には明確な区別が必要です。
一包化予製(特定患者): 処方箋が出る前に一包化 原則NG(調剤前行為)
予製剤(不特定多数):軟膏混合、半錠割りなど 条件付きでOK
調剤現場の実情:理想と現実のジレンマ
実際の薬局現場では、「理想論だけでは回らない」という声が多数です。
たとえば――
・一包化対象の患者が1人30〜60分かかる
・毎月同じ処方内容が数年間変わらない患者も多い
・外来から複数名同時に来局したら、通常業務が止まる
・病院でも長時間待ったのに、薬局でも数時間待たされたら患者の不満爆発
こうした事情から、「予め準備しておかないと、現場が回らない」というのが本音ではないでしょうか。
保健所の監査ではどう見られるか?
保健所の立場としては、「処方箋なしの調剤=原則違反」として扱う可能性が高いです。
もし監査時に一包化済の薬が見つかった場合、
「これは調剤ミスした薬です」
「患者からキャンセルされた薬です」
といった説明をするケースもあるかもしれませんが、意図的な予製と認定されれば指導対象になる可能性もあります。
薬局によっては、「保健所の監査がある日は予製品をバックヤードに移す」などの対応をしているところもあるようですが、根本的な問題解決とは言えません。
厚生労働省の見解は?
厚労省からの明確な通知は多くありませんが、以下のような通達があります。
「調剤における安全確保の徹底について」(平成24年6月7日)
調剤は、処方箋内容を確認し、調剤設計を行ったうえで実施されるべきであり、漫然と行うべきでない。
ここからも、処方箋を確認せずに行う一包化は、調剤の原則から逸脱していると判断できます。
薬剤師ができる対処法
人員体制の見直し
重度の一包化患者が多数いる薬局では、人手不足が根本問題である場合が多いです。
管理薬剤師や経営者に「予製が違法とされるなら、それを防ぐための人員が必要」と正直に相談しましょう。
一部の作業を「調剤前業務」として仕分ける
「分包設計」や「薬歴確認」など、薬の袋詰め以外の業務は処方箋前に可能。
完全な一包化ではなく、「準備だけしておく」ことは違法ではありません。
医師と連携して事前処方を依頼する
慢性疾患の定期患者で毎回同じ内容の処方が想定される場合、事前に処方箋を交付してもらう工夫もできます(在宅などで実施例あり)。
医療機関や患者との信頼関係にも影響
違法ではなくとも、予製による調剤ミスや変更時の廃棄、誤交付は、信頼を損なう大きな原因となります。
一度でも「あの薬局は薬を先に作っていて間違えた」と噂が立てば、地域での信用失墜につながりかねません。
一包化予製は「必要悪」ではなく、体制で解決すべき課題
法的に予製は可能か?:原則NG(処方箋が出てから調剤)
保険請求できるか?:基本的にできない(処方箋なし)
予製剤との違いは?:不特定多数への準備ならOK(20%減算)
現場の声:患者満足や待ち時間短縮のため、黙認されがち
望まれる対策:人員体制強化・事前処方の相談・分包設計の分離
最後にひと言
一包化の予製は、薬局業務において「黙認されがちなグレーゾーン」です。
忙しい現場の中では、“必要悪”として実施してしまいたくなる場面も多いでしょう。
しかし、患者の安全や薬局の信頼性を守るためには、ルールと現実を両立させる工夫が求められます。
「予製は違法行為です」と現場を責めるのではなく、
「予製が不要な体制に変えるにはどうすればよいか?」という建設的な議論が必要です。
薬剤師の専門性と責任を守るためにも、今一度この問題に向き合ってみてはいかがでしょうか。




