記事
めまいに抗うつ薬?持続性知覚性姿勢誘発めまい
公開. 更新. 投稿者: 667 ビュー. カテゴリ:めまい/難聴/嘔吐.この記事は約5分41秒で読めます.
目次
PPPD(持続性知覚性姿勢誘発めまい)となぜ抗うつ薬が使われるのか
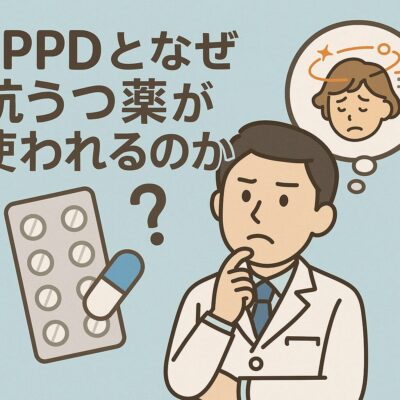
「めまい」と診断されている患者に抗うつ薬(SSRIやSNRIなど)が処方されていることがあります。
「抗うつ薬でめまいが副作用として出るのでは?」と感じ、思わず疑義照会を検討するようなケースもあるでしょう。
確かに、添付文書上でも抗うつ薬には「めまい」「ふらつき」「立ちくらみ」といった副作用が明記されています。
それなのになぜ、めまいに対して抗うつ薬が使われるのか――。
そこには、「PPPD(持続性知覚性姿勢誘発めまい)」という比較的新しい診断概念が関係しています。
PPPDとは何か
PPPD(Persistent Postural-Perceptual Dizziness:持続性知覚性姿勢誘発めまい)は、2017年に国際的診断基準がまとめられた新しい慢性めまい疾患です。
主な特徴
・めまいやふらつきが3か月以上持続
・明確な耳(内耳)や脳の異常は検出されない
・以下の状況で悪化しやすい
立っている・歩いているなどの姿勢保持
動くものを見たとき、あるいは自分が動いたとき(視覚刺激)
精神的ストレスや不安状況
・座って安静にしていると軽快する
つまり、身体的な平衡障害が治ったあとも、「脳がめまいを感じ続けてしまう」状態なのです。
発症の背景:最初の“きっかけ”は身体的
PPPDは、最初に何らかの“きっかけ”があることが多いとされています。
たとえば以下のようなものです。
・前庭神経炎や良性発作性頭位めまい症(BPPV)などの急性めまい疾患
・片頭痛関連めまい(vestibular migraine)
・強いストレスや不安障害
・通事故や外傷後の心理的ショック
この「きっかけ」によって平衡感覚が一時的に乱れると、脳はその情報を過敏に処理しようとするモードに切り替わります。
そして、急性期のめまいが治っても、その「過敏な状態」が解除されないまま残ってしまう。
その結果、刺激過敏・姿勢不安定・慢性的な違和感が持続するのです。
心因性めまいではない ―「脳の機能的変化」としての理解
PPPDはかつて「心因性めまい」と混同されることもありましたが、
現在では脳の感覚統合機能の異常として理解されています。
fMRI(機能的MRI)による研究では、
・前庭情報を処理する脳部位(島皮質や頭頂葉など)の活動異常
・視覚刺激に対する過敏な反応
・不安や警戒を司る扁桃体の活動亢進
などが報告されています。
つまり、PPPDは「気のせい」ではなく、脳が過剰にバランス情報を処理し続けている状態だと言えます。
抗うつ薬が効く理由:セロトニンと前庭機能の関係
ここで登場するのがSSRIやSNRIなどの抗うつ薬です。
なぜこれらがPPPDに有効とされるのでしょうか。
不安・恐怖の過敏反応を抑制
PPPDでは、「まためまいが起きるのでは」という予期不安が強く、
これが脳の過敏な感覚処理をさらに悪化させます。
SSRIは扁桃体などの情動回路の活動を安定化させ、不安の増幅ループを断つ効果があります。
前庭系への直接的な作用
セロトニンは、前庭神経核(内耳からの平衡情報を処理する部位)でも作用することが知られています。
SSRIやSNRIによってセロトニン系が調整されると、
前庭刺激への感受性を下げ、過剰なめまい反応を緩和すると考えられています。
痛み・自律神経の安定化
PPPDの患者では、自律神経の過緊張(動悸・吐き気など)を伴うことが多く、
SNRI(デュロキセチンなど)が持つ神経過敏抑制作用が有効とされる場合もあります。
抗うつ薬の副作用との関係 ―「めまいが出る薬なのに?」
ここが薬剤師として最も気になるポイントです。
確かに、SSRIやSNRIの添付文書には「めまい」「ふらつき」「起立性低血圧」などの副作用が記載されています。
しかし実際には、服用初期の一時的なものが多く、
体が慣れるにつれて消失するケースがほとんどです。
注意すべき点
・服用開始1〜2週目に一時的なふらつきが出ることがある
・高齢者や低血圧傾向の患者では起立性めまいに注意
・他の中枢性薬(抗不安薬、睡眠薬など)との併用で相加作用に注意
・減量・中止時に離脱性のめまいが出ることもある(SSRI特有)
したがって、服薬指導では
「初めのうちはふらつくこともあるが、しばらく続けることで体が慣れ、
むしろめまいが軽くなることもある」と説明しておくと安心です。
臨床でよく使われる薬剤例
PPPDに対して使われることのある抗うつ薬は以下の通りです。
・パロキセチン(パキシル):SSRI 不安抑制作用が強く、国内では比較的使用経験が多い
・セルトラリン(ジェイゾロフト):SSRI めまい・不安症に対するエビデンスあり、初期量少なめが推奨
・エスシタロプラム(レクサプロ):SSRI 副作用が少なく忍容性が高い
・デュロキセチン(サインバルタ):SNRI 自律神経症状や倦怠感が強い場合に有用
・ミルナシプラン(トレドミン):SNRI 日本での使用経験が長い
いずれも添付文書上「めまい」への適応はなく、いわゆるoff-label(適応外)使用です。
治療は「抗うつ薬だけではない」
PPPDは薬だけで完結する病気ではありません。
むしろ、薬物療法はあくまで“補助的”です。
前庭リハビリテーション
・バランス訓練や視覚刺激への慣れを促す運動療法
・「めまいを避ける」よりも「少しずつ慣れる」ことが目的
心理的サポート
・認知行動療法(CBT)によって「めまいへの恐怖」を軽減
・患者が「自分の体を信じる感覚」を取り戻す支援
生活指導
・長時間のスマホ・PC作業を避ける
・睡眠リズムを整える
・過度な安静は避け、できる範囲で活動を続ける
薬剤師としては、薬だけに頼らない総合的治療の一部として抗うつ薬が位置づけられていることを理解しておくことが大切です。
おわりに:薬剤師の“違和感”を臨床知識に変える
「めまいに抗うつ薬?」という違和感は、薬剤師として自然な反応です。
しかし、PPPDの理解を深めると、
それは心因性ではなく脳の感覚過敏状態を治すための合理的な治療であることが見えてきます。
抗うつ薬は“うつ病だけの薬”ではありません。
脳のバランスを整え、過剰な感覚処理を鎮めるという点で、
PPPD治療においては「神経のリセット薬」とも言える存在です。
薬剤師がこの背景を理解していれば、
患者の不安に寄り添いながら、
「この薬はあなたの“脳のめまい回路”を落ち着かせるためのものなんですよ」
と安心感を与える服薬指導ができるでしょう。




