記事
副作用で市場から消えた薬たち
公開. 更新. 投稿者: 825 ビュー. カテゴリ:副作用/薬害.この記事は約9分39秒で読めます.
目次
- 1 副作用で市場から消えた薬たち ― 販売中止薬の歴史から学ぶ安全性の教訓
- 2 アセナリン/リサモール(成分名:シサプリド)
- 3 ケテック(成分名:テリスロマイシン)
- 4 メレリル(成分名:チオリダジン)
- 5 バイコール/セルタ(成分名:セリバスタチン)
- 6 トリルダン(成分名:テルフェナジン)
- 7 アンダーム(成分名:ブフェキサマク)
- 8 ガチフロ(成分名:ガチフロキサシン)
- 9 スパラ(成分名:スパルフロキサシン)
- 10 ダンリッチ(成分名:塩酸フェニルプロパノールアミン, PPA)
- 11 ノスカール(一般名:トログリタゾン)
- 12 ロフェコキシブ(商品名:バイオックス)
- 13 まとめ ― 販売中止薬から学ぶこと
副作用で市場から消えた薬たち ― 販売中止薬の歴史から学ぶ安全性の教訓
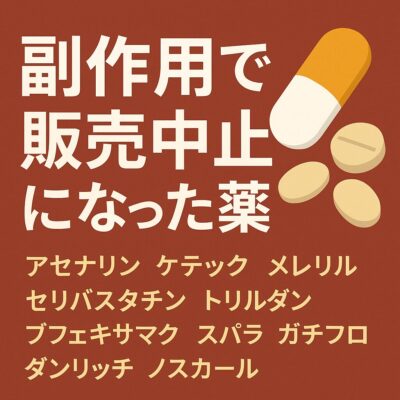
医薬品は、人々の健康を守るために日々開発され、臨床試験を経て承認されます。しかし承認時の臨床試験は対象患者数が数千例規模に限られるため、まれに重大な副作用が見逃されることがあります。市販後に数十万、数百万という患者が実際に使用して初めて、「予期しない重篤な副作用」が明らかになり、その結果として販売中止に追い込まれた薬が少なくありません。
日本で販売されたものを中心に、副作用を理由に市場から姿を消した代表的な薬を取り上げます。それぞれの薬がどのように登場し、どのような副作用によって消えていったのかを、勉強していきます。
アセナリン/リサモール(成分名:シサプリド)
胃腸運動改善薬の期待と挫折
アセナリン/リサモールは、消化管のセロトニン受容体(5-HT4受容体)を刺激し、アセチルコリンの遊離を促進することで腸管蠕動を改善する薬でした。1990年代、日本でも「食後の胃もたれ」「消化不良」「逆流性食道炎」などに広く用いられていました。
致死的不整脈の発覚
しかし、使用から数年後に問題が表面化します。シサプリドは心筋のKチャネルを阻害し、QT延長を引き起こすことが判明しました。結果、トルサード型心室頻拍と呼ばれる致死的不整脈を誘発するリスクがあると報告されたのです。特にマクロライド系抗菌薬やアゾール系抗真菌薬など、CYP3A4阻害薬との併用で血中濃度が上昇し、不整脈のリスクが高まることが問題となりました。
代替薬の登場
販売中止後は、ガナトン(イトプリド)やプリンペラン(メトクロプラミド)が代替薬として使われています。現在では薬剤師が処方監査の際に「QT延長リスク」「CYP3A4代謝阻害薬併用注意」を考慮する習慣が根付いていますが、その背景にはアセナリンの苦い経験があるのです。
ケテック(成分名:テリスロマイシン)
次世代マクロライドとして期待された薬
ケテックは2004年頃に登場した「ケトライド系」と呼ばれる抗菌薬です。従来のマクロライド耐性菌にも効果があると期待され、「呼吸器感染症の切り札」として注目されました。
予期せぬ重篤副作用
しかし発売後、米国を中心に重篤な肝障害や視覚障害の報告が相次ぎました。わずか数回の投与で急性肝不全を起こし、死亡例も確認されたのです。また、視覚異常や一過性の失明といった副作用も問題となりました。
市場からの撤退
日本でも臨床使用が始まりましたが、安全性上の懸念からわずか数年で販売中止に追い込まれました。現在、ケテックを知る若手薬剤師は少ないかもしれませんが、「新薬だからといって過信できない」ことを示す象徴的な事例です。
メレリル(成分名:チオリダジン)
古典的抗精神病薬の一角
メレリルはフェノチアジン系抗精神病薬のひとつで、統合失調症などに用いられていました。鎮静作用や抗幻覚作用を持ち、1960年代から長く使われてきた歴史ある薬です。
QT延長によるリスク
しかし、2000年代に入りQT延長から心室性不整脈を起こすリスクが大きく問題視されました。特に高用量使用や多剤併用でリスクが増加し、突然死の事例も報告されました。
市場からの姿消し
新しい非定型抗精神病薬の普及もあり、メレリルは安全性上の理由から販売中止となりました。「古くからある薬だから安全」とは限らないという事例であり、薬歴にメレリルの名前を見かけたときに不整脈との関連を思い出せるかどうかは、薬剤師にとって重要な知識です。
バイコール/セルタ(成分名:セリバスタチン)
「第3のスタチン」として登場
1990年代、セリバスタチンは脂質異常症治療薬として発売されました。当時、プラバスタチン、シンバスタチンに続く新しいスタチンとして注目を浴びました。
横紋筋融解症の多発
ところが、使用後に横紋筋融解症の多発が報告されます。他のスタチンでもまれに起こり得る副作用ですが、セリバスタチンでは発現頻度が高く、国内外で死亡例も確認されました。肝障害のリスクも高く、短期間で販売中止となりました。
代替薬と現在
現在ではリピトール(アトルバスタチン)、クレストール(ロスバスタチン)などのより安全性が高いスタチンが主流となり、セリバスタチンの記憶は薄れつつありますが、薬剤師国家試験や副作用の講義では必ず触れられる「教科書的な事例」です。
トリルダン(成分名:テルフェナジン)
抗ヒスタミン薬の新時代
トリルダンは第二世代抗ヒスタミン薬として1990年代に登場しました。眠気が少なく、花粉症患者にとって画期的な薬とされました。
不整脈による撤退
しかし、テルフェナジンもCYP3A4代謝を受ける薬であり、マクロライド系抗菌薬やアゾール系抗真菌薬との併用で血中濃度が上昇し、QT延長・心室性不整脈を引き起こすことが問題となりました。
フェキソフェナジンへの進化
この経験を踏まえ、テルフェナジンの代謝物であるフェキソフェナジン(アレグラ)が開発されました。フェキソフェナジンは心毒性がなく、安全性が飛躍的に向上しました。副作用をきっかけに、より良い薬へ進化した稀有な事例といえます。
アンダーム(成分名:ブフェキサマク)
外用抗炎症薬の期待
ブフェキサマクは、湿疹や皮膚炎の治療に用いられた外用消炎薬でした。ステロイド外用薬と異なり、長期使用でも副作用が少ないと期待されていました。
接触皮膚炎の多発
しかし実際には、ブフェキサマクそのものによる接触皮膚炎が高頻度で報告されました。特に、湿疹や皮膚炎という本来の適応症に対して塗布した患者で悪化を招く事例が目立ちました。
中止の経緯
「皮膚炎を治すはずの薬が皮膚炎を起こす」という逆説的な状況により、信頼を失い販売中止となりました。薬剤師として、患者に外用薬を勧める際のリスク説明の重要性を思い知らされる事例です。
ガチフロ(成分名:ガチフロキサシン)
次世代ニューキノロンとしての登場
ガチフロは1990年代後半に登場したニューキノロン系抗菌薬で、幅広い抗菌スペクトルと高い有効性が期待されました。
重大な血糖異常
しかし発売後、低血糖や高血糖といった重篤な血糖コントロール異常が報告されました。糖尿病患者での致死例もあり、国内では内服薬としての使用が中止されました。
点眼薬は存続
興味深いことに、点眼薬(ガチフロ点眼液)は局所使用のため全身副作用リスクが低く、現在も市販されています。「同じ成分でも剤形によってリスクが違う」ことを示す典型例です。
スパラ(成分名:スパルフロキサシン)
ニューキノロンの新星として登場
スパラは1990年代に登場したニューキノロン系抗菌薬で、肺炎や尿路感染症、耳鼻咽喉科領域の感染症など幅広く使用されました。特に半減期が長く、1日1回投与で効果が期待できる点は、当時としては画期的でした。
光線過敏症という大きな問題
しかし、発売後に深刻な副作用が明らかになります。スパラは光線過敏症(光毒性反応)を高頻度に引き起こすことが知られるようになったのです。紫外線を浴びた皮膚に激しい紅斑や水疱、色素沈着を残すような重篤な皮膚障害が多発しました。特に日本のように日照の強い環境では患者被害が大きく、社会問題化しました。
市場からの撤退
光線過敏症の予防には「服薬中および終了後数日間は直射日光を避ける」という指導が必須でしたが、現実的に守るのは困難で、重篤例も相次いだため、やがてスパラは市場から姿を消しました。
教訓とその後
その後のニューキノロン開発では、光毒性の少ない構造修飾が強く意識されるようになりました。現在使われているレボフロキサシンやガレノキサシンなどは、スパラの教訓を踏まえて設計されています。薬剤師にとって「スパラ=光線過敏症」という知識は、今も副作用学の定番トピックです。
ダンリッチ(成分名:塩酸フェニルプロパノールアミン, PPA)
鼻炎治療薬として広く使われた薬
ダンリッチは、かつて風邪薬や鼻炎用内服薬として広く使われていた塩酸フェニルプロパノールアミン(PPA)を含む製剤です。交感神経刺激作用を持ち、鼻粘膜の血管を収縮させることで鼻づまりを改善する効果が期待されていました。
脳出血リスクの報告
しかし2000年頃、米国でPPAを含む製剤を服用した若年女性において脳出血のリスクが有意に高まることが大規模研究で示されました。特にダイエット用薬や風邪薬に含まれていたケースで深刻な有害事象が相次ぎ、FDAはPPAの安全性に強い警告を発しました。
日本での販売中止
日本では2000年、米国での大規模研究を受けて厚生労働省がフェニルプロパノールアミン(PPA)の使用中止を指示しました。一般用医薬品に含まれる成分として広く流通していましたが、医療用で唯一PPAを配合していたのが「ダンリッチ」 です。耳鼻科領域で処方されることも多く、医療現場においてもその影響は小さくありませんでした。販売中止に伴い、代替薬への切り替えや処方見直しが必要となり、一部では混乱も生じました。
教訓
ダンリッチの販売中止は、「医療用として処方される薬であっても、長年使われてきた成分の安全性が再評価により覆ることがある」という事実を示しました。薬剤師としては、患者から「以前ダンリッチを飲んでいた」という話が出たときに、その薬がなぜ市場から姿を消したのかを正しく説明できることが求められます。
ノスカール(一般名:トログリタゾン)
チアゾリジン系の先駆けとして登場
ノスカールは、インスリン抵抗性を改善する初のチアゾリジン系糖尿病薬として1990年代後半に登場しました。脂肪組織や筋肉でインスリン感受性を高める作用は画期的で、「新時代の糖尿病治療薬」と大きな期待を集めました。
予測困難な肝障害
しかし使用後、重篤な肝障害が相次いで報告されます。AST・ALT上昇から急性肝不全に至り死亡する例もあり、発症のタイミングやリスク因子が一定せず、定期的な肝機能検査でも防ぎきれないことが問題でした。
短期間での販売中止
投与開始後のモニタリングを強化する対応が取られたものの、劇症肝炎の発生は止まらず、最終的に日本でも販売中止が決定されました。発売からわずか数年という短命な薬となったのです。
後継薬と教訓
後に登場したピオグリタゾン(アクトス)は肝障害リスクが低く、現在も使用されています。ノスカールは「有望な新薬でも、市販後の副作用で撤退し得る」ことを強く印象づけた事例であり、薬剤師にとって市販後の安全性監視の重要性を再確認させる薬となりました。
ロフェコキシブ(商品名:バイオックス)
日本未発売ながら世界的に有名
ロフェコキシブはCOX-2選択的阻害薬として米国で登場し、胃腸障害が少ないNSAIDsとして大ヒットしました。日本でも導入が検討されていました。
心血管イベントの増加
しかし臨床試験の追跡調査により、心筋梗塞や脳卒中のリスクが増加することが判明。2004年、製薬企業は自主回収を決断しました。世界的に大規模なリコールとなり、医薬品業界に衝撃を与えました。
その後の影響
日本では未承認のまま終わったため患者への影響は限定的でしたが、「COX-2阻害薬の安全性を厳しく見直す契機」となり、以降のNSAIDs開発に大きな影響を残しました。
まとめ ― 販売中止薬から学ぶこと
今回取り上げた薬には、
・QT延長 → アセナリン、メレリル、トリルダン(テルフェナジン)
・肝障害 → ケテック、ノスカール(トログリタゾン)、セリバスタチン
・横紋筋融解症 → セリバスタチン
・光線過敏症 → スパラ(スパルフロキサシン)
・血糖異常 → ガチフロ(ガチフロキサシン)
・脳出血 → ダンリッチ(PPA)
・心血管イベント → ロフェコキシブ
といった多彩な副作用が存在しました。
これらは「副作用そのものの予測困難性」や「市販後調査の重要性」を物語っています。薬剤師としては、過去に販売中止となった薬の歴史を知ることが、現在使われている薬の安全性評価や副作用監視に役立ちます。
医薬品は「効く」だけでは不十分で、「安全に効く」ことが必須です。販売中止薬の教訓を次世代の薬学にどう活かすかが、私たち薬剤師に課せられた使命といえるでしょう。




