記事
目薬を湿布と一緒に保管しちゃダメ?
公開. 更新. 投稿者: 824 ビュー. カテゴリ:眼/目薬/メガネ.この記事は約3分27秒で読めます.
目次
目薬と湿布を一緒に保管しちゃダメ?
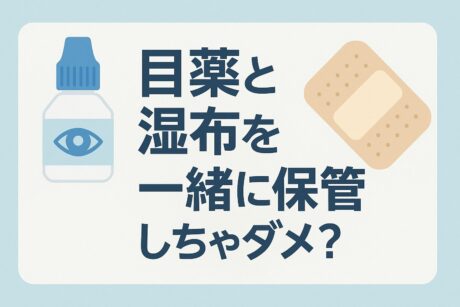
薬を自宅で保管する際、多くの方が「冷蔵庫に入れておけば安心」「まとめて薬箱に入れておけば大丈夫」と考えがちです。しかし、薬の中には一緒に保管することで品質に影響を与える可能性のあるものも存在します。その代表例のひとつが、目薬(点眼薬)と湿布薬です。
実際に薬局で「湿布と目薬は一緒に保管しないでください」と説明を受けた経験がある方もいるかもしれません。なぜそんな注意が必要なのでしょうか。
目薬(点眼薬)の特徴と保管条件
無菌性が最も重要
目薬は眼に直接使う薬であるため、無菌性が非常に重要です。細菌や真菌に汚染された薬を点眼すると、眼の感染症を引き起こし、最悪の場合は失明につながることもあります。そのため、点眼薬の製造過程は無菌的に行われており、保存料が含まれる製剤もあります。
湿布薬(貼付剤)の特徴と保管条件
成分の揮発と臭い
湿布薬には、サリチル酸メチルやメントール、カンフルなど揮発性の成分が含まれています。これらの成分は独特の臭気を持ち、密閉していないと周囲に移ることがあります。
湿布の保管上の注意
添付文書では、多くの湿布薬に以下のような記載があります:
・直射日光、高温、多湿を避けて保管
・小児の手の届かないところに保管
・開封後は袋をきちんと閉じる
湿布の有効成分は温度や湿度により分解・変質する場合があるため、冷暗所や常温での保存が基本です。
目薬と湿布を一緒に保管してはいけない理由
では、なぜ目薬と湿布を一緒に保管してはいけないのでしょうか。大きく分けて以下の2点が挙げられます。
揮発成分による汚染のリスク
湿布に含まれる揮発性成分(サリチル酸メチル、カンフル、メントールなど)は、密閉容器から微量に漏れ出ることがあります。この成分が目薬の容器や薬液に移ることで、点眼時に刺激や違和感を引き起こす可能性があります。
特にサリチル酸メチルなどは粘膜刺激性が強いため、微量でも目に入るとしみたり赤くなったりすることがあります。製薬メーカーや医薬品情報でも「点眼薬は揮発性成分を含む薬と一緒に保管しないこと」と注意書きされている場合があります。
臭気移行による品質低下
目薬は通常、無臭またはごくわずかな薬品臭しかしません。しかし湿布と一緒に保管することで臭気成分が容器に移り、患者さんが使用時に不快感を覚えることがあります。実際、薬局には「目薬が湿布臭い」と訴える患者が稀にいます。
さらに揮発成分が薬液中に溶け込むと、安定性に影響を与え、薬効が落ちるリスクも否定できません。
実際に起こりうるトラブル事例
ケース1:高齢者の薬箱
湿布と点眼薬を同じ引き出しに保管していた患者さんから「目薬がスースーする」との訴え。湿布臭が強く、点眼液に揮発成分が移行した可能性あり。
ケース2:冷蔵庫保管の誤解
「薬は冷蔵庫に入れた方が安心」と考え、湿布と目薬を一緒に冷蔵庫で保存。低温環境下で湿布成分が揮発しにくい一方、庫内で臭気が充満し目薬に移行した。
ケース3:旅行時の簡易保管
旅行にまとめて薬を持っていく際、ジッパー袋に湿布と点眼薬を一緒に入れてスーツケースに収納。到着後に目薬を使用すると強い臭気があり、使用を中止。
正しい保管方法のポイント
目薬の場合
・冷所保存指定があれば必ず冷蔵庫へ(ただし冷凍はNG)
・室温保存指定のものは直射日光を避けた涼しい場所に
・開封後は1か月以内に使用するのが基本
湿布の場合
・室温保存が基本。冷蔵庫保管は不要
・開封後は袋をしっかり閉じる
・強い臭気があるため、他の薬と分けて保管
併せて守るべきこと
・目薬と湿布は別々に保管する(薬箱を分ける)
・旅行時は袋を分ける(ジッパー袋やタッパーで遮断)
・子どもや高齢者には分かりやすい収納方法を工夫
患者指導に活かす視点
薬剤師や医療従事者が患者に説明するときには、「なぜ一緒に保管してはいけないのか」を具体的に伝えることが重要です。
「湿布のニオイや成分が目薬に移って、目にしみる可能性があります」
「保管場所を分けることで薬の品質を守れます」
「特に冷蔵庫で一緒に保管するのは避けましょう」
こうした説明を添えると、患者の納得度が高まり、実際の行動につながります。
まとめ
・目薬と湿布を一緒に保管するのは避けるべき
・理由は「揮発成分による汚染」と「臭気移行による品質低下」
・目薬は無菌性と安定性が命。湿布の臭いが移るだけでも使用感に影響する
・保管は必ず分けて行うのが基本
薬の効果を最大限に発揮させるためには、正しい保管方法を守ることが欠かせません。特に目薬は眼というデリケートな臓器に使う薬であるため、少しの不注意が大きなトラブルにつながる可能性があります。湿布と一緒に保管しない、このシンプルなルールを守ることが安全につながります。




