記事
ウイルスが引き起こすがん
公開. 更新. 投稿者: 1,668 ビュー. カテゴリ:癌/抗癌剤.この記事は約4分52秒で読めます.
目次
がんを引き起こすウイルス
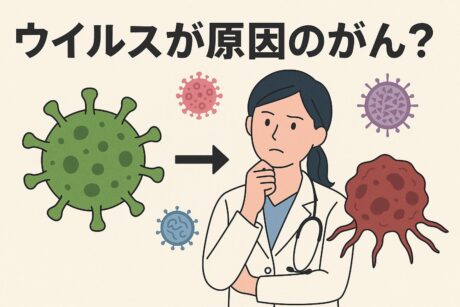
がんは、遺伝子の異常によって細胞が無制限に増殖することで起こる病気ですが、その「遺伝子の異常」を引き起こす原因は、生活習慣や加齢、放射線や化学物質だけではありません。実は、ウイルスの感染もがんの大きな原因の一つとされており、世界で発生するがんの約15〜20%はウイルスが関連していると推定されています。
なぜウイルスでがんになるのか?
ウイルスは、ヒトの細胞に侵入して自己複製することで増殖します。その過程で、細胞のDNAに異常を起こしたり、細胞の分裂を促進したり、免疫からの回避機構を作ったりと、がん化の原因となるさまざまな影響を与えることがあります。
がん化のメカニズムには主に以下のようなものがあります:
・ウイルス遺伝子の宿主DNAへの組み込み
・がん抑制遺伝子の不活化
・細胞増殖を促進するタンパクの産生
・慢性炎症による細胞障害と再生の繰り返し
これらの影響が時間をかけて蓄積されることで、最終的に“がん”へと進展していくのです。
主な「発がん性ウイルス」一覧
以下は、ヒトにおいて発がん性があるとされる代表的なウイルスです。
| ウイルス名 | 関連するがん | 感染経路 |
|---|---|---|
| ヒトパピローマウイルス(HPV) | 子宮頸がん、肛門がん、中咽頭がんなど | 性交渉などの粘膜接触 |
| B型肝炎ウイルス(HBV) | 肝細胞がん | 血液・体液 |
| C型肝炎ウイルス(HCV) | 肝細胞がん | 血液 |
| EBウイルス(EBV) | バーキットリンパ腫、鼻咽頭がん、胃がんなど | 唾液・密接接触 |
| 成人T細胞白血病ウイルス(HTLV-1) | 成人T細胞白血病 | 母乳・性交渉・輸血 |
| ヒトヘルペスウイルス8型(HHV-8) | カポジ肉腫 | 性的接触、輸血 |
| メルケル細胞ポリオーマウイルス(MCPyV) | メルケル細胞がん | 不明(皮膚経由?) |
HPV(ヒトパピローマウイルス)と子宮頸がん
HPVは100種類以上の型が知られていますが、発がん性が高いのは主に16型・18型などで、子宮頸がんの約70%がこれらの型に関連しています。
感染そのものは自然免疫で排除されることもありますが、一部の感染が持続化すると、子宮頸部の細胞に異形成を起こし、数年〜十数年を経てがんに進展することがあります。
予防にはHPVワクチン(シルガード9など)が非常に有効で、世界的にも子宮頸がんの予防に寄与しているワクチン接種が推奨されています。
B型・C型肝炎ウイルスと肝がん
B型肝炎(HBV)、C型肝炎(HCV)ウイルスは、慢性的に感染すると肝臓に炎症を起こし、肝硬変→肝がんへと進行するリスクが高まります。
特徴の違い:
・HBVはウイルスDNAを宿主DNAに組み込み、直接的ながん化のリスクがある
・HCVはRNAウイルスで、直接的な遺伝子変化よりも慢性炎症の繰り返しによりがん化
現在、B型肝炎にはワクチンがあり、出生直後の接種が義務化されています。一方、C型肝炎には直接的なワクチンはないものの、DAA(直接作用型抗ウイルス薬)による高い治癒率が得られるようになっています。
EBウイルス(Epstein-Barr Virus)とがん
EBウイルスはヘルペスウイルス科の一種で、90%以上の成人が感染しているといわれています。通常は無症状ですが、特定の条件下で以下のようながんに関連するとされています。
・バーキットリンパ腫(特にアフリカ系)
・鼻咽頭がん(中国南部・東南アジアに多い)
・胃がん(一部)
がん細胞の中にEBウイルスが高率に検出されることがあり、診断や分子標的治療のターゲットとして注目されつつあります。
成人T細胞白血病ウイルス(HTLV-1)
HTLV-1は、主に母乳感染によって小児期に感染し、長い潜伏期間(数十年)を経て成人T細胞白血病(ATL)を引き起こすことがあります。
日本では特に九州・沖縄地方に多く、厚労省は妊婦のスクリーニング検査を通じて母乳感染の予防(人工乳育児の推奨)を行っています。
ATLは非常に進行が速く、予後が悪いため、感染そのものを抑えることが重要です。
HHV-8(ヒトヘルペスウイルス8型)とカポジ肉腫
HHV-8は、カポジ肉腫というがんの原因ウイルスです。これはAIDS(HIV感染)患者に多くみられる皮膚や粘膜の悪性腫瘍で、免疫力の低下によって発症しやすくなります。
免疫機能が正常な人にとっては発症頻度はきわめて低いものの、免疫抑制下では日和見的にがん化することがあるため、免疫管理の重要性が問われます。
MCPyVとメルケル細胞がん
近年発見された新しいウイルスに、メルケル細胞ポリオーマウイルス(MCPyV)があります。これは皮膚がんの一種であるメルケル細胞がんとの関連が指摘されています。
皮膚がんの中でも非常に悪性度が高く、転移しやすいタイプのがんです。感染経路や発症メカニズムは未解明な部分も多いですが、高齢者や免疫抑制患者に発症が集中しています。
がんウイルスは“防げる”感染症
ウイルス感染が原因となるがんは、予防可能ながんとも言えます。以下のような対策によって、その多くを防ぐことができます。
・HPVワクチン・B型肝炎ワクチンの接種
・母乳感染の予防(HTLV-1)
・感染源の遮断(輸血・注射器・性交渉など)
・免疫機能の維持(HIV感染の管理)
また、C型肝炎のように治療で根治できる時代に入ってきたこともあり、「ウイルス感染=一生もののリスク」とは限らなくなっています。
まとめ:ウイルスとがん─感染症としての顔を忘れずに
がんは一見、個人の体質や生活習慣の結果に思える病気ですが、実は感染症が原因となる場合も多くあります。ウイルスによるがんは、ワクチンや予防によって抑えることができる可能性のある“社会で防げるがん”でもあります。
医療の進歩により、感染予防・早期診断・新たな治療法が開発されている今、がんとウイルスの関係に対する理解を深めることが、未来のがん医療において重要な鍵となるでしょう。




