記事
菌がいない膀胱炎?無菌性膀胱炎と間質性膀胱炎
公開. 更新. 投稿者: 5,737 ビュー. カテゴリ:抗菌薬/感染症.この記事は約5分7秒で読めます.
目次
無菌性膀胱炎
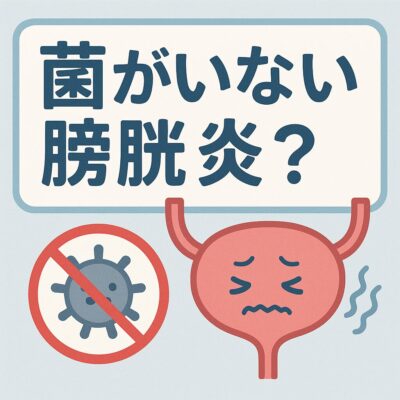
膀胱炎といえば「細菌感染によって起こる病気」というイメージが強いですが、実際には菌が検出されないのに症状が出るタイプの膀胱炎も存在します。
「尿が近い」「残尿感がある」「排尿時に痛い」といった典型的な膀胱炎の症状があるにもかかわらず、尿検査で細菌が見つからない――そんな場合、考えられるのが無菌性膀胱炎(非細菌性膀胱炎)や間質性膀胱炎です。
膀胱炎の基本 ― 原因のほとんどは大腸菌
膀胱炎の原因の大部分は細菌感染です。
特に多いのが大腸菌(Escherichia coli)。大腸菌は本来、腸内に存在する常在菌ですが、肛門から尿道へと侵入し、膀胱まで達すると感染を起こします。
女性に膀胱炎が多いのは、尿道が短く、肛門との距離が近いという解剖学的な理由によるものです。
さらに、排便後の拭き方、性的接触、ストレス、疲労などが誘因になることもあります。
一般的な膀胱炎(細菌性膀胱炎)は、抗生物質を数日服用すれば改善します。
しかし、なかには「菌が検出されないのに症状が出る」という、やっかいなケースもあります。
検査で菌が見つからないのに膀胱炎のような症状 ― 無菌性膀胱炎とは?
尿検査で細菌が検出されないのに、排尿痛・頻尿・残尿感がある――
このような場合に疑われるのが無菌性膀胱炎(非細菌性膀胱炎)です。
無菌性膀胱炎は、細菌感染ではないため、抗生物質を使っても効果がありません。
原因としては次のようなものがあります。
ウイルスや真菌による炎症
ヘルペスウイルスやアデノウイルス、カンジダなどが関与する場合があります。
これらは通常の尿培養では検出されにくいため、「菌がいない」と判断されることがあります。
薬剤性膀胱炎
抗がん剤のシクロホスファミドやイホスファミドなどは、代謝産物が膀胱粘膜を刺激して炎症を起こすことがあります。
この場合も細菌感染ではないため、抗菌薬は無効です。
放射線性膀胱炎
骨盤部への放射線治療の影響で膀胱粘膜が傷つき、慢性的な炎症を起こすことがあります。
女性ホルモンの低下
中高年女性では、エストロゲンの減少により膀胱や尿道粘膜が薄くなり、刺激に敏感になることがあります。
このため「感染ではないのに炎症を起こしたような状態」が生じ、膀胱炎に似た症状を呈します。
心因性・自律神経性の要因
強いストレスや自律神経の乱れが、膀胱の知覚過敏や筋緊張を引き起こすことがあります。
明確な原因が見つからない場合、医師が抗不安薬(安定剤)や漢方薬を処方することもあります。
抗生物質が効かない膀胱炎 ― 間質性膀胱炎とは?
無菌性膀胱炎のなかでも特に注目されているのが、間質性膀胱炎(Interstitial cystitis)または膀胱痛症候群(Bladder pain syndrome)と呼ばれる疾患です。
この病気は、膀胱の最内層(上皮)よりも下にある間質という組織に、慢性的な炎症が起こるのが特徴です。
この炎症により膀胱が知覚過敏状態になり、少しの刺激でも強い尿意や痛みを感じます。
間質性膀胱炎の主な症状
・頻尿(昼夜問わず何度もトイレに行きたくなる)
・尿意切迫感(急に強い尿意が起こる)
・排尿時の痛みや不快感
・膀胱や下腹部の鈍痛
・膀胱に尿をためると痛みが強くなり、排尿後に一時的に楽になる
これらの症状は、通常の細菌性膀胱炎と非常によく似ています。
しかし尿検査では細菌が検出されず、抗菌薬を服用しても改善しないのが大きな違いです。
過活動膀胱との違い
頻尿や尿意切迫感という点では過活動膀胱(OAB)とも似ていますが、異なる点もあります。
| 症状 | 間質性膀胱炎 | 過活動膀胱 |
|---|---|---|
| 主な原因 | 炎症・粘膜障害・知覚過敏 | 排尿筋の過剰収縮 |
| 尿意 | 痛みを伴う尿意 | 痛みはほとんどない |
| 抗コリン薬 | 効果が乏しい | 有効な場合が多い |
| 尿検査 | 菌は検出されない | 菌は検出されない |
| 代表的治療 | 抗ヒスタミン薬・抗うつ薬・膀胱拡張療法など | 抗コリン薬・β3刺激薬など |
このように、症状が似ていても治療方針がまったく異なるため、正確な診断が重要です。
間質性膀胱炎の原因 ― まだ不明な部分も多い
間質性膀胱炎の明確な原因はまだわかっていません。
現在、次のような仮説が考えられています。
膀胱粘膜の防御機能の低下
膀胱内面を覆う「グリコサミノグリカン層(GAG層)」が損傷し、尿中の刺激物質が組織に浸透して炎症を起こす。
免疫系の異常反応
自己免疫疾患のように、体の免疫が膀胱組織を攻撃している可能性。
神経の過敏化
繰り返す炎症で神経が敏感になり、痛みを感じやすくなっている。
ホルモンバランスやストレスの関与
エストロゲンの低下や心理的ストレスが症状を悪化させることもあります。
検査と診断 ― 「膀胱鏡+水圧拡張」がカギ
尿検査では菌が検出されず、画像検査でも異常が見つからないことが多い間質性膀胱炎。
診断には、膀胱鏡検査が重要な役割を果たします。
膀胱鏡を挿入して観察すると、膀胱内に点状の出血(ハンナー病変)が見られることがあります。
さらに「膀胱水圧拡張検査」と呼ばれる方法で、膀胱に生理食塩水を注入して膨らませると、出血がより明瞭に現れます。
この検査は診断と治療を兼ねており、膀胱を一時的に拡張することで症状が軽くなる例も多く、報告では約8割の患者で一時的な改善が見られるといわれます。
間質性膀胱炎の治療 ― 長期戦になることも
間質性膀胱炎の治療は、原因がはっきりしないため対症療法が中心です。
薬物療法
・抗ヒスタミン薬・抗アレルギー薬:炎症やアレルギー反応を抑える
・尿アルカリ化薬(クエン酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウムなど):尿の刺激を軽減
・H₂ブロッカー(シメチジンなど):粘膜保護作用
・三環系抗うつ薬(アミトリプチリン):痛みを伝える神経の過敏を抑える
・抗けいれん薬(ガバペンチンなど):神経性の痛みを緩和
物理的治療
・膀胱水圧拡張療法:膀胱を拡張して神経過敏をリセットする
・局所麻酔薬やヒアルロン酸の膀胱内注入:粘膜保護や鎮痛を目的とする
生活習慣の工夫
・コーヒー・アルコール・柑橘類・辛い食品など、尿を刺激する食べ物を控える
排尿を我慢せず、適度にトイレに行く
・ストレスをためない、睡眠を十分に取る
「気のせい」ではない膀胱炎
以前は、菌がいない膀胱炎は「気のせい」「ストレスのせい」と片づけられることもありました。
しかし、近年では間質性膀胱炎や非細菌性膀胱炎が実在する疾患であることが広く認識されつつあります。
特に日本ではこれまで稀とされてきましたが、アメリカでは100万人以上の患者がいるとされ、日本でも40歳以上女性の約3割が頻尿に悩んでいるとの調査もあります。
実際には、未診断の間質性膀胱炎が多数存在している可能性があります。
まとめ ― 抗生物質が効かないときは要注意
膀胱炎の症状があるのに菌が出ない、抗生物質を飲んでも治らない、そんなときは「無菌性膀胱炎」「間質性膀胱炎」を疑う必要があります。
・菌がいないのに膀胱炎のような症状が出ることがある
・原因はホルモン、アレルギー、神経の過敏、ストレスなど多様
・抗生物質では治らず、専門的な検査と治療が必要
・「気のせい」ではなく、実際に存在する病気
女性に多く、長く続く排尿トラブルの陰には、こうした非細菌性の膀胱炎が隠れているかもしれません。
市販の膀胱炎治療薬で改善しない場合は、早めに泌尿器科を受診し、適切な診断と治療を受けましょう。




