記事
ミラペックスとビ・シフロールの違いは?
公開. 更新. 投稿者: 1,162 ビュー. カテゴリ:睡眠障害.この記事は約5分36秒で読めます.
目次
ミラペックスとビ・シフロールの違い
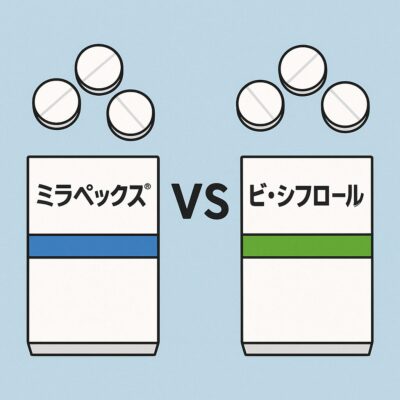
パーキンソン病治療薬の中でもドパミン受容体作動薬は、L-DOPAに次いで重要な位置を占めています。
中でもプラミペキソール(pramipexole)は、運動症状の改善に加え、うつや倦怠感など非運動症状にも有用であることが知られています。
日本ではこのプラミペキソールを有効成分とする製剤として、
ミラペックス®とビ・シフロール®の2種類が存在します。
同じ有効成分でありながら、添付文書上の適応症・用法用量・製剤設計にいくつかの違いがあります。
この記事では、両剤の違いを薬理学的背景から整理し、
実際の切り替え時の用量調整や注意点まで掘り下げて解説します。
プラミペキソールとは
プラミペキソールは、ドパミンD₂様受容体(特にD₃受容体)選択的作動薬です。
中脳黒質線条体系において、ドパミン神経の減少に伴う運動障害を改善します。
・D₂受容体刺激 → 運動制御改善
・D₃受容体刺激 → 意欲低下や抑うつなど非運動症状の改善にも寄与
L-DOPAと比較すると、プラミペキソールは神経変性に左右されにくく、wearing-off現象が少ないという特徴があります。
ただし、幻覚・傾眠・衝動制御障害などの副作用には注意が必要です。
ミラペックスとビ・シフロールの基本情報
| 項目 | ミラペックス | ビ・シフロール |
| 一般名 | プラミペキソール塩酸塩水和物 | プラミペキソール塩酸塩水和物 |
| 適応症 | パーキンソン病のみ | パーキンソン病、レストレスレッグス症候群(RLS) |
| 投与回数 | 1日1回 | 1日1~3回 |
適応症の違い
両剤とも基本はパーキンソン病ですが、
レストレスレッグス症候群(RLS)への適応があるのはミラペックスのみです。
ミラペックスの効能・効果
・パーキンソン病のみ
ビ・シフロールの効能・効果
・パーキンソン病・レストレスレッグス症候群(むずむず脚症候群)
RLSは「下肢の不快感・むずむず感で眠れない」症状を特徴とし、
中枢ドパミン機能低下が関与することが知られています。
プラミペキソールはこのドパミン低下を補う作用により、RLS症状を改善します。
したがって、RLS治療でミラペックスを使用していた患者をビ・シフロールに切り替えることは不可です。
添付文書上の適応外使用となり、保険算定上も問題になります。
用法・用量の違い
パーキンソン病における用法・用量
・ビ・シフロール錠:0.375mg/日から開始し、漸増。維持量0.375〜4.5mg/日を分3。最大4.5mg/日
・ミラペックスLA錠(徐放) 0.375mg/日から開始し、1日1回経口投与。最大4.5mg/日
※LA錠は1日1回投与で、同一成分ながら血中濃度が緩やかに上昇し、安定維持します。
RLSにおけるミラペックス用量
・就寝2〜3時間前に0.125mgより開始 0.5mg/日まで漸増可能
RLSでは極めて低用量から開始し、パーキンソン病の約1/10以下の量で有効です。
この点も、両剤を安易に置き換えることができない理由の一つです。
ミラペックスLA錠の特徴
・1日1回投与で血中濃度を安定化
・夜間のwearing-offや朝のオン遅延に有用
・持続性により服薬アドヒアランス向上
・初期は眠気・起立性低血圧などに注意
切り替え時の用量設定と注意点
プラミペキソールは同一有効成分を持つため、
原則として等量換算が可能です。
しかし、臨床的には以下の点に注意が必要です。
同一成分でも添加物・製剤が異なる
ミラペックスとビ・シフロールは、添加物・錠剤硬度・崩壊特性などが異なります。
そのため、「同量でも体感が違う」と訴える患者もいます。
切り替え時は副作用や眠気、幻覚の出現に注意して経過観察が必要です。
RLS→ビ・シフロールは不可
RLSの適応を持たないため、切り替えること自体が不適切です。
保険審査で査定される可能性もあります。
LA錠⇔即放錠の切り替え
ミラペックスLA錠(徐放)から即放性製剤に切り替える際は、
1日総量をそのまま3分割してもおおむね同等効果が得られます。
ただし、LA錠は血中濃度の立ち上がりが遅く、切り替え初日〜2日はオフ時間が出やすいため、
L-DOPA製剤で補うことも検討されます。
副作用とモニタリング
プラミペキソールの副作用は両剤共通です。
導入期・漸増期に注意すべき点を以下にまとめます。
・傾眠・突発的睡眠 (5〜10%):運転禁止指導、用量調整
・幻覚・妄想:高齢者に多い、抗精神病薬慎重投与
・衝動制御障害(ギャンブル、過食など)(数%):家族への説明が重要
・浮腫:末梢血管拡張作用、利尿薬の追加を検討
・嘔気:初期に多い、制吐剤(ドンペリドン)併用
臨床上の使い分け
・初期パーキンソン病➡どちらでも可:同成分・同等効果
・夜間off現象が強い➡ミラペックスLA錠:血中濃度安定化
・RLS症状あり➡ミラペックス:唯一の適応あり
・薬価抑制目的➡ジェネリック(プラミペキソール錠):同等製剤あり
・服薬回数を減らしたい➡ミラペックスLA :1日1回で服薬負担軽減
RLSにおける注意点 ― ドパミン増感現象(augmentation)
RLSでプラミペキソールを長期間使用すると、
症状がかえって悪化する「オーグメンテーション現象」が知られています。
これは長期的なドパミン受容体過刺激によるもので、
発症時間の前倒し・症状範囲の拡大を特徴とします。
したがって、RLSに対しては
・できる限り低用量で維持
・増量は慎重に
・日中症状が出た場合はα₂δリガンド(ガバペンチンエナカルビルなど)への切り替えを検討
が原則です。
おわりに
ミラペックスとビ・シフロールは、有効成分こそ同じでも、
適応症・剤形・臨床的使い方が異なる「兄弟薬」といえます。
実際の薬局現場では、「同じプラミペキソールなのに名前が違う」という点で、
医師・薬剤師・患者の間で混乱が生じやすい薬の一つです。
薬剤師としては、患者がどの疾患目的で処方されているのか、
あるいはどの剤形・用量でコントロールされているのかを確認することが重要です。
特にレストレスレッグス症候群(RLS)ではミラペックス一択であること、
徐放製剤(LA錠)の有無が切り替え時のポイントになることを覚えておくと、
現場での疑義照会・指導の精度が格段に上がります。





2 件のコメント
適応症について
ビ・シフロール→パーキンソン+むずむず
ミラペックス→パーキンソンのみ
ではないでしょうか?
コメントありがとうございます。
やっちまいました。修正いたします。