記事
ミドリンPがぶどう膜炎に効く?
公開. 更新. 投稿者: 14,245 ビュー. カテゴリ:眼/目薬/メガネ.この記事は約3分24秒で読めます.
ミドリンPがぶどう膜炎に効く?散瞳薬の役割と使い分け
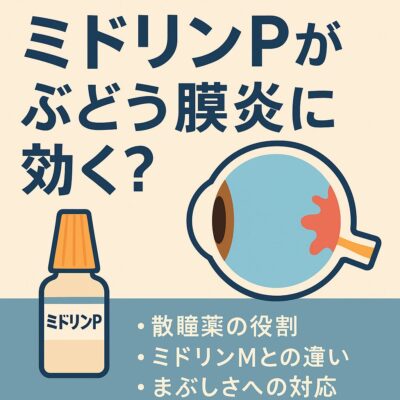
高血圧や糖尿病と同じように「目の病気」も慢性的に付き合っていく必要があるものが多くあります。その中で「ぶどう膜炎」は、視力低下や失明の原因となりうる重大な疾患です。
治療にはステロイドや免疫抑制薬などが使われますが、点眼薬として散瞳薬(ミドリンなど)が併用されることがあります。
一見すると「散瞳薬=眼底検査に使う薬」というイメージがありますが、実は治療にも意味があるのです。
ぶどう膜炎とは何か
ぶどう膜とは?
眼球を内側から包む構造のうち、虹彩・毛様体・脈絡膜を合わせて「ぶどう膜」と呼びます。血流が豊富で免疫反応も活発なため、全身疾患に関連して炎症を起こすことがあります。
虹彩後癒着とは?
ぶどう膜炎が起こると、虹彩表面に炎症性の滲出物が出てきます。これが水晶体の前面に接して固着すると、虹彩後癒着(posterior synechia)が形成されます。
虹彩後癒着が起こると瞳孔が変形し、房水の流れが悪くなり、続発性緑内障や視力障害を引き起こすリスクが高まります。
散瞳薬が果たす役割
ぶどう膜炎の治療において散瞳薬を投与する理由は以下の通りです。
・虹彩と水晶体を離す:瞳孔を広げて距離を確保し、癒着を防ぐ。
・虹彩を動かす:散瞳と縮瞳を繰り返すことで癒着を物理的に引き剥がす。
・炎症の疼痛緩和:虹彩のけいれんを抑えることで、眼痛や光刺激に伴う不快感を和らげる。
つまり散瞳薬は「炎症そのものを抑える薬」ではありませんが、合併症や後遺症を防ぐ上で重要な補助治療薬です。
ミドリンMとミドリンPの違い
散瞳薬として代表的なのが ミドリンM と ミドリンP です。
製剤 成分 作用機序 主な用途 効果持続時間
ミドリンM トロピカミド(副交感神経遮断薬) 瞳孔括約筋を麻痺 → 散瞳 仮性近視、眼底検査 約5〜8時間
ミドリンP トロピカミド+フェニレフリン(交感神経刺激薬) 瞳孔括約筋を麻痺+瞳孔散大筋を収縮 → 強力な散瞳 眼底検査、術前散瞳、ぶどう膜炎での虹彩後癒着予防 約6〜12時間
ミドリンMは単剤(トロピカミド)のため作用が比較的マイルドで、夜間点眼で仮性近視に用いられることもあります。
ミドリンPは配合薬で散瞳作用が強く、持続時間も長い。検査・処置で使われることが多く、治療目的での処方は比較的少ないです。
- ぶどう膜炎におけるミドリンPの意義
ぶどう膜炎で虹彩後癒着を防ぐために散瞳薬を連日点眼することがあります。その際にミドリンPが選択されるケースがあります。
トロピカミドによる瞳孔括約筋弛緩
フェニレフリンによる瞳孔散大筋収縮
この二つの作用で、より確実で強力な散瞳が得られるためです。
特に癒着のリスクが高い症例では、ミドリンMよりもミドリンPの方が効果的と判断されることがあります。
- まぶしさ(羞明)という問題
散瞳薬を使うと「まぶしい」と訴える患者は多くいます。これは瞳孔が広がり、光が入りやすくなるためで、医学用語では羞明(しゅうめい)と呼ばれます。
なぜ添付文書に「羞明」と書かれていないのか?
散瞳は薬の主要な作用であり、羞明は「予測される現象」と整理されているため、副作用として明記されないことが多い。
代わりに「霧視」「視覚異常」などの表現で記載されることがあります。
ぶどう膜炎で連日投与した場合は?
ミドリンPを連日点眼すると、瞳孔が常に大きく開いた状態が続き、羞明が慢性的に起こり得ます。
実務上はサングラスや遮光眼鏡を使用して対応します。
患者指導の場面では「散瞳薬を使っている間は光をまぶしく感じるのは普通のこと」と説明して安心させることが大切です。
- 実際の処方状況
眼底検査や手術前処置:ミドリンPが多用される。
仮性近視:ミドリンM(トロピカミド単剤)が選ばれる。
ぶどう膜炎:虹彩癒着のリスクが高ければミドリンPが処方されることがある。
つまり、ミドリンPは「検査薬」という印象が強いですが、治療薬としても一定の役割を持っているのです。
まとめ
ミドリンPはトロピカミド+フェニレフリンの合剤で、強力かつ持続的な散瞳作用を持つ。
主に眼底検査や術前処置に使われるが、ぶどう膜炎の虹彩後癒着を防ぐ目的でも用いられる。
ミドリンMはトロピカミド単剤で作用がマイルド。仮性近視や眼底検査に使用される。
散瞳薬の使用に伴い羞明は避けられず、特にぶどう膜炎での連日使用では慢性的にまぶしさを感じることがある。
医療従事者は患者に「まぶしさは予測される現象」であることを伝え、遮光眼鏡の使用など生活上の工夫を提案することが重要。




