記事
脱毛しやすい抗癌剤― 抗がん剤による脱毛のしくみと薬ごとの違い
公開. 更新. 投稿者: 1,184 ビュー. カテゴリ:癌/抗癌剤.この記事は約6分51秒で読めます.
目次
抗がん剤と脱毛
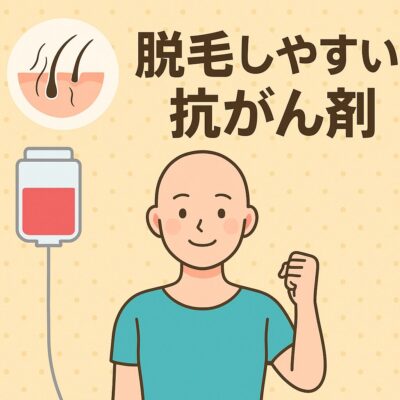
抗がん剤治療というと「髪が抜ける」というイメージを持つ人は多いでしょう。
しかし実際には、すべての抗がん剤で脱毛が起こるわけではありません。
薬の種類や作用機序によって、脱毛の頻度や程度は大きく異なります。
抗がん剤による脱毛のメカニズム、脱毛しやすい薬とそうでない薬、そして近年進歩している脱毛予防の工夫まで、勉強していきます。
抗がん剤でなぜ髪が抜けるのか?
私たちの髪の毛は、頭皮の中にある「毛母細胞」が盛んに分裂することで伸びています。
抗がん剤の多くは「細胞分裂の活発な細胞を攻撃する」性質を持っています。
がん細胞は異常な増殖を続けるため、抗がん剤の標的となりますが、同時に毛母細胞も影響を受けてしまうのです。
毛母細胞がダメージを受けると、毛髪の成長が止まり、毛が抜けやすくなります。
つまり、抗がん剤による脱毛は、薬の副作用というよりも「作用の延長線上」にある現象といえます。
脱毛の時期と回復の経過
脱毛は多くの場合、治療開始後2〜3週間で始まります。
最初はブラッシング時の抜け毛が増え、次第に頭皮が透けて見えるようになります。
治療が進むと頭髪だけでなく、眉毛、まつ毛、体毛、陰毛まで抜けることもあります。
ただし、抗がん剤による脱毛は一時的なものです。
治療が終わると毛母細胞が回復し、1〜3か月ほどで再生が始まります。
再生初期には「色が薄い」「縮れている」「白髪が増える」といった変化がみられることもありますが、多くは半年〜1年ほどで元に戻ります。
脱毛の強さは薬によって違う
脱毛の程度は、抗がん剤の種類によって明確に異なります。
一般に「細胞障害性抗がん剤」と呼ばれるタイプほど脱毛が起こりやすく、
「分子標的薬」や「免疫チェックポイント阻害薬」では脱毛が少ない傾向があります。
以下では、薬の系統別に脱毛の強さを見ていきましょう。
タキサン系 ― 脱毛頻度が最も高い薬
主な薬剤:
・パクリタキセル(タキソール)
・ドセタキセル(タキソテール)
・ナブパクリタキセル(アブラキサン)
タキサン系は微小管を安定化させることで、がん細胞の分裂を止めます。
この「分裂を止める作用」が毛母細胞にも及び、ほぼ確実に脱毛が起こるといわれます。
頭髪だけでなく、眉毛・まつ毛・鼻毛・体毛まで抜けることが多く、
治療中はウィッグや帽子の準備が必要になるケースが一般的です。
ただし治療終了後の回復も早く、3か月ほどで再生が始まります。
最近ではスカルプクーリングを併用することで、脱毛を軽減できる症例も報告されています。
アントラサイクリン系 ― 鮮やかな赤色の強力な抗がん剤
主な薬剤:
・ドキソルビシン(アドリアシン)
・エピルビシン(ファルモルビシン)
・ダウノルビシン
イダルビシン
赤色の溶液が特徴的なアントラサイクリン系は、DNA合成を阻害し、がん細胞を強力に攻撃します。
この薬も脱毛の頻度は非常に高く、ほぼ100%に近いとされます。
乳がんの「AC療法(アドリアシン+エンドキサン)」などでは、
タキサン系と並んで脱毛の代表格です。
治療後には毛質や髪色が変化することがありますが、多くは時間とともに回復します。
アルキル化剤 ― 古くから使われる定番の抗がん剤
主な薬剤:
・シクロホスファミド(エンドキサン)
・イホスファミド(イホマイド)
・ダカルバジン
・ベンダムスチン
アルキル化剤はDNAに直接結合して細胞分裂を妨げるタイプの抗がん剤です。
汎用性が高く、乳がん、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫など多くのがんで使用されます。
脱毛はやや遅れて出現することが多いものの、程度は中等度〜高度で、
長期投与ではほぼ確実に抜けます。
トポイソメラーゼ阻害薬 ― イリノテカンなど
主な薬剤:
・イリノテカン(カンプト、トポテシン)
・トポテカン(ハイカムチン)
・エトポシド(ラステット)
DNAのねじれをほどく酵素(トポイソメラーゼ)を阻害することで細胞分裂を止める薬です。
脱毛は中等度程度で、全脱毛に至る人もいれば、部分的な脱毛にとどまる人もいます。
イリノテカンは下痢など消化器症状が有名ですが、脱毛の頻度も無視できません。
抗代謝薬 ― 比較的脱毛が少ない薬
主な薬剤:
・フルオロウラシル(5-FU)
・カペシタビン(ゼローダ)
・テガフール・ウラシル(ユーエフティ)
・S-1(ティーエスワン)
・メトトレキサート
抗代謝薬はDNAの材料となる物質を妨害して、がん細胞の増殖を止めます。
毛母細胞への影響は比較的穏やかで、脱毛は軽度〜中等度にとどまります。
部分的に薄くなる程度で済むケースも多く、ウィッグを必要としないこともあります。
S-1のように経口で長期内服する薬では、脱毛よりも口内炎や色素沈着が問題となることが多いです。
分子標的薬 ― 精密医療の時代の抗がん剤
主な薬剤:
・イマチニブ(グリベック)
・エルロチニブ(タルセバ)
・ゲフィチニブ(イレッサ)
・ソラフェニブ(ネクサバール)
・スニチニブ(スーテント)
分子標的薬は、がん細胞特有のシグナル伝達を狙い撃ちする薬です。
正常細胞の分裂にはあまり影響を与えないため、脱毛はまれまたは軽度です。
むしろ特徴的なのは「皮疹」「乾燥」「手足症候群」などの皮膚障害。
頭髪が細くなる、部分的に薄くなる程度の変化はみられるものの、
ウィッグを必要とするほどの脱毛は少ないです。
免疫チェックポイント阻害薬 ― 新しいがん治療の波
主な薬剤:
・ニボルマブ(オプジーボ)
・ペムブロリズマブ(キイトルーダ)
・アテゾリズマブ(テセントリク)
がん細胞が免疫から逃れる仕組みを解除し、自分の免疫でがんを攻撃させる薬です。
毛母細胞への直接的な影響はほとんどなく、脱毛はまれです。
ただし免疫の異常反応として「円形脱毛症」のような症状を起こすことがあり、
これを免疫関連有害事象(irAE)と呼びます。
脱毛の強さを比較
・タキサン系(パクリタキセル、ドセタキセル):★★★★★ 全身脱毛が多い
・アントラサイクリン系(ドキソルビシン、エピルビシン):★★★★★ 乳がん治療で頻発
・アルキル化剤(シクロホスファミド、イホスファミド):★★★★☆ 治療期間で強くなる
・トポイソメラーゼ阻害薬(イリノテカン、エトポシド):★★★☆☆ 中等度
・抗代謝薬(5-FU、S-1、カペシタビン):★★☆☆☆ 軽度
・分子標的薬(イマチニブ、エルロチニブ):★☆☆☆☆ まれ
・免疫チェックポイント阻害薬(オプジーボ、キイトルーダ):★☆☆☆☆ まれ
スカルプクーリング(頭皮冷却療法)とは?
近年、脱毛を軽減する方法として「スカルプクーリング」が注目されています。
冷却キャップを装着して頭皮を10〜20℃程度に冷やすことで、
頭皮の血流を減らし、抗がん剤が毛根に到達するのを抑える仕組みです。
欧米ではすでに広く普及しており、日本でも乳がん治療を中心に導入が進んでいます。
完全に脱毛を防ぐことはできませんが、「部分的な温存」や「回復の早期化」が期待できます。
副作用としては頭痛や寒気などがありますが、多くは一時的です。
病院によっては自費(数万円/1クール)で提供されている場合もあります。
脱毛時の生活上の工夫
・ウィッグや帽子の準備:治療開始前から試着し、自分に合うものを選ぶ。
・頭皮ケア:刺激の少ないシャンプーを使用し、乾燥を防ぐ。
・日焼け対策:脱毛部は紫外線に弱くなるため帽子や日焼け止めを活用。
・まつ毛・眉毛ケア:眉毛用ペンシルやつけまつげで自然な印象に。
・心のケア:脱毛は外見の変化として精神的な負担が大きいため、医療スタッフやカウンセラーと相談を。
まとめ ― 脱毛は「治療が効いている証拠」でもある
抗がん剤による脱毛は、誰にとってもつらい副作用のひとつです。
しかし、それは同時に「がん細胞と同じく、細胞分裂の盛んな細胞が反応している」ということでもあります。
つまり、薬がきちんと働いている証拠ともいえるのです。
最近では脱毛を防ぐ技術や、より脱毛しにくい抗がん剤も増えています。
一時的な変化に過ぎないことを理解し、治療終了後には再び髪が生えてくるという希望を持つことが大切です。




