記事
骨の痛みにビスホスホネートは効くのか? がんの骨転移と骨痛治療
公開. 更新. 投稿者: 2,878 ビュー. カテゴリ:骨粗鬆症.この記事は約4分3秒で読めます.
目次
骨の痛みにビスホスホネートは効くのか?
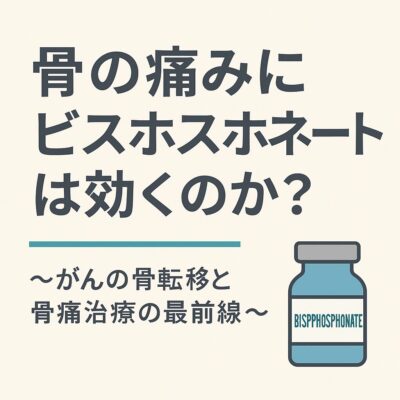
「骨が痛い」と訴える患者さん。整形外科の領域ではよく耳にする症状ですが、その原因が一筋縄ではいかないのが「骨痛(こつつう)」という症状です。筋肉痛や関節痛は一般の方にも比較的イメージしやすい一方で、「骨そのものが痛い」ことを想像できる方はあまり多くないかもしれません。
しかし、骨もれっきとした「感覚のある器官」であり、適切な病態では痛みを生じます。
骨に神経はあるのか?
「骨の中に神経なんてあるの?」と疑問に思った方もいるかもしれません。たしかに骨の内部には多くの神経は通っていませんが、骨膜や骨髄には豊富な神経や血管が走っており、特に骨膜には痛覚受容器が多く存在します。
そのため、骨膜への刺激や炎症、腫瘍による圧迫・破壊などがあれば、強い痛みとして感じられるのです。
骨転移と骨痛
悪性腫瘍が骨に転移した場合、「骨痛」はよく見られる症状のひとつです。骨転移を起こしやすい癌としては以下が代表的です。
・乳がん
・前立腺がん
・肺腺がん
・多発性骨髄腫
これらのがんでは、血流豊富な骨組織に転移しやすく、特に脊椎、骨盤、大腿骨、肋骨などでの転移が多く見られます。
骨転移によって引き起こされる合併症には以下のようなものがあります。
・骨痛
・病的骨折
・脊髄圧迫(脊髄損傷)
・高カルシウム血症
中でも最も患者さんのQOL(生活の質)に影響を与えるのが「骨痛」です。強い痛みのために日常生活が制限されるだけでなく、病的骨折によって寝たきりになるリスクもあります。
骨痛の原因 〜なぜ痛むのか?〜
骨転移による骨痛は、単なる圧迫や腫瘍増大によるものだけではありません。転移が起こると、がん細胞が以下のような物質を放出し、破骨細胞を異常に活性化させます。
・副甲状腺関連蛋白質(PTHrP)
・インターロイキン-1(IL-1)
・インターロイキン-6(IL-6)
これらの物質は破骨細胞を刺激し、骨吸収(骨を壊すプロセス)を促進します。骨吸収が進むと骨がもろくなり、骨膜にある痛覚受容器が刺激されたり、微小骨折が生じることで痛みが発生します。
さらに骨の構造が破壊されることで、腫瘍の浸潤が進み、神経組織への圧迫や炎症が起こることも、骨痛の重要な要因です。
骨痛の治療選択肢
骨転移による骨痛の治療は、複数の方法を組み合わせて行われます。
・鎮痛薬(NSAIDs、オピオイドなど)
痛みの強さに応じて使い分けられます。がん性疼痛ではモルヒネやフェンタニルなどのオピオイドが中心。
・放射線治療
局所的な骨転移に対しては、放射線治療によって腫瘍の縮小・疼痛緩和が期待できます。
・神経ブロック
痛みが強い場合には、神経ブロック注射によって一時的に痛みを遮断することもあります。
・ビスホスホネート製剤
近年、がんの骨転移による骨痛の管理において、ビスホスホネート系薬剤が重要な役割を担っていることが明らかになってきました。
ビスホスホネート製剤とは?
ビスホスホネートは、破骨細胞の機能を抑える薬剤です。もともとは骨粗鬆症の治療薬として開発されましたが、骨転移に対しても効果を示すことが分かり、がんの支持療法として保険適用を受けるようになりました。
主な作用機序:
・骨表面に結合し、破骨細胞が骨を溶かす過程を阻害
・骨吸収を抑えることで、骨構造の安定性を保つ
・結果として、骨痛や病的骨折の発生を予防・軽減できる
骨痛に対するビスホスホネートのエビデンス
複数の臨床試験により、ビスホスホネート製剤が骨転移による骨痛を軽減する効果を持つことが確認されています。
・パミドロン酸(アレディア)
・ゾレドロン酸(ゾメタ)
これらは、骨痛だけでなく、病的骨折の予防、高カルシウム血症の発症予防、脊髄圧迫の抑制などにも効果があると報告されています。
保険適用されている薬剤は?
現在、骨転移に対する保険適用があるビスホスホネート製剤は以下の2つです。
・パミドロン酸二ナトリウム :アレディア(2016年販売中止)→後発品のみ販売中
・ゾレドロン酸水和物:ゾメタ/ゾレドロン酸点滴静注
※アレディアは2016年に販売中止となり、現在はジェネリック医薬品のみ流通しています。
投与方法と注意点
ビスホスホネートは静脈内投与されることが多く、通常は3〜4週に1回の間隔で投与されます。
主な副作用:
・急性期反応(発熱、筋肉痛など)
・腎機能障害(腎クリアランスに依存)
・低カルシウム血症
・顎骨壊死(ONJ:osteonecrosis of the jaw)
特に顎骨壊死は問題視されており、歯科治療歴のある患者では投与前に口腔評価を行うことが推奨されています。
ビスホスホネート以外の治療薬
近年ではデノスマブ(ランマーク)という薬剤も登場しています。これはRANKL(破骨細胞の活性化因子)を直接阻害するモノクローナル抗体製剤で、ビスホスホネートとは異なる作用機序を持ちます。
・腎機能に依存しないため、腎障害のある患者にも使用可能
・皮下注射での投与が可能
ただし、副作用に関してはビスホスホネートと似たリスク(顎骨壊死、低Ca血症)があるため、同様の注意が必要です。
骨の痛みとどう向き合うか
ビスホスホネート系薬剤は、単なる「骨を強くする薬」ではありません。がん患者にとって、痛みを和らげ、生活の質を保つための重要な支持療法です。
服薬指導においては、「飲んで終わり」「打って終わり」ではなく、口腔ケアの重要性や、血液検査・カルシウム補充の必要性について丁寧に伝えることが、薬剤師の役割です。




