記事
CT検査の前にβブロッカーを飲ませる?─冠動脈CTと心拍コントロール
公開. 更新. 投稿者: 6,024 ビュー. カテゴリ:不整脈.この記事は約4分16秒で読めます.
目次
CT検査の前にβブロッカーを飲むのは本当?─冠動脈CTと心拍コントロールの医学的理由
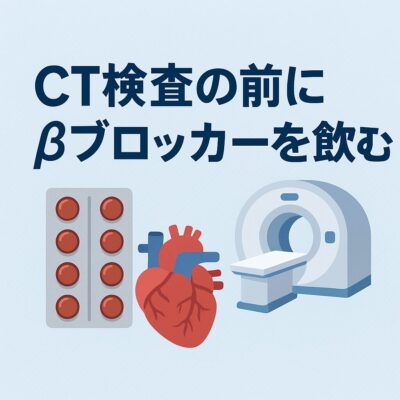
CT検査は現代医療において欠かせない画像診断技術であり、がん・内臓疾患・血管病変まで幅広く利用されている。しかし、その中でも 心臓(冠動脈)を評価するCT検査だけは「他のCTとはまったく性質が違う」ことをご存じだろうか。
胸部CTや腹部CTでは薬を事前に飲む必要はほとんどない。
しかし、冠動脈CT(CCTA:Coronary CT Angiography)の場合は、
検査前にβブロッカー(心拍数を下げる薬)を服用することが一般的である。
なぜ、冠動脈のCTだけ薬が必要なのか?
なぜ心拍数が下がると画像が良くなるのか?
どのような薬が使われるのか?
危険性はないのか?
保険診療としてはどう扱われるのか?
薬剤師として知っておくべき 「冠動脈CTとβブロッカー」の仕組み、臨床運用、禁忌、代替手段などを勉強していく。
CT検査の中でも冠動脈CTは“特殊な検査”
通常のCTは、腹部・胸部・頭部などを撮影するが、臓器は比較的静止しているため、画像がブレにくい。
しかし、心臓だけは事情が違う。
・1分間に60〜80回打ち続ける
・横方向に揺れ、収縮・拡張を繰り返す
・血流量が多く、血管も常に動いている
このため、動いている対象を撮影するための特別な工夫が必要になる。
そのひとつが
「心臓が止まって見える瞬間(静止相)」を狙って撮影すること
である。
冠動脈CTは、この“わずかな静止相”を高精度で捉える必要があるため、心拍が早すぎると画像がボケてしまう。
心拍数が高いと画像がブレる理由
現代の冠動脈CTは「マルチスライスCT」と呼ばれ、1回転で大量の断面を取得できる。しかし、どれだけ装置が進化しても、
被写体(心臓)が高速で動いていたらブレは避けられない。
● 心拍が速いと問題が起きる
1回の心拍の中で画像に適しているのは、収縮期と拡張期の“ほんの数ミリ秒”だけ。
心拍が速いと:
・静止時間が短くなる
・CTの取得時間が静止相に一致しない
・その結果、冠動脈の輪郭がボケる
・狭窄(血管の細い部分)を評価できなくなる
つまり、心拍が高い=冠動脈CTは失敗しやすいという構造がある。
理想の心拍数は「60 bpm以下」
冠動脈CT撮影の理想は
心拍数 50〜60/分。
多くの施設では、撮影前に次の基準を設定する。
・60以下 → 撮影可能
・65〜70 → 条件付きで撮影 or βブロッカー追加
・70以上 → 心拍コントロール必須
実際、緊張して70〜80台になっている患者は多い。
そこで登場するのがβブロッカーである。
βブロッカーを使う理由:心拍数を下げるため
βブロッカーは
・心拍数を下げる
・心臓の収縮力を抑える
・リラックスさせる(交感神経を抑制)
という作用があり、冠動脈CT撮影で最も重要な「心拍をゆっくりにする」目的に最適。
● どの薬を使うのか?
施設によるが、以下がよく使われる。
・テノーミン(アテノロール)
・セロケン(メトプロロール)
・インデラル(プロプラノロール)
・ランジオロール(静注) ←即効性が高い
とくに テノーミン・セロケン はβ1選択性が高く、気管支喘息への悪影響が比較的少ないため使われやすい。
● 内服タイミング
一般的には:
・検査の1〜2時間前に内服
・または検査直前に静注(ランジオロールなど)
βブロッカーを使うのは冠動脈CTだけ?
胸部CT・腹部CT・頭部CTでは使用しない。
βブロッカーを使うのはあくまで
“心臓の細い血管(冠動脈)を撮るときだけ”。
冠動脈の診断精度を高めるために、心拍をコントロールする必要があるからだ。
どんな患者に使えないのか(禁忌と注意)
βブロッカーは非常に有効だが、使えない患者もいる。
◆ 使用禁忌
・気管支喘息(特に非選択性βブロッカー)
・治療されていない高度徐脈
・2度・3度房室ブロック
・急性心不全
・βブロッカーアレルギー
◆ 使用注意
・COPD
・低血圧
・糖尿病で低血糖注意
・徐脈傾向
喘息患者には使わないため、検査自体が中止・延期になることもある。
βブロッカー以外の代替薬
βブロッカーが使えない患者には、以下の薬が使用されることがある。
● Ca拮抗薬(ジルチアゼムなど)
・心拍を下げる
・気道収縮がないため喘息患者でも使える
・効果はβブロッカーほど強くない
● 硝酸薬
・血管拡張で冠動脈を見やすくする補助
・心拍そのものはそこまで下がらない
・最終的に心拍が下がらなければ検査が成立しない場合もある。
検査の実際の流れ
1.来院時の脈拍測定
2.70以上の場合、βブロッカー追加指示
3.検査の1〜2時間前に内服
4.必要があれば直前に静注(ランジオロール等)
5.CT撮影
6.撮影後はβブロッカー継続なし(あくまで準備薬)
7.造影剤の観察(アレルギーに注意)
βブロッカー使用の安全性
一時的に脈を下げる目的で使うため、
ほとんどの患者で安全に使用できる。
・半減期が短い薬(ランジオロール)は“必要な時だけ効く”
・中止すればすぐに消失する
・通常は検査後に薬は残らない
医療機関では必ず
心電図・血圧・酸素飽和度をモニターしながら投与する。
冠動脈CTとβブロッカー ― まとめ
● βブロッカーを使う理由
・心拍を60/分以下に下げる
・心臓が“止まって見える瞬間”を長くする
・冠動脈の画質が劇的に向上する
● 使用する薬
・テノーミン(アテノロール)
・セロケン(メトプロロール)
・インデラル(プロプラノロール)
・ランジオロール(静注)
● 禁忌
・喘息
・重度の徐脈
・房室ブロック
・急性心不全
● 結論
CT検査の中でも、冠動脈CTだけは“心拍を遅くする必要がある”。
そのため、検査前にβブロッカーを使うのは医学的に合理的で、
全国の医療機関で広く行われている。




