記事
お酒を飲むと血圧は上がる?下がる?― アルコールと血圧の関係
公開. 更新. 投稿者: 3,851 ビュー. カテゴリ:肝炎/膵炎/胆道疾患.この記事は約5分24秒で読めます.
目次
お酒と血圧の関係、どっちが本当?
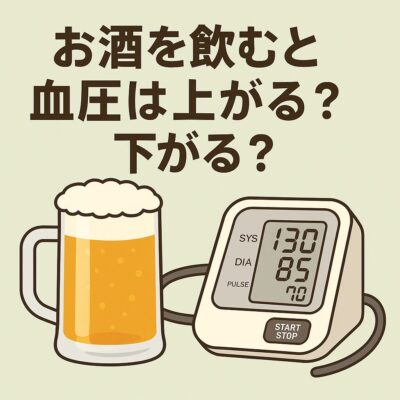
「お酒を飲むと血圧が上がる」と聞いたことはありませんか?
一方で、「お酒を飲むと血圧が下がる」という話も耳にします。
実は、どちらも正しいのです。
アルコールには短期的には血圧を下げる作用と、長期的には血圧を上げる作用の両方があります。
この二面性を理解しないと、「毎日飲んでるけど平気」と思っているうちに、高血圧が進行してしまうこともあります。
アルコールが血圧に与える影響を生理学的メカニズム・遺伝的体質・飲酒習慣・薬との関係といった観点から整理します。
アルコールを飲むと血圧は「一時的に下がる」
お酒を飲んだ直後、多くの人は顔が赤くなり、体が温かくなります。
これは、アルコールが末梢血管を拡張させているためです。
● アセトアルデヒドの血管拡張作用
体内に入ったエタノール(アルコール)は、肝臓の酵素「アルコール脱水素酵素(ADH)」によって酸化され、アセトアルデヒドに変わります。
このアセトアルデヒドが血中に増えると、血管が拡張し、血圧は一時的に低下します。
・血管拡張 → 末梢抵抗が低下
・血圧低下 → 代償的に心拍数が上昇(動悸)
・顔面紅潮・発汗・頭がボーッとする
いわゆる「ほろ酔い」状態は、この血管拡張作用によるものです。
● 日本人の約半数は「お酒に弱い」体質
アセトアルデヒドは、本来「アルデヒド脱水素酵素(ALDH2)」によって分解されます。
しかし、日本人の約55%はこのALDH2が不活性型(ALDH2*2)であり、アセトアルデヒドをうまく処理できません。
このため、
・顔が真っ赤になる
・脈が速くなる
・血圧が一時的に下がる
といった反応が強く出ます。
これがいわゆる「フラッシャー体質」です。
飲酒後しばらくして血圧は「上がる」
アセトアルデヒドが分解され、血中濃度が下がると、血管拡張作用は弱まります。
すると、体は血圧を元に戻そうとして交感神経を刺激します。
・交感神経刺激 → 血管収縮
・脈拍上昇・血圧上昇
・翌朝の「動悸」「顔のむくみ」など
つまり、アルコールによる血圧低下は一時的であり、時間が経つとむしろ上昇傾向になります。
とくに翌朝、「飲みすぎた翌日は血圧が高い」という人は少なくありません。
長年の飲酒で「慢性的に血圧が上がる」
お酒の血圧への影響で最も重要なのは、長期的な上昇作用です。
● 長期飲酒で血圧が上がる理由
交感神経の持続的な活性化
→ ノルアドレナリン分泌増加により、心拍数・血圧上昇。
腎臓でのナトリウム再吸収亢進
→ 体液量増加、循環血液量増。
アルコールと一緒に摂取する食事内容
→ 塩分・脂質が多くなり、肥満や動脈硬化を助長。
睡眠の質の低下
→ 睡眠時高血圧や夜間血圧非下降型を招く。
これらが重なって、慢性高血圧の発症リスクが高まります。
飲酒量と血圧上昇の関係
日本高血圧学会の報告では、アルコール摂取量と血圧上昇の間に明確な相関があります。
| アルコール量(1日) | 相当する酒量の目安 | 血圧上昇の目安 |
|---|---|---|
| 約10g(ビール中瓶1/3本) | 軽度飲酒 | ほぼ影響なし |
| 約30g(ビール大瓶1本) | 中等量 | 約3mmHg上昇 |
| 約60g以上(日本酒2合超) | 多量 | 5〜10mmHg上昇 |
さらに、飲酒を減らすと血圧が下がることも確認されています。
節酒を1か月継続すると、平均で収縮期血圧が3〜4mmHg低下するという報告もあります。
飲酒と薬の相互作用 ― 注意すべき薬剤群
アルコールは、単に血圧を変動させるだけでなく、降圧薬や血管拡張薬との相互作用にも注意が必要です。
● 降圧薬+アルコール
α遮断薬(ドキサゾシン、タムスロシンなど)
→ 起立性低血圧のリスク増大。
硝酸薬(ニトログリセリン、亜硝酸薬など)
→ 過度の血管拡張による失神の危険。
Ca拮抗薬(アムロジピンなど)
→ アルコールと併用で頭痛・顔面紅潮が強く出る。
ACE阻害薬・ARB
→ アルコールによる脱水で腎機能障害が悪化する可能性。
これらの薬を服用中の人は、「お酒を飲むと血圧が下がりすぎる」または「翌日高くなる」などの不安定な変動が起こりやすくなります。
「顔が赤くなる人」はより注意が必要
日本人の約半数は「ALDH2不活性型」であり、アセトアルデヒドを分解できません。
この体質では、次のような特徴があります。
・飲酒後に血圧低下が強く出る
・動悸や頭痛を感じやすい
・翌日に血圧上昇・脈拍増加が続く
このようなタイプの人は、少量のアルコールでも血管への負担が大きく、長期的な高血圧・心血管疾患リスクが高いとされています。
欧米人と比べて、日本人に「少量飲酒でも脳出血が多い」背景には、この遺伝的体質が関係しています。
飲酒と心血管イベントの関係
● アルコール誘発性冠攣縮(異型狭心症)
アルコールの代謝が進み、血中濃度が下がるとき(深夜〜早朝)に冠動脈が痙攣し、胸痛発作(狭心症)を起こすことがあります。
特に男性の常習飲酒者に多く、飲酒直後ではなく「酔いがさめた頃」に起こるのが特徴です。
● 心房細動との関連
アルコール摂取は心房細動(AF)の誘発因子として知られています。
「ホリデーハート症候群」と呼ばれるように、宴会などで一時的に大量飲酒すると、一過性の不整脈が起こることがあります。
適量飲酒の目安と節酒のすすめ
健康を守るためのアルコール摂取の上限は、以下のように定義されています(日本高血圧学会ガイドライン2023)。
| 性別 | 1日の純アルコール量 | 酒量の目安 |
|---|---|---|
| 男性 | 20gまで | ビール500mL、日本酒1合、ワイン200mL |
| 女性 | 10gまで | ビール250mL、日本酒0.5合、ワイン100mL |
これを超える飲酒を続けると、血圧上昇だけでなく、肝疾患、心筋障害、糖代謝異常、睡眠障害などのリスクも増大します。
● 節酒で得られる効果
・1〜2週間の禁酒 → 睡眠の質・むくみ改善
・1か月の節酒 → 血圧3〜5mmHg低下
・3か月の禁酒 → 肝酵素・中性脂肪の改善
「毎日飲む」よりも「休肝日を設ける」ことが、血圧・血管を守る第一歩です。
血圧コントロールのための飲酒ガイドライン
・飲酒は週に2日以上の休肝日を設ける
・飲むなら食事と一緒に(空腹時は急激に血中濃度が上昇)
・塩分の多いおつまみ(枝豆・漬物・焼き鳥のタレなど)を避ける
・飲酒後の測定値を「正常」と判断しない(一時的に低下している可能性)
・高血圧治療中の人は、医師・薬剤師と相談しながら節酒を検討
まとめ:お酒は「一時的に下がるが、長期的に上がる」
| 時期 | 血圧変化 | 主なメカニズム |
|---|---|---|
| 飲酒直後 | 一時的に下がる | 血管拡張、アセトアルデヒド作用 |
| 数時間後〜翌日 | 上がる | 交感神経活性化、脱水、体液貯留 |
| 長期的 | 恒常的に上がる | 腎機能変化、肥満、塩分摂取増加 |
ポイントまとめ
・飲酒直後は「血圧が下がる」のは一時的
・翌日以降は「血圧が上がる」方向に働く
・長期的には「慢性高血圧」のリスク
・降圧薬服用中は低血圧・失神の危険あり
・顔が赤くなる体質の人は特に注意
・節酒・休肝日を設けることで血圧は下がる
おわりに
「お酒を飲むと血圧が下がる」というのは、あくまで一時的な現象です。
長年の飲酒習慣は、確実に血圧を上昇させ、動脈硬化や脳卒中のリスクを高めます。
お酒を楽しむこと自体は悪いことではありません。
しかし、「血圧を守るための上手な付き合い方」を意識することが、健康寿命を延ばす第一歩です。
今日から「休肝日」を1日増やしてみる。
それだけでも、あなたの血管は確実に健康に近づきます。




