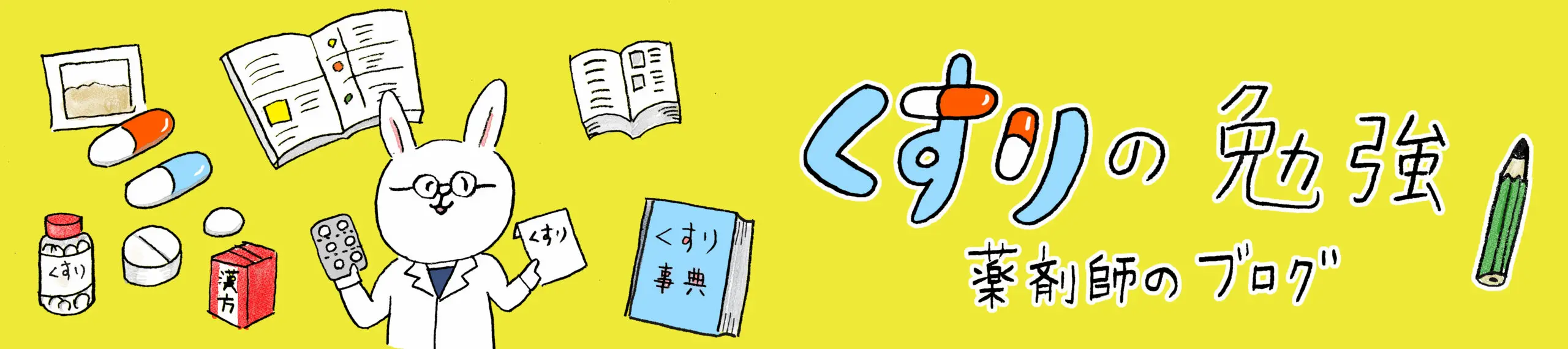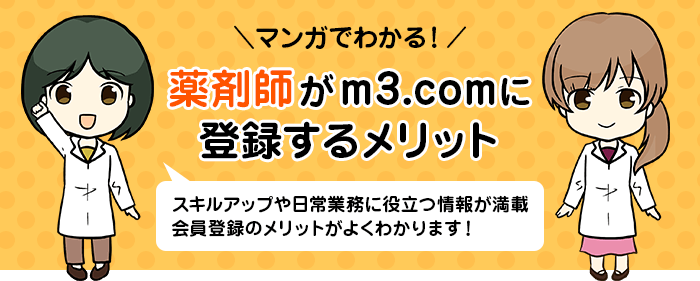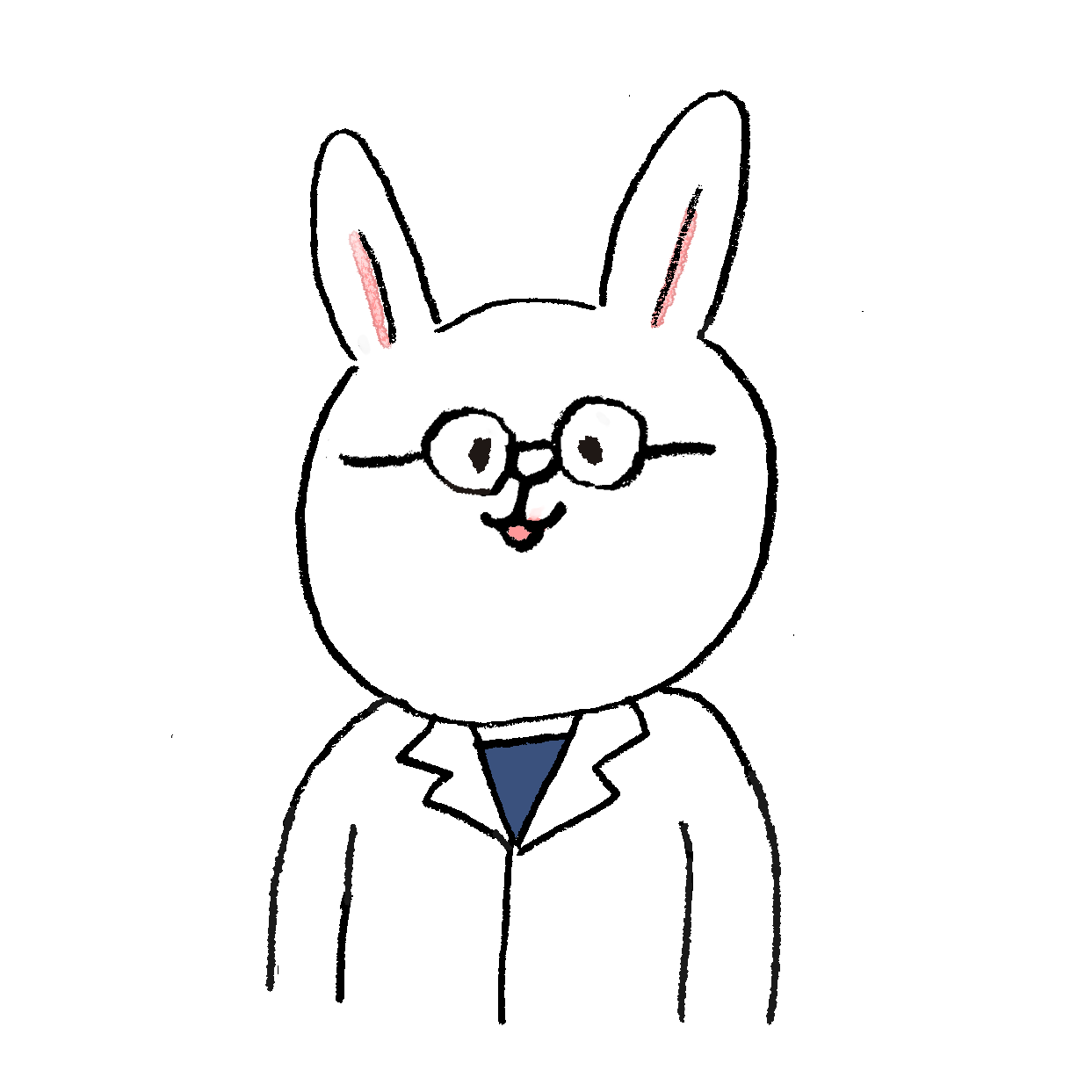記事
アスピリンの至適用量はどのくらい?
公開. 更新. 投稿者: 14,344 ビュー. カテゴリ:脳梗塞/血栓.この記事は約5分18秒で読めます.
アスピリンの抗血小板薬としての用量
低用量のアスピリンは抗血小板作用を有するので、心筋梗塞の再発予防などに使われます。
日本ではアスピリン81mgを含むバファリンと100mgを含むバイアスピリンが使われることが多いです。
バファリンの1日最大投与量は324mgで、バイアスピリンは300mgとなっています。
抗血栓作用を目的として使うアスピリンはどのくらいの量がベストなのでしょうか?
75mg/日未満では効果は低い。
75~160mg/日よりも160~325mg/日のほうが出血率が高い。
出血率が高いということは、よく効いているとも言える。急性期にはバイアスピリン1回2錠という用法も見かける。
長期的に飲まないといけない薬なので、出血や消化管障害などの副作用も考慮するとなるべく低用量で投与したいと考えると、やはり100mg程度がベストなのでしょう。
アスピリンの至適用量
核を持たない血小板ではCOX(シクロオキシゲナーゼ)の再合成は行われず、アスピリンによる抗血小板作用は不可逆的となる。そのため、抗血小板作用は血小板の寿命(7~10日)の間、持続する。
これに対して、血管内皮細胞ではCOXの再合成が行われるため、アスピリンによる血液凝固作用は可逆的となる。このCOXの再合成は、アスピリンの投与量が少ないほど早く回復することが知られている。
従って、抗血小板薬としてのアスピリンは低用量が適しているという。
「低用量アスピリン」の用量は、文献によって40~330mg/日と幅が広い。
アスピリンによるTXA2産生阻害はおよそ10mg/日以上で表れ、160mg/日でプラトーに達する。
一方、胃粘膜でのプロスタグランジン合成阻害による胃毒性は、およそ100mg/日以上で表れ始めるとの報告もある。
また、抗血小板薬として用いられるバファリン配合錠A81のインタビューフォームによると、アスピリンジレンマを回避するアスピリンの至適用量は40~80mgと報告されている。
さらに、TXA2の代謝物量を抑制し、かつPGI2代謝物量に影響の少ないアスピリンの至適用量は、個人差も考慮し40~320mg/日が適当であるとの記載がある。
これらを考慮した結果、国内では抗血小板薬として81mgまたは100mg錠が主に用いられている。
ただし至適用量に関しては、いまだ不明な点も多い。
高用量アスピリンで血液凝固する?
アスピリンは、アラキドン酸代謝の過程において、シクロオキシゲナーゼ(COX)をアセチル化し、COX活性を不可逆的に抑制する。
それにより、血小板では、血小板凝集作用を持つトロンボキサンA2(TXA2)の産生を抑制し、抗血小板作用を発揮する。
一方、血管内皮細胞では、血小板凝集抑制作用を持つプロスタグランジンI2(PGI2)の産生を抑制し、血液凝固作用を発揮する。
このように、アスピリンが相反する作用をもたらすことを、アスピリンジレンマと呼ぶ。
高用量のアスピリンによる血液凝固作用が、臨床的な影響を及ぼすかといえば、そうとは限らない。
抗血小板療法のランダム化比較試験のメタ解析の結果、アスピリンの高用量群(500~1500mg) 、中等量群(160~325mg) 、低用量群(75 ~150mg) の間で、脳卒中や心筋梗塞、血管死といった心血管イベントの低減効果に有意差はなかったことが報告されている。
この結果からは、500mg/日以上の高用量でも抗血小板作用は維持されることがうかがえる。
つまり、アスピリンの抗血小板作用は用量を増やすと消失するわけではなく、増強しなくなると考えるべきだろう。
バファリン配合錠A81が処方されている患者に、バファリン配合錠A330が頓服で処方された場合、「これでいいのか?」と思いがち、疑義照会したくなりますが、抗血小板作用が失われるわけではないので、いちいち疑義照会する必要もないということだろう。
アスピリンジレンマとは?
頭痛薬として使われることのあるアスピリンですが、現在は血液をサラサラにする目的で使われることが多いです。
このアスピリンですが、使う量が薬の効果に大きく影響します。
少ない量だと、血栓ができにくくなりますが、多い量だと逆に血栓ができやすくなってしまいます。
これをアスピリンジレンマといいます。
アスピリン・ジレンマとは、アスピリンに期待する抗血小板作用において、用量の多寡によって血小板凝集の抑制と促進という相反する作用が現れることをいいます。
アスピリンは、COXを阻害することで、血小板凝集促進および血管収縮作用を有するトロンボキサン(TXA2)の生成を抑制し抗血小板作用を示します。
また同時に血小板凝集抑制および血管拡張作用を有するプロスタサイクリン(PGI2)の生成も抑制します。
アスピリンはいわば、悪玉(TXA2)と善玉(PGI2)の両方を抑制するわけですが、少量では、TXA2の作用が抑制され、血栓はできにくくなり、大量の投与では、PGI2の作用が抑制され、血小板凝集が生じやすくなります。
ではなぜ、用量の違いによってこのようなアスピリンジレンマが現れるのでしょうか。
それは、TXA2とPGI2の産生細胞の違いが、最も大きな要因です。
TXA2は主に血小板において生成されますが、PGI2は血管内皮細胞において生成されます。
アスピリンは、血管内皮細胞のCOXよりも血小板のCOXに対してはるかに高い親和性をもつため、低用量では血小板におけるCOXの作用のみが阻害され、TXA2の生成が抑制されて、血小板凝集抑制効果を発現します。
しかし、高用量になると血管内皮細胞におけるCOXの作用も阻害されるため、PGI2の生成が抑制されて、血小板凝集促進作用が発現してくるのです。
また、核のない血小板では、アスピリンによって不可逆的に阻害されたCOXの作用が、その血小板の存在する限り代償されないという点も、アスピリンによる血小板凝集抑制作用の重要なポイントの1つです。
このため、アスピリンによる抗血小板作用は、アスピリンの投与後、血小板の寿命である7~10日間は持続します。
なお、抗血小板作用を期待したアスピリンの投与量は、メタ解析の結果からは75~150mg/日が適量として推奨されていますが、各種のガイドラインでは325mg/日が上限とされているものも多く、日本でも1日投与量として324mgまで承認されています。
COX1と血小板
アスピリンの抗血小板作用は、血小板のシクロオキシゲナーゼ1(COX-1)を阻害することによって、血小板凝集物質であり血管収縮物質であるトロンボキサンA2(TXA2)の産生を阻害することによって発揮される。
一方、血管内皮細胞のCOX-1も阻害し、強い血小板凝集抑制作用や血管拡張作用を持つプロスタサイクリン(PGI2)の産生を阻害する。
このことから、アスピリンが血管内皮細胞のCOX-1を阻害することは血栓を促進することになりかねない。
この相反する作用があることから、このことをアスピリン・ジレンマと言う。このアスピリン・ジレンマを解決する方法としては、アスピリンの少量投与(80〜300mg程度)法が用いられている。
これは、血小板のCOX-1は、血管内皮細胞のCOX-1に比べてアスピリンの感受性が高いことから少量でも十分TXA2の産生を抑制でき、かつ血管内皮細胞のPGI2の産生抑制は比較的軽度に抑えることができるためである。