記事
胃を全摘しているのに胃薬?PPIやH₂ブロッカーが処方される理由
公開. 更新. 投稿者: 12,688 ビュー. カテゴリ:消化性潰瘍/逆流性食道炎.この記事は約5分14秒で読めます.
目次
胃を全摘しているのに胃薬?
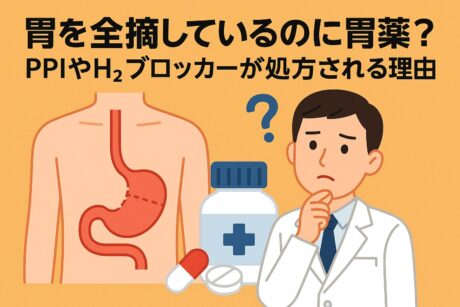
薬局で調剤していると、時々こういう処方に出会うことがあります。
「胃を全摘しているのに、PPI(プロトンポンプ阻害薬)やH₂ブロッカーが処方されている。」
たとえば、
「ランソプラゾールOD錠」や「ファモチジン錠」が、胃全摘術後の患者に長期処方されているケース。
「胃がないのに胃酸を抑える薬?」と違和感を覚える薬剤師も多いのではないでしょうか。
実際、服薬指導で「胃酸を抑える薬です」と説明してしまうと、患者から
「でも、私、胃ないんですよ」
とツッコまれることもしばしばです。
では、なぜ胃全摘後の患者に、胃酸分泌抑制薬が処方されるのでしょうか?
その意外と合理的な医学的理由を、消化管の構造変化と臨床的背景から詳しく勉強していきます。
胃全摘といっても「胃がゼロ」になるわけではない?
「胃全摘」というと、文字通り「胃をすべて取る」手術を想像しますが、実際には個人差があります。
① 幽門部・噴門部が一部残る場合がある
胃全摘術といっても、吻合の都合上、ごく一部の胃粘膜(特に噴門側)を残すことがあります。
残存粘膜に「壁細胞(胃酸を分泌する細胞)」が残っていれば、少量でも胃酸は分泌され続けます。
このわずかな酸でも、術後の吻合部や食道に炎症・潰瘍を引き起こす可能性があります。
② 十二指腸や空腸に「胃の化生」が起こることがある
術後の再建過程で、十二指腸や空腸に胃粘膜化生(胃のような上皮が再生する現象)が生じることがあります。
この異所性粘膜にも壁細胞が出現し、胃酸を分泌することが報告されています。
つまり「胃がないのに胃酸が出る」状態になることがあるのです。
したがって、「胃全摘後でも胃酸を抑える意味がある」という状況は珍しくありません。
吻合部は脆弱で潰瘍ができやすい
胃を切除して、食道や腸をつなぐ吻合部は、構造的にも血流的にも弱点になりやすい部位です。
この部分にできる潰瘍を「マージナル潰瘍(吻合部潰瘍)」と呼びます。
吻合部は、胃酸だけでなく胆汁や膵液などの刺激でも容易に障害されます。
この潰瘍の予防・治療に、PPIやH₂ブロッカーがしばしば用いられます。
・吻合部潰瘍の再発率を下げる効果がある
・痛みや出血、狭窄などの合併症を防ぐ目的で投与される
・特にNSAIDsやステロイドを併用している患者では必須に近い
H₂ブロッカーは「潰瘍抑制薬」としての役割を担っています。
逆流性食道炎の予防・治療
胃を全摘すると、食道の下端(下部食道括約筋)と胃の連続性が失われます。
これにより、食道への逆流を防ぐ“弁”の構造がなくなり、胆汁や膵液が食道へ逆流します。
これを「胆汁逆流性食道炎」と呼びます。
胃酸が原因ではないが、酸抑制薬が効くこともある
逆流の主成分は胃酸ではなく胆汁や膵液ですが、
PPIやH₂ブロッカーによって食道粘膜のpH環境が安定化し、症状が軽減することがあります。
一部報告では、PPI投与により胆汁逆流性食道炎の症状が改善した例もあり、
機序は完全には解明されていないものの、「抗酸薬による防御因子強化」が関与していると考えられています。
➡目的:食道粘膜保護・胆汁逆流の症状軽減
残胃・異所性胃粘膜の酸分泌抑制
手術の際、わずかでも胃粘膜が残っている場合には、そこから酸分泌が起こります。
さらに、食道や腸の粘膜に「胃粘膜化生」が生じると、その部位でも酸が産生されることがあります。
これらが吻合部や食道に潰瘍をつくるリスク因子になるため、
PPIやH₂ブロッカーで酸を抑えることに臨床的意義があります。
「幽門部や噴門部が残存している患者で壁細胞があれば、
胃酸が分泌されているので酸分泌抑制薬の使用に意味がある」
まさにその通りです。
胃酸がなくても「消化酵素のため」に意味がある
胃酸は食物を溶かすだけでなく、消化酵素の働きを最適化する役割もあります。
胃酸が失われると、上部腸管のpHがアルカリ性に傾き、膵酵素(リパーゼ、アミラーゼなど)の活性が低下します。
このため、消化酵素製剤(パンクレアチン、パンクレリパーゼなど)を併用することが多いのですが、
同時にPPIやH₂ブロッカーを投与して、腸内pHを安定化させることで酵素活性を保ちやすくする意図もあります。
➡目的:消化吸収補助・膵酵素の働きを支える
胆汁・膵液逆流による炎症に対して
胃全摘後の逆流性食道炎では、主因は「胃酸」ではなく胆汁・膵液です。
それにもかかわらず、PPIやH₂ブロッカーが処方されることがあります。
一見矛盾するようですが、
PPIには抗炎症作用・抗酸化作用などがあり、
胆汁逆流に伴う粘膜障害を軽減する報告があります。
また、膵液・胆汁の分泌を抑制する目的で「フオイパン(カモスタット)」が併用されることもあります。
胆汁逆流による強い胸やけには、フオイパン+PPIの併用が有効だったという報告も見られます。
「胃がないのに胃薬」という誤解
服薬指導時に「胃酸を抑える薬です」と説明してしまうと、患者は必ず疑問を持ちます。
このような場合には、次のように伝えるとよいでしょう。
「胃はありませんが、手術のあとにつないだ腸や食道が炎症を起こさないように、
あるいは潰瘍ができないようにお薬で保護しています。」
または、
「胃酸を抑える薬というより、消化管を守る薬というイメージです。」
この説明なら、患者さんも納得しやすくなります。
胃全摘後に起こりやすい消化管トラブル
合併症と対応薬
・逆流性食道炎:胆汁・膵液の逆流➡PPI、H₂ブロッカー、フオイパン
・吻合部潰瘍:胃酸・胆汁・局所虚血➡PPI、H₂ブロッカー
・ダンピング症候群:食後の急激な血糖変動➡食事指導・αGIなど
・消化吸収障害:酵素活性低下➡消化酵素製剤、PPI併用
・貧血:鉄・ビタミンB₁₂吸収不良➡補充療法
PPIとH₂ブロッカー、どちらを選ぶ?
・急性期・潰瘍予防にはPPIが主流(酸抑制が強く、長時間作用)
・長期維持・軽症例にはH₂ブロッカー(安全性が高い)
・胆汁逆流型では、フオイパン+PPI併用が検討されることもあります。
術後年数が経つにつれ、PPI → H₂ブロッカー → 制酸剤 へとステップダウンしていくケースもあります。
まとめ
処方理由
・残胃・異所性胃粘膜からの酸分泌:壁細胞が残れば酸が出るため抑制する
・吻合部潰瘍の予防:潰瘍ができやすい部位を守る
・胆汁逆流性食道炎の予防:胆汁・膵液逆流で起こる炎症を抑制
・酵素製剤との併用:腸内pHを安定化して酵素を守る
・NSAIDs併用時:消化管潰瘍の予防
「胃がないのに胃薬?」という疑問には、
「胃酸を抑える薬というより、消化管を保護する薬」
というのが正確な答えです。
胃全摘術後は、消化管の構造やpH環境が大きく変わり、
食道や吻合部が新たな“弱点”になります。
PPIやH₂ブロッカーは、その弱点を守るために欠かせない薬なのです。
そしてもう一つ、薬剤師として大切なのは、
患者が“なぜ自分にこの薬が出ているのか”を理解できるように説明すること。
「胃がないから関係ない薬」と誤解されないよう、
服薬指導の言葉選びにも注意が必要です。




