記事
逆流性食道炎にPPIを1日2回使うことがある?
公開. 更新. 投稿者: 9,096 ビュー. カテゴリ:消化性潰瘍/逆流性食道炎.この記事は約6分33秒で読めます.
目次
NAB(夜間胃酸分泌破綻)とPPI抵抗性GERD
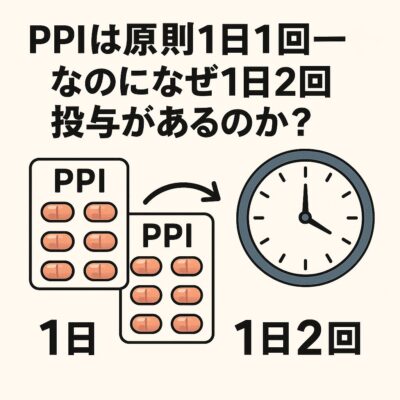
プロトンポンプ阻害薬(PPI:Proton Pump Inhibitor)は、逆流性食道炎や胃潰瘍など幅広い消化器疾患に使われている。
タケプロン(ランソプラゾール)、オメプラール(オメプラゾール)、パリエット(ラベプラゾール)など、どのPPIも 基本用法は「1日1回」である。
しかし、現場では時折、PPIが「1日2回」という処方に出会うことがある。
薬剤師としては「用法違反では?」と疑義照会したくなるところだ。
添付文書上、1日2回投与を正式に認めているのはラベプラゾール(パリエット)だけである。
それなのに、なぜ臨床ではPPIを1日2回に増量するのか?
この背景には、
・PPI抵抗性GERDの存在
・夜間胃酸分泌の破綻(NAB:Nocturnal Acid Breakthrough)
・PPIの薬理学的特性(作用時間・プロトンポンプ新生)
・壁細胞の胃酸分泌リズム
・H. pylori陰性例の増加
といった複数の因子が関係している。
「なぜPPIを1日2回投与するのか?」を、薬剤師が実務で判断できるレベルまで深く掘り下げてみる。
PPIの基本は「1日1回」だが、完全ではない理由
PPIは服用することで、吸収された後、血流に乗って胃の壁細胞に到達する。
そこで、分泌活性化されたプロトンポンプと結合し、その働きを不可逆的に阻害する。
▼ なぜ1日1回でよいのか?
・プロトンポンプ1個を阻害すると、回復には24時間以上かかる
・新しく合成されるプロトンポンプは1日20%程度
・つまり「古いポンプを止めれば1日持つ」
これが「1日1回でよい」とされている理由だ。
しかし、この仕組みには盲点がある。
PPI抵抗性GERDとは?
日本消化器学会ガイドラインでは次のように定義されている。
「標準量のPPIを8週間投与しても症状改善や内視鏡治癒が不十分な状態」
これが PPI抵抗性GERD であり、治療の難しさから実臨床でもしばしば問題となっている。
原因としては、
・食道運動異常
・非酸性逆流
・心因性要因
・胃酸分泌抑制の不十分さ
・NAB(夜間胃酸分泌破綻)
などがある。
NAB(Nocturnal Acid Breakthrough:夜間胃酸分泌破綻)とは?
NABとは:
PPI使用中にもかかわらず、夜間(特に22時〜翌2時)に胃内pHが4未満の状態が1時間以上続く現象
特に H. pylori 陰性者では NAB が多いことが報告されている。
NABが存在すると、
・夜間の胸焼け
・夜間咳(LPR:咽喉頭逆流症)
・食道炎の再発
・症状の難治化
などを引き起こしやすい。
PPIは昼間の分泌期には強く働くが、夜間のヒスタミンによる基礎分泌には弱い。
このため、PPIだけでは夜間酸を完全抑制できない。
なぜPPIを1日2回にするのか?
PPIは血中から消失するのが早く、
服用後10〜12時間で血中濃度はほぼゼロになる。
そして、プロトンポンプは1日に20%ずつ新生されるため、
朝の1回投与だけでは 夕方〜夜間に新生されたポンプが未阻害のまま残る。
これが「NAB」を引き起こす原因だ。
▼ PPIを1日2回にすると?
・血中濃度が1日2回ピークを持つ
・朝と夕の2回、プロトンポンプ活性化のタイミングを捉えられる
・新しく合成されたポンプも抑制できる
つまり 1日2回投与は、プロトンポンプの新生サイクルに対する合理的なアプローチ である。
パリエット(ラベプラゾール)だけが添付文書で「1日2回」を認めている理由
ラベプラゾール(パリエット)はPPIの中で以下の特徴がある。
・酸による活性化が最も速い
・壁細胞への到達性が良い
・代謝酵素(CYP2C19)の影響を受けにくい
そのため、1日2回投与に関する臨床試験が多く行われ、
添付文書にも次が明記されている。
● <治療期(最大8週間)>
10mg 1日1回
症状によって20mg 1日1回
効果不十分時:10mg or 20mg を1日2回(8週間まで)
● <維持療法>
10mg 1日1回
効果不十分時:10mg 1日2回
このように、ラベプラゾールだけはエビデンスに基づき正式に1日2回が認められている。
他のPPIにも医学的根拠はあるが、添付文書へ反映されたのはラベプラゾールのみである。
PPIを1日2回にする具体的な臨床シナリオ
● ① PPI抵抗性GERD
標準量でも改善しない患者に対して
朝+夕の2回投与が有効。
● ② NAB(Nocturnal Acid Breakthrough)
夜間にpHが4未満に落ちる患者では効果的。
・夜間の胸焼け
・夜間咳
・喉の違和感(LPR)
・夜間悪化型の逆流症状
が多い場合に考慮される。
● ③ H. pylori 陰性・萎縮なしの胃
胃酸分泌が強いため、NABが起こりやすい。
PPI 1日2回投与 vs PPI 2倍量(1日1回)の違い
PPI抵抗性GERDには
・1回量を2倍にする(例:20mg→40mg)
・1回量そのままで1日2回にする(例:10mg→10mg×2)
の2パターンがある。
臨床的には次のように使い分けられる。
● 用量2倍(1日1回)は?
・朝のピークは強くなる
・しかし夜間の酸抑制改善は不十分
→ NABには弱い
● 分割投与(1日2回)は?
・血中濃度が二峰性になる
・夜間のプロトンポンプ新生にも対応
→ NABに有効
多くの研究で
1日2回のほうが夜間酸の抑制効果が高い
ことが示されている。
PPI 1日2回投与の代替策
1日2回が難しい場合や、他の選択肢として以下がある。
● ① H2ブロッカーの就寝前追加
NABに最も直接的な効果。
ただし耐性が早く出る。
● ② P-CAB(タケキャブ)への切替
・24時間安定作用
・食事の影響なし
・反応が早い
・夜間酸も抑制しやすい
今や PPI 1日2回より強力と言われることも多い。
● ③ 生活習慣の改善
・就寝前の食事を避ける
・枕を高くする
・右側臥位を避ける
・飲酒・油ものを控える
薬剤師としての疑義照会ポイント
▼ 疑義照会「すべきでない」ケース
・ラベプラゾール(パリエット)で1日2回 → 添付文書上問題なし
・明らかにPPI抵抗性GERD症例
・夜間症状が強い、喉症状がある
・消化器専門医の処方
・HEENT症状(咽喉頭逆流症)が強い
▼ 疑義照会「すべき」ケース
・患者に喘息や重度肝障害がある
・他のPPI(タケプロン・オメプラールなど)の1日2回で理由が不明
・投与前に医師の指示が不十分
・胃潰瘍・十二指腸潰瘍治療での1日2回(普通は1日1回)
▼ 判断基準
「医学的妥当性があるかどうか」
=PPI抵抗性GERD or NAB を疑う状況であれば合理的
まとめ:PPIは原則1日1回だが、“1日2回”は明確に根拠がある
● 原則
・PPIは1日1回で十分
・添付文書で1日2回を認めているのはパリエットだけ
● しかし臨床では
・PPI抵抗性GERD
・NAB(夜間胃酸分泌破綻)
に対して 1日2回が合理的な治療戦略となる。
● 理由
・プロトンポンプは24時間で20%新生
・PPIは10〜12時間で血中から消失
・分割投与のほうが新生ポンプを阻害しやすい
・夜間酸を抑制しやすい
● 代替策
・H2ブロッカーを就寝前に追加
・P-CAB(タケキャブ)へ変更
・生活習慣改善
● そして最重要ポイント
「PPIが1日2回で出てきても、必ずしも誤りではない」
医学的にきちんとした根拠とガイドライン背景がある。
薬剤師としては固定観念にとらわれず、
処方意図を理解したうえで判断することが求められる。




