記事
疑義照会不要項目?疑義照会簡素化プロトコール
公開. 更新. 投稿者: 11,512 ビュー. カテゴリ:調剤/調剤過誤.この記事は約5分38秒で読めます.
目次
疑義照会はどこまで必要か?― 病院が公表する「不要項目」「事後FAX」の実態
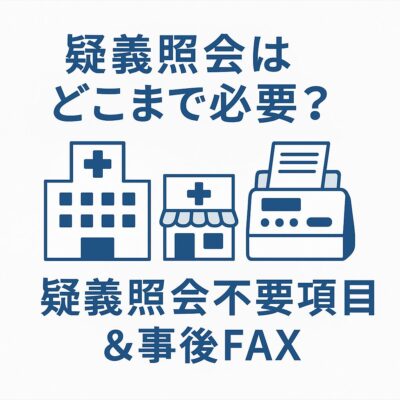
調剤薬局にとって「疑義照会」は、患者の安全を守るための重要な業務です。しかし、現場レベルでは次のような本音が交錯しています。
薬剤師側
「これ、確認する必要ある?」「また電話で時間が取られる…」
医師側
「毎回こんなことで電話しなくてもいいのに」「診療が止まる」
患者の安全のために行うべき“適正な疑義照会”と、医師・薬剤師双方の負担を減らすべき“過剰な疑義照会”との線引きは、長年の課題でした。
この問題に対する現実的な解決策として、最近増えているのが、
病院側が「疑義照会不要項目」や「事後FAXで良いもの」を公式に公表する仕組み
です。すでに地域でも採用され始め、薬局実務の効率化に大きな影響を与えています。
・疑義照会簡素化の背景
・実際に「不要」または「事後FAX」で良いとされている項目
・注意すべき例外
・薬剤師が取るべき対応
を勉強していきます。
なぜ「疑義照会不要」「事後FAX」が増えているのか?
■ 本来の疑義照会の目的
薬機法 第24条の規定により、疑義照会は法的義務です。
「処方内容に疑義がある場合、薬剤師は照会しなければならない」
しかし、この“疑義”は必ずしも“電話確認”を意味していません。
■ 過剰な疑義照会が医療の妨げになる
現場では、次のような負担が生じています。
| 影響 | 薬局側 | 医師側 |
|---|---|---|
| 時間 | 調剤が止まる | 診療が止まる |
| ヒューマンエラー | 電話情報の転記ミス | 患者対応中の中断 |
| 患者への影響 | 待ち時間延長 | 医師・薬局への不信感 |
■ 対応時間の不均衡
調剤薬局の疑義照会の多くは「指示変更で安心感を得たいだけ」の確認であり、医師にとっては優先順位が低く、むしろ負担に感じることがあります。
「不要」または「事後FAX」で良いとされる代表項目
近年、地域連携の一環として、病院側が「疑義照会の簡素化プロトコル」や「照会不要項目」を公表するケースが増えてきました。そこでは共通して、医師の診断・治療方針に影響しない範囲に限り、薬局側の判断で対応してよい項目が明示されています。
以下は、複数の病院(例:下志津病院、夢が丘総合病院など)が公開しているプロトコルをもとに、実際に“事後FAXでよい/疑義照会不要”とされている代表例です。
① 同一成分・同一規格の銘柄変更(先発⇄後発・メーカー変更)
例:
・アムロジピン錠5mg(A社)→ アムロジピン錠5mg(B社)
・グラクティブ錠50mg → ジャヌビア錠50mg(同成分)
ポイント
・医師は「成分(薬効)が同じであれば患者の治療に影響しない」と判断している。
・銘柄を指定していない処方は、薬局に選択を委ねているケースが多い。
ただし例外あり
・血中濃度依存性の高い薬(フェニトイン・テオフィリンなど)
→ 銘柄差による治療影響が大きいため照会必須。
・“銘柄指定不可” の明記がある処方
→ 医師の治療意図として尊重する必要あり。
② 同一成分・同一規格内の“軽微な剤形変更”
例:
・錠剤 → OD錠
・細粒 → 同規格の別メーカー細粒
ポイント
・患者の嚥下状態や服薬状況は薬局側の方が把握しやすいため、剤形変更が服薬支援であると解釈されている。
・用法・用量・成分が変わらない限り、治療結果には影響しない。
ただし例外あり
・徐放剤・腸溶剤・速放性に意図がある製剤
→ 剤形が作用・副作用に影響するため必ず照会。
③ 外用薬の単純な包装・規格変更(総量が変わらない場合)
例:
・クリーム 5g×2 → 10g×1
・アズノールうがい液 10mL×1 → 5mL×2
ポイント
・これは治療内容の変更ではなく“包装形態の調整”。
・患者の利便性や管理性を向上させるため、「事後報告(FAX)」で十分だとする病院が多い。
例外
・麻薬貼付剤(フェンタニル等)
→ 剤形・規格が治療方針と密接に関係するため照会必須。
④ 残薬調整に伴う日数短縮のみ
例:
28日分 → 患者「7日分余っている」→ 21日分のみ交付
・治療を変えるのではなく、“余っている分を引いて調整”するだけ
・過量投与の防止、薬の廃棄防止につながるため、照会不要または事後報告とする病院が多いです。
ポイント
・“余っている薬を減らす方向(短くする)」は、治療を変更しているのではなく、薬の重複や廃棄を防ぐ目的。
・そのため、日数を増やすことは許容されず、短縮のみ事後報告扱いとしている医療機関が多い。
注意喚起
・「日数延長」は治療に影響し、転売・過量服薬のリスクもあるため 絶対に薬局判断では行わない。
【総括】
これらに共通する考え方は、
“薬局が判断して良い領域” = 治療方針を変えない変更であること
治療薬の選択・量・期間は医師の診断に基づくべきであり、
薬局の判断領域は 患者の服薬支援と利便性の範囲 に限定されます。
薬局での実務運用:どうすれば安全か?
“プロトコルの範囲内で薬剤師の判断” を明確にする
・病院は「許可範囲」を公表
・薬局は「判断基準」を薬歴に残す
電話よりFAX/電子連携が主流になりつつある
・電話 → 情報が残らない、記載ミス
・FAX → 記録が残る、安全性向上
・電子連携 → 今後の標準化が進む
“判断の根拠” を必ず文書化する
・「病院の公開プロトコルに基づき変更」
→ 調剤監査が強化されても説明可能
地域連携が重要になる
病院と薬局で判断基準が異なると患者リスクが上がるため、
地域薬剤師会が中心となり、共通運用を整備することが理想
医師側にもメリットがある
■ 医師の仕事が減る
・ルーチン変更の電話がなくなる
・診療が止まらない
■ 患者説明がシンプルに
「剤形やメーカー変更は薬局で対応してくれます」
→ 患者は薬局をより信頼するようになる。
■ 地域連携の質が向上する
「薬局に任せられる領域」が明確になる
→ チーム医療としての役割分担になる
まとめ:疑義照会は“なくす”のではなく“適正化”すべき
誤った方向性➡正しい方向性
・疑義照会を減らす➡不要な疑義照会を減らす
・電話しない➡事後FAX・文書化で安全性を担保
・薬剤師に丸投げ➡プロトコルに基づく判断
疑義照会は、患者の安全を守るもの
しかし “全てを電話でする必要はない”
文書化されたプロトコルと、薬局の専門性に基づき、
適正化していくことがこれからの薬剤師の役割




