記事
吐き気止めは食前に飲まないとダメ?ナウゼリンやプリンペランの用法
公開. 更新. 投稿者: 31,025 ビュー. カテゴリ:めまい/難聴/嘔吐.この記事は約4分0秒で読めます.
目次
吐き気止めは食前に飲まないとダメ?―制吐薬の正しい使い方
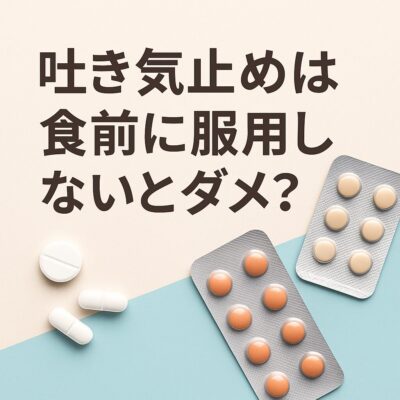
吐き気や嘔吐は、消化器疾患、薬の副作用、乗り物酔い、感染症、がん化学療法など、さまざまな状況で出現する症状です。その不快感や生活への影響は大きく、日常生活の質(QOL)を著しく低下させます。こうした症状に対して処方されるのが「制吐薬(吐き気止め)」です。
ところで、制吐薬は添付文書を見ると「食前投与」と書かれていることが多いのですが、実際には「食前じゃないと効かないの?」「吐き気があるのに食事できないときはどうするの?」といった疑問が患者からも現場の薬剤師からも出てきます。プリンペラン(メトクロプラミド)、ナウゼリン(ドンペリドン)、ガナトン(イトプリド)といった代表的な薬を例に、制吐薬を食前に飲む理由や例外的なケース、実務上のポイントについて勉強したいと思います。
制吐薬の作用機序と「食前投与」の意味
プリンペラン(メトクロプラミド)
プリンペランはドパミンD₂受容体拮抗作用を持ち、中枢(化学受容器引金帯:CTZ)に作用して制吐効果を示すほか、末梢では消化管のアセチルコリン遊離を促進し、胃の蠕動を高め、胃内容物を早く小腸に送る作用があります。
添付文書では以下のように記載されています。
「メトクロプラミドとして、通常成人1日7.67~23.04mg(塩酸メトクロプラミドとして10~30mg、2~6錠)を2~3回に分割し、食前に経口投与する。」
つまり、消化管に食物が入ってから動き始めるよりも、あらかじめ運動を高めておくほうが効果的という考え方です。
ナウゼリン(ドンペリドン)
ナウゼリンもドパミンD₂受容体を遮断する薬で、消化管運動促進作用と制吐作用を併せ持っています。
「通常、ドンペリドンとして1回10mgを1日3回食前に経口投与する。」
こちらもプリンペランと同様、食物摂取前に飲むことで、食事後の胃もたれや吐き気を予防する狙いがあります。
ガナトン(イトプリド)
ガナトンはドパミン受容体拮抗作用に加え、アセチルコリン分解酵素阻害作用を併せ持ち、より強い胃運動改善効果を示す薬です。
「通常、成人にはイトプリド塩酸塩として1日150mgを3回に分けて食前に経口投与する。」
このように、いずれも基本的に「食前服用」が標準的な用法として明記されています。
なぜ食前に服用する必要があるのか?
制吐薬の「食前投与」には大きく2つの理由があります。
作用点とのタイミング合わせ
胃の中に食物が入ると胃の蠕動運動が必要になります。その直前に薬を飲んでおくことで、薬の作用がちょうど消化のタイミングに合致し、胃内容物の停滞を防げるのです。
薬の吸収効率
吐き気止めの多くは空腹時に吸収されやすく、食後に飲むと吸収が遅れたり作用発現が遅れることがあります。吐き気は待ったなしの症状ですから、速やかに効果を出すためにも食前服用が合理的です。
実際の臨床現場での疑問
「食事ができないときはどうするの?」
「吐き気が強くて食事がとれないのに、食前服用と言われても飲めない」というケースは珍しくありません。この場合はどう考えればいいのでしょうか。
実際には、「食前でなければ絶対に効かない」というわけではありません。食事の有無にかかわらず、薬は血中に入って作用するため、吐き気があるなら服用して問題はありません。ただし、本来期待される「食後の消化を助ける」というメリットは弱くなる可能性があります。
「頓服で使えないの?」
添付文書では「食前1日3回」と定められていますが、現場では「頓服でお願いします」と依頼されることもあります。吐き気があるときにだけ飲むという使い方です。これは理論的にも十分効果がありますし、「必要なときだけ飲む」というシンプルな指示のほうが患者にとって理解しやすい場合もあります。
疑義照会と薬剤師の悩み
薬剤師が処方箋を受け取ったとき、「あれ、この患者さん、食事がとれないのに制吐薬が食前で出ている…」という場面があります。こうした場合に医師へ疑義照会すべきかどうか、判断に迷うことがあります。
・常識的に考えれば食事できない患者にも必要な薬
・しかし用法は厳密には『食前』
現場では、「食前にこだわらず、吐き気があるときに服用してよい」と説明するケースもあります。実際に、抗がん剤治療の患者や、食欲不振の高齢者に対しても柔軟に運用されています。
添付文書と現実のギャップ
医薬品の添付文書は、治験で得られたデータに基づいた標準的な投与方法を示しています。しかし、現実の臨床現場では、患者の状態に合わせた使い方が必要です。
・添付文書:食前服用が基本。
・実臨床:食事ができない患者では頓服的に使用することもある。
このギャップを埋めるのが薬剤師の役割であり、患者の理解を助ける服薬指導が求められます。
まとめ:吐き気止めは「食前」が基本だが柔軟に
・プリンペラン、ナウゼリン、ガナトンといった代表的な制吐薬は、添付文書上「食前投与」が基本。
・食前に服用する理由は「消化管運動とタイミングを合わせる」「吸収を早める」ため。
・ただし、食事がとれないときでも服用してよい。頓服としての使用も現場では行われている。
・薬剤師は添付文書と臨床実態の間をつなぎ、患者に「いつ飲んでもいいけど、食事前がベスト」と説明するのが望ましい。
吐き気止めを「食前でなければ効かない」と思い込みすぎると、患者が薬を飲み逃してしまうリスクがあります。大切なのは、「まずは吐き気を抑えることが優先」という視点を持ちつつ、食前服用の意義も正しく伝えることです。




