記事
年をとると飲み込みにくい?液体の誤嚥とむせの仕組み
公開. 更新. 投稿者: 3,559 ビュー. カテゴリ:結核/肺炎.この記事は約3分29秒で読めます.
目次
嚥下機能と誤嚥リスク
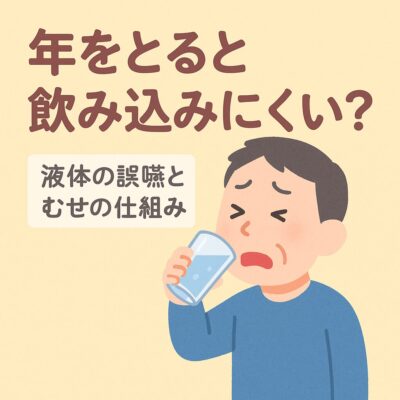
薬剤師が日常業務の中で直面する高齢者や在宅患者における大きな課題の一つが「嚥下障害」と「誤嚥性肺炎」です。錠剤やカプセルの服薬困難だけでなく、液体製剤や経腸栄養剤の取り扱いも、嚥下機能と密接に関わります。本稿では、ヒト特有の嚥下の仕組みと液体嚥下の特殊性を踏まえ、薬剤師が知っておくべき実践的な知識を整理します。
ヒトと他の哺乳類の嚥下の違い
ヒトの喉頭は哺乳類の中でも低い位置に存在します。この構造が「発声」を可能にする一方で、「嚥下」にはリスクをもたらしています。
・咀嚼嚥下:固形物を喉頭蓋谷に送り込み、嚥下反射で飲み込む方式。ヒトも他の哺乳類も共通して利用。
・液体嚥下:水分のように流動性が高いものを飲み込むため、口腔内に一旦貯留してから一気に嚥下。ヒト特有の様式。
水分は咽頭へ先行して流れ込みやすく、喉頭閉鎖が遅れると誤嚥の危険が高まります。つまり、液体嚥下はそもそも「難易度の高い嚥下様式」なのです。
液体嚥下のメカニズム
液体嚥下では瞬時に複雑な動きが連携して行われます。
・軟口蓋が挙上 → 鼻腔への流入を防ぐ
・舌が食塊(液体)を押し込む → 舌骨・喉頭挙上、食道入口部が開大
・喉頭蓋の反転、披裂内転、声門閉鎖 → 気道を遮断(呼吸は一時停止)
・咽頭収縮 → 食塊を食道へ送り込む
わずか1秒前後の間にこれだけの動作が連動して行われるため、加齢や疾患による機能低下があると誤嚥リスクが急増します。
高齢者に嚥下障害が多い理由
(1) 加齢変化
・喉頭挙上筋群の筋力低下 → 喉頭の位置が低下し閉鎖が遅れる
・嚥下反射の遅延・低下
・咳反射の減弱
これらが重なると、誤嚥性肺炎につながります。
(2) 神経疾患の影響
・脳卒中後:嚥下中枢や経路の障害による球麻痺・仮性球麻痺
・パーキンソン病:ドパミン低下による不顕性誤嚥
・認知症:食塊形成の障害、注意力低下
薬剤師は「むせやすい」「飲み込みに時間がかかる」「食後に咳が多い」などの訴えに敏感である必要があります。
不顕性誤嚥と夜間のリスク
寝ている間に唾液や分泌物を気付かないうちに誤嚥する「不顕性誤嚥」は、特に高齢者で多発します。
・唾液1mg中に10億以上の細菌 → 肺内に入り誤嚥性肺炎の原因に
・睡眠中はサブスタンスP合成が減少 → 咳反射・嚥下反射がさらに弱まる
薬剤師としては「むせない=安全」ではなく、むせない誤嚥こそ危険と理解しておくことが重要です。
唾液と口渇がもたらす嚥下困難
唾液は単なる潤滑剤ではなく、以下の重要な役割を担っています。
・食塊形成を助ける
・食道蠕動促進
・胃酸の中和(重炭酸イオン)
・粘膜修復因子による食道防御
薬剤性口渇(抗コリン薬、抗ヒスタミン薬、抗うつ薬など)は嚥下困難やGERD悪化の原因となり、服薬支援に直結します。
半固形化・とろみ付けによる対応
液体は最も誤嚥しやすいため、臨床現場では「とろみ付け」「半固形化」が実践されています。
・経腸栄養剤の半固形化 → 逆流防止、誤嚥リスク低下、介護負担軽減
・とろみ剤の種類:デンプン系、グアーガム系、ゼラチン・寒天系など
・投与前の準備・細菌汚染リスクへの配慮
薬剤師は患者背景に応じて、「水分にとろみをつけるべきか」「少量分割投与がよいか」などを具体的に助言できます。
簡便な嚥下機能チェック
臨床現場で参考になる発声法によるチェック。
「らりるれろ」:舌の可動性を確認 → 食塊形成の目安
「ぱぴぷぺぽ」:口唇閉鎖力を確認 → 食べこぼしの有無の目安
簡単に確認できるスクリーニング方法として、服薬指導や在宅訪問時に有用です。
薬剤師ができる実践的支援
服薬剤形の選択
・錠剤 → OD錠・ゼリー包材・カプセル開封可否の検討
・液剤 → とろみ付け、ゼリー化による服薬補助
・経腸栄養 → 半固形化の適否を医師・看護師と連携
誤嚥リスクの観察
・むせやすさ、咳の有無、飲水時の表情変化
・食後の痰や咳 → 誤嚥サインの可能性
口渇副作用への注意
・薬歴管理で抗コリン薬・抗ヒスタミン薬などを把握
・代替薬の提案、服薬タイミングの調整
多職種連携
・看護師やST(言語聴覚士)との情報共有
・嚥下造影・嚥下内視鏡検査の必要性を医師に提案
まとめ
ヒトは液体嚥下という「特殊かつリスクの高い」嚥下様式を持ち、加齢や疾患によって容易に誤嚥が起こります。薬剤師は「服薬支援の専門家」として、剤形選択や服薬補助食品の提案だけでなく、嚥下障害のサインを捉えて医療チームに橋渡しする役割を担います。
嚥下障害は「薬の服用可否」だけでなく、「栄養状態」「生活の質」に直結します。薬剤師が嚥下の仕組みを理解し、臨床現場で活かすことで、誤嚥性肺炎の予防や服薬アドヒアランスの向上につながるでしょう。




