記事
精神科ではなぜ多剤併用が多いのか?
公開. 更新. 投稿者: 7,432 ビュー. カテゴリ:統合失調症.この記事は約9分33秒で読めます.
目次
精神科の多剤併用療法
病院が配置しなければならない医師の最低人員数は一般病床で入院患者16人当たり医師1人、精神病床で48人当り医師1人。
看護師の最低人員数は一般病床で入院患者3人当たり看護師1人、精神病床で4人当り看護師1人となっています。
少ない人員で治療に当たるため、症状の重い入院患者には治療よりも鎮静作用を重視した処方が行われがちというのが、精神科で多剤併用療法の多い理由の一つです。
家庭でもそうでしょう。
躁鬱病の患者の家族なら、とにかく躁状態は避けたい、過鎮静でもいいから大人しくしていて欲しいと思います。
なぜ多剤併用になってしまったのか
統合失調症に対して薬らしい薬がなかった時代に治療として行われていたのは、症状が自然に消褪し安定するまで刺激の少ない病院内に留めておくということでした。
実際には、半永久的に病院内にいることを意味していたと思います。
それが、第一世代の抗精神病薬が出現したことにより、初めて治療らしい治療へと大きな変革が起こりました。
しかしながら、当時はどの抗精神病薬も症状に対して何らかの効果はあるものの、その薬理特性が鋭敏さに欠けるため、次々に新しい抗精神病薬が発売されました。
新しい薬が登場するたびに、基本的にはドーパミン遮断の微妙な違いにすぎないにもかかわらず、効能として、「今度の薬は特に妄想に効果が高い」「鎮静は少ないが攻撃性に効く」という異なった特徴が謳われたため、陽性症状の改善にとらわれすぎて、あれもこれもと何種類もの抗精神病薬を組み合わせて使う多剤併用療法へと移行していったのです。
一度投与してしまうと、今度はどの薬剤を抜けばよいのか迷いますし、少し前の精神科の治療では、どちらかといえば大人しく過鎮静気味で、あまり変化がない状態を「治療がうまくいっている」と考えていたこともあり、投薬される薬剤の数は増える一方となりました。
さらに悪いことに、各薬剤が組み合わされた多剤併用の状態でどのような効果が得られるかという薬理学的検証ができなかった時代なので、そのことについて議論さえされず、多剤併用療法が漫然と治療スタンダードとなってしまったのです。
現在の抗精神病薬治療の考え方からすれば、呆れられるような話であり、なんとも幼稚で滑稽で褒められる話ではないのですが、陽性症状を標的とする治療原理が標準であった時代に、当時の精神科医が、患者の症状をいかに改善できるかを懸命に考えて処方した結果が、多剤併用療法であったともいえます。
多剤併用療法はただの過量処方でしかない
薬効に不足を感じて薬剤を追加してきたという多剤併用の背景を考えると、1つずつの薬剤は必ず許容用量の目一杯まで使用されてきたはずです。
それが複数種類処方されるのですから、極端な表現をすれば、多剤併用はただのオーバードーズに過ぎません。
最新の研究では、統合失調症の治療において、単剤での治療と多剤併用での治療とでは、長期予後に差が出ることがわかっています。
至適用量を超えた抗精神病薬は脳に対する細胞毒性を示すと考えられるのです。
さらに、同じ単剤治療で適用量であった場合は、第一世代抗精神病薬と第二世代抗精神病薬とで再燃率に差が出ることが報告されています。
多剤併用が多いのはなぜか
わが国では精神分裂病の患者さんに対する薬物療法が多剤併用大量療法となっていることが多く、諸外国と比較しても特異な現象であるといわれています。
一方で、抗精神病薬や抗うつ薬、気分安定薬などを併用することは諸外国でも行われていますが、薬理作用の全く異なる薬剤の併用はpolypharmacyとは呼ばずcombinationと呼ばれ、わが国における多剤併用とは異なっています。
多剤併用が行われる背景と問題点としては、次のようなものが考えられます。
背景
①単剤では無効あるいは効果が不十分なので併用する
②1剤の投与量を増加させるよりも少量の2剤を併用するほうが有効で、副作用が少ないという仮説
③多剤併用にすれば効果がある確率が高いのではないかという考え方
④薬物相互作用、併用による弊害の基本的知識の欠如
⑤約束処方や習慣となっている処方の影響
⑥移行性抗精神病薬(スルピリドなど)の出現
⑦医療経済的理由
問題点
①有効な薬物が確定できず、至適用量が決められない
②副作用出現時の原因薬物の特定ができない
③少量ずつの併用ではどの薬物も有効血中濃度に達しない
④併用する薬物によっては効果が減弱する
⑤薬物相互作用による有害作用の出現
⑥調剤ミスの誘発
⑦服薬コンプライアンスの低下
わが国における多剤併用療法の原因として、明治時代以前の漢方薬の処方や、名処方集などによる「さじ加減」を信奉する考え、結核治療におけるSM、INAH、PASの3者併用療法、白血病に対するVMP療法などの影響、精神科における医師の処方能力が多剤処方により示されるとの無意識な思い込み、医薬分業の不徹底などがあげられています。
抗精神病薬の併用
精神分裂病患者に対する維持療法に至るまでの処方変更についての調査では、鎮静作用を要する場合に新たな鎮静系(フェノチアジン系)薬剤の追加の頻度が高く、その理由として1剤大量使用による副作用の回避が目的であると推定されたと報告されています。
抗精神病薬による鎮静作用は、抗精神病作用と逆相関しており、用量力価と正の相関を示すのは、ドパミン受容体遮断作用の強度であり、その他の受容体遮断作用の強度とは相関しないことを考えると、抗精神病薬の分裂病に対する有効性とは直接関係がないと考えられています。
むしろ、鎮静作用の強い抗精神病薬を併用することによる相互作用により有害事象が引き起こされることを考慮すべきです。
抗精神病薬を数種類併用していると、全体としてどの程度の量の薬剤を使用しているのか判断がつきにくいことが多く、等価換算表で処方をチェックしてみると、個々の薬剤の投与量は少なくても、総量ではかなりの量に上っていることがわかります。
抗精神病薬において、脳内レセプターに対する作用機序が異なるもの同士の併用は必ずしも非合理的とはいえず、sedative(鎮静催眠性)の薬剤とincitive(鋭利的、抗幻覚性)の薬剤を分裂病の入院初期に併用することは有効な場合もあるとしており、睡眠障害を有する症例においてハロペリドールとクロルプロマジンの併用がハロペリドール単剤よりも優れているという報告もあります。
抗精神病薬と抗パーキンソン薬の併用
向精神薬の長期投与と副作用の関係で重要なのは、抗精神病薬と抗パ薬との併用です。
特に力価の高い定型抗精神病薬(ハロペリドール、フルフェナジンなど)治療では錐体外路症状が生じることが多く、その予防と改善を目的として抗パ薬が併用されています。
わが国におけるさまざまな調査から抗パ薬の1日当たりの平均投与剤数は1~2剤で、処方率は80%以上となっています。
精神分裂病の薬物療法では、薬効よりもアカシジアやディスフォリアなどの副作用が投与初期に出てしまうと、治療の継続が困難となってしまうという懸念から、予防的投与が多くみられます。
しかし、抗精神病薬を長期にわたって投与されている患者さんでは、抗パ薬の併用は大部分で不要であるというのが世界的にみた定説です。
抗精神病薬とベンゾジアゼピン系薬の併用
精神分裂病をはじめうつ病、神経症などでは不眠・不安・緊張などの症状はよくみられます。
このような症状に対して、現在はベンゾジアゼピン系の薬剤が多く併用されています。
これらの薬剤は、精神分裂病患者ではかえって精神症状を悪化させてしまうという指摘もあり、ベンゾジアゼピン系薬剤の使用は必要最小限に留めるべきで、症状の改善がみられたら徐々に減量、中止を試みるべきです。
非定型抗精神病薬の併用
現在、非定型抗精神病薬は化学構造と薬理作用の違いにより、三環構造をもつclozapine-likeな薬剤とその他のrisperidone-likeな薬剤に分類することができます。
しかし、非定型抗精神病薬は、脳内の各種レセプターに対する作用や親和性がそれぞれの薬剤の特徴となっていることから、併用によりその特徴が失われてしまう可能性が考えられます。
また、投与量が多くなると、セトロニン受容体に対する親和性をドパミン受容体に対する親和性が上回ってしまい、非定型抗精神病薬の作用特性を失ってしまいます。
さらに、これらの薬剤にはそれぞれ特徴的な副作用(オランザピンでは体重増加、リスペリドンではプロラクチンの上昇など)があります。
したがって、これらの薬剤の併用により副作用の増加を招くことも考えられることから、十分なデータを元に臨床応用を検討するべきであると考えられます。
特定抗精神病薬治療管理加算
統合失調症の入院患者に対し、計画的な医学管理をしながらリスペリドンなどの非定型抗精神病薬による治療を行った場合、「特定抗精神病薬治療管理加算」(非定型抗精神病薬加算)という点数を算定できます。
この点数が次回の診療報酬改定で、使用する抗精神病薬が2種類以下の場合15点、2種類より多い場合には現行の10点という点数になるらしい。
その差5点(50円)ですが、どうなんでしょう。多剤併用は改善されるのでしょうか。
精神科で散薬処方が多いのはなぜか
色々な理由がありますが、高齢者が多いため錠剤が飲み込みにくい場合があることや、現在のように全自動で錠剤を一包化できなかった昔に、多剤を一包化しやすかったことのなごりなどがあると思います。
また、あまりよいことではありませんが、薬の変更などに過敏に反応する患者に対し、本人に気が付かれないように処方を変更するために散薬を選択する場合もあります。
最近では散薬の処方は減少してきています。
多剤併用がインスリン抵抗性を誘発
ドパミンD2受容体を同じ程度に遮断しようとした場合に、それを単剤ではなく多剤で行ったほうが、インスリン抵抗性を起こしやすいと考えられるデータがあります。
抗精神病薬の「量」ではなく、「剤数」が増えると内科系の薬の数も増加しているとのこと。
糖尿病の予防という意味からも、多剤併用は避けるべきだといえます。
抗精神病薬はなるべく単剤で使用するのが望ましいですが、幻覚・妄想を抑える作用の強い高力価抗精神病薬と催眠鎮静作用の強い低力価抗精神病薬は、その作用の違いから併用される頻度は高いといえます。
よって、もし抗精神病薬を併用する際にも高力価と低力価の2種類までに留めておきます。
また、近年登場した非定型抗精神病薬は併用におけるデータが不足していることもあり、非定型抗精神病薬同士での併用の可否については、今後明らかになってくると思われますが、非定型抗精神病薬であっても薬物相互作用が、併用によってどの薬が効いているかわかりづらいといった問題は変わりません。
基本的に単剤での使用が推奨されている薬であることから、併用のメリットが明らかになるまではなるべく単剤に近い形での使用が望ましいでしょう。
抗精神病薬の大量療法は有効か?
クロルプロマジンやハロペリドールなどの、定型抗精神病薬による大量療法は古くは有用とされましたが、以降の研究からその有効性は否定されています。
非定型抗精神病薬に関しては、相対的に錐体外路症状は少ないですが、リスペリドンなど一部の薬剤に関しては用量が増加するとそのリスクは増えるとされる一方、リスクのさらに少ないオランザピンやクエチアピンでは、症例によっては保険用量よりも高用量が有用ではないかと示唆されてもいます。
市販前試験における用量設定に問題がある場合もあり、一部の薬剤に関しては比較的高用量からスタートするのが有用であるとの報告もありますが、原則は低用量から開始し、副作用が問題とならない(保険適応の)範囲において、相応の治療効果が得られるまで徐々に増薬していくことであると考えられます。
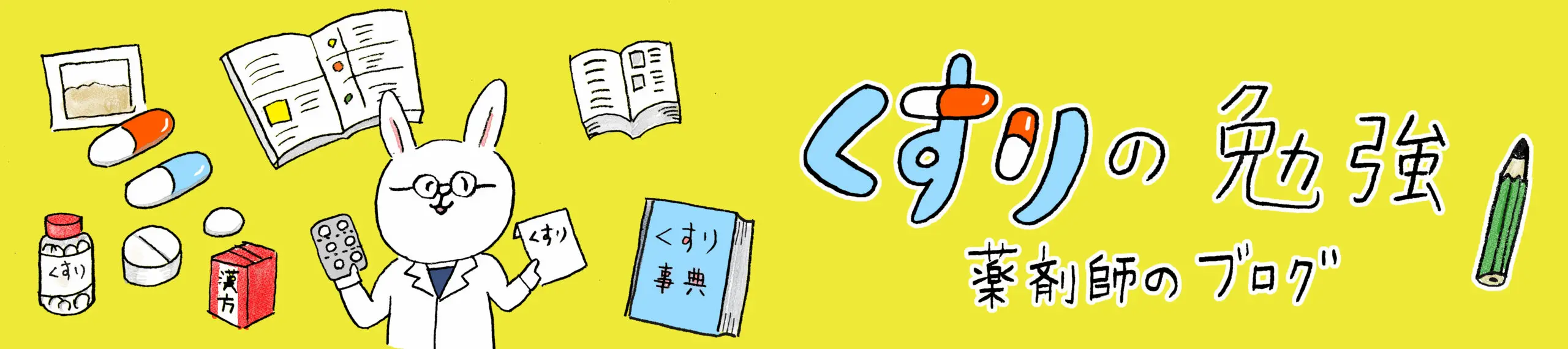

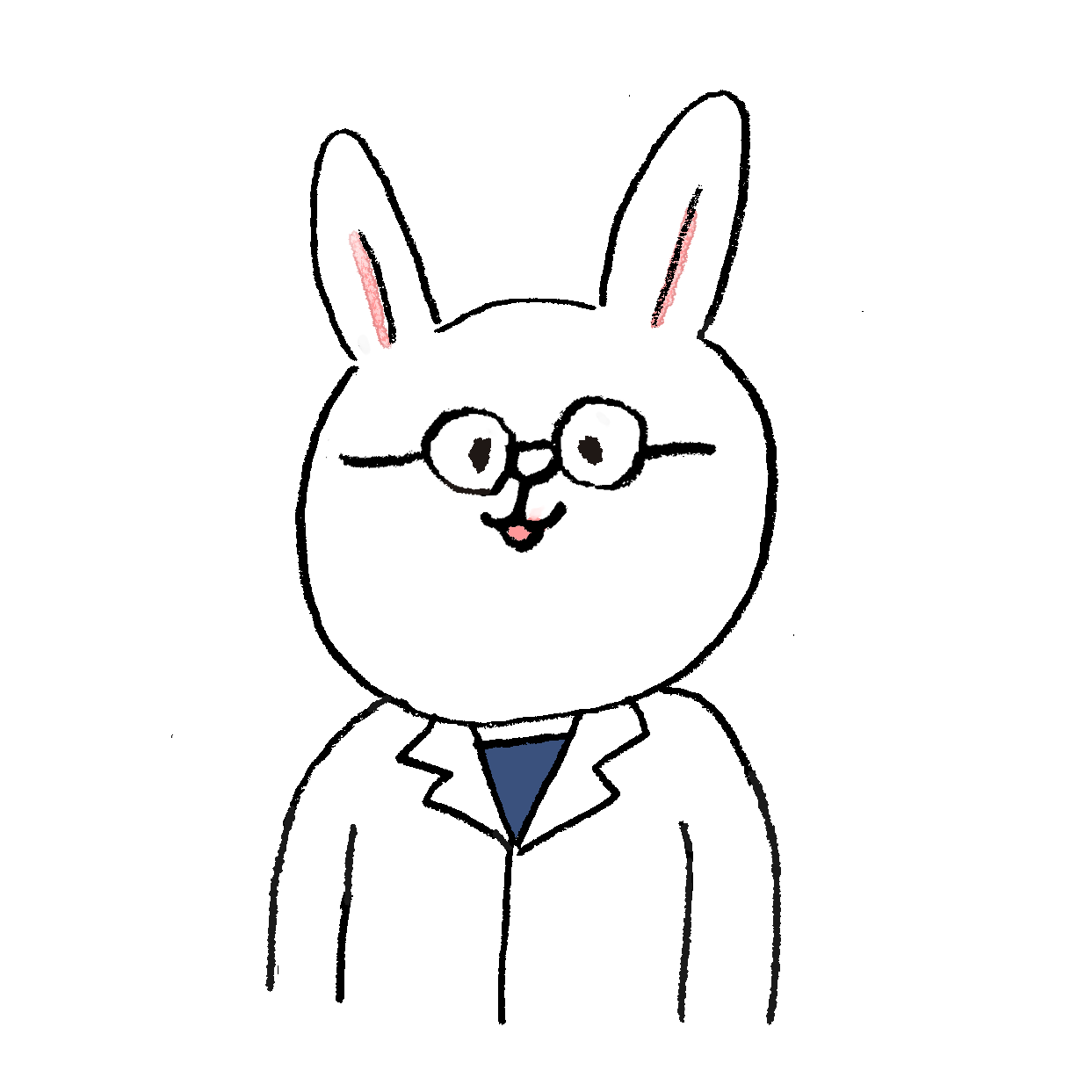

4 件のコメント
不眠が強くロヒプのールにレボトミンを使用して来ましたがどのような薬の配合が良かったのでしょうか。
医者の薬の調合はどのようにしてチックしていけばよいのでしょうか。
医者の薬の調合はどのようにしてチックしていけばよいのでしょうか。
回答頂きたく存じます
コメントありがとうございます。
薬品名がわからない、ということでしょうか?
医師から何の薬か知らされずに服用しているということでしょうか?
院内処方だとそういうこともあり得るのかも。
よくわかりませんが、薬品名がわからないのであれば、医師に直接聞くのがよろしいと思います。