記事
薬害とは何か?過去の薬害と再評価された薬たち
公開. 更新. 投稿者: 3,832 ビュー. カテゴリ:副作用/薬害.この記事は約4分24秒で読めます.
目次
薬害とは
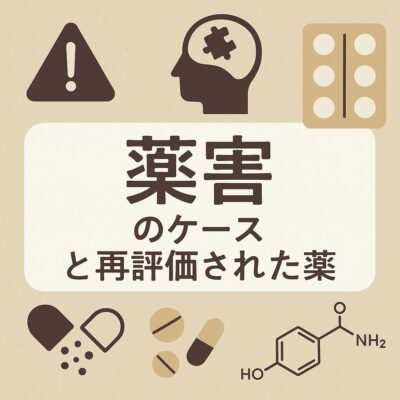
「薬害」とは、医薬品の使用により発生した健康被害のうち、適切な情報提供や規制、監視体制が欠如していたことに起因する公衆衛生上の問題を指します。薬の副作用とは異なり、防げたはずの被害が社会的な教訓として記録される点が特徴です。
日本においては、1970年のスモン事件をはじめ、サリドマイド事件、HIV薬害事件、C型肝炎薬害事件など、社会に大きな影響を与えた薬害が数多く存在します。
薬害の全体像に触れた上で、作用機序的に特徴的な薬害事例として、以下の4つの薬剤を掘り下げます。
・サリドマイド
・ソリブジン
・キノホルム
・クロロキン
いずれも、かつて薬害の主役となった薬剤でありながら、現代医療において再評価されたものも含まれます。
薬害の構造:なぜ防げなかったのか
薬害が発生する背景には、以下のような複合的な要因があります。
・科学的知識の不足:発売当時は薬の作用や副作用に関する理解が不十分だった例が多い
・規制の甘さ:承認審査や市販後調査が不十分であったケース
・情報の不透明性:副作用報告が隠されたり、公開が遅れた例
・社会的要請:患者や医師の強いニーズによって過剰な使用が促された場合も
薬害を「個別の失敗」としてではなく、医療制度全体の課題として捉えることが再発防止には不可欠です。
サリドマイド ― 血管新生を止めた薬
薬害の背景
サリドマイドは1950年代にドイツで開発された睡眠薬・鎮静薬で、日本でも「イソミン」「プロバンM」といった商品名で販売されていました。主に妊婦のつわりを抑える目的で使用されていましたが、服用した妊婦から手足の短い子ども(アザラシ肢症)が多数誕生し、世界的な薬害事件となりました。
作用機序と再評価
当初は安全とされていたサリドマイドですが、後に血管新生阻害作用(anti-angiogenesis)を持つことが判明。これは胎児の四肢形成期において新しい血管が形成される過程を阻害することで奇形を引き起こすというものです。
さらに、近年ではサリドマイドがセレブロン(CRBN)というタンパク質に結合し、ユビキチン化によるタンパク質分解を促すことで、多発性骨髄腫における抗腫瘍作用を示すことがわかり、2008年に「サレド」として再承認されました。厳格な管理下で、いまも使われている薬です。
ソリブジン ― 相互作用の恐怖
薬害の背景
ソリブジン(S-1-(2-ブチニル)-5-ブロモ-ウラシル)は1980年代に「帯状疱疹の特効薬」として開発された抗ウイルス薬ですが、抗がん剤との相互作用で死亡事故が相次ぎ、発売からわずか数ヶ月で回収されました。
作用機序と相互作用
ソリブジン自体は軽度の抗ウイルス活性を持ちますが、腸内で代謝されてブロモビニルウラシル(BVU)となり、これがジヒドロピリミジンデヒドロゲナーゼ(DPD)という酵素を阻害します。
DPDは、フルオロウラシル(5-FU)系抗がん剤の代謝に必要な酵素であるため、これを阻害すると5-FUの代謝が著しく低下し、血中濃度が致死的に上昇します。
そのため、ソリブジンを服用中または直後に抗がん剤(TS-1、UFT、5-FUなど)を投与すると、骨髄抑制や消化管障害により死亡する可能性が極めて高いのです。
この事例は、代謝酵素を介した薬物相互作用の危険性を明確に示したものとして、現在でも薬剤師国家試験や医療安全教育で頻繁に取り上げられています。
キノホルム ― 整腸剤が引き起こした神経障害
薬害の背景
「キノホルム(clioquinol)」はかつて整腸剤として「エンテロヴィオフォーム」「チバビン」などの商品名で市販されていました。1960年代、日本でこの薬を服用した人々に手足のしびれや麻痺、視力障害を伴う神経障害が多数報告され、「スモン(SMON)病:亜急性脊髄視神経症」という病名が社会問題化。約1万人以上が被害を受けたとされます。
作用機序の再評価
キノホルムは金属キレート作用を持ち、腸内環境の整備に効果があると考えられていましたが、その過剰摂取または蓄積によって神経毒性を発揮するとされています。
近年、アルツハイマー病に対して「アミロイドβと金属イオンの結合を阻害する作用」に期待が寄せられ、キノホルム誘導体(PBT-2)が一時期開発されました。しかし臨床試験での有効性が示されず、またスモンの記憶も根強く、現在では治療薬としての採用はありません。
クロロキン ― 再評価された抗マラリア薬
薬害の背景
クロロキンは、かつてマラリア治療薬として広く使われていた薬剤です。しかし、長期使用により網膜症や角膜障害が問題視され、「クロロキン網膜症」という視覚障害の薬害が発生しました。特に日本では、自己免疫疾患に対しても広く使用されていた背景があり、長期処方が原因となるケースが多発しました。
再評価と現代医療での利用
クロロキンはオートファジー抑制作用や抗ウイルス活性、免疫調整作用があることから、近年ではSLE(全身性エリテマトーデス)や皮膚エリテマトーデスの治療薬(プラケニル)として使われています。
またCOVID-19流行初期には抗ウイルス作用が注目され、ヒドロキシクロロキンの臨床試験も行われましたが、効果は否定され、重篤な心毒性も問題となり、最終的には使用推奨されなくなりました。
薬害と再評価:失敗の中から見つかる可能性
これらの事例はすべて、一度は社会的に失敗とみなされた薬剤が、その本質的な作用機序を理解することで再評価された例でもあります。
| 薬剤 | 当初の用途 | 薬害 | 再評価後の用途 |
|---|---|---|---|
| サリドマイド | 鎮静・睡眠薬 | 催奇形性 | 多発性骨髄腫(サレド) |
| ソリブジン | 抗ウイルス薬 | 5-FUとの相互作用 | 使用中止 |
| キノホルム | 整腸剤 | 神経障害(スモン) | 開発中止(アルツハイマー治療薬の研究終了) |
| クロロキン | 抗マラリア薬 | 網膜症 | 自己免疫疾患治療薬(プラケニル) |
おわりに:薬害を繰り返さないために
薬害を防ぐためには、単に「薬を怖がる」ことではなく、正確な知識・適切な使用・情報の共有が必要です。薬剤師としては、以下の視点を常に意識する必要があります。
・「相互作用」「長期使用時の蓄積毒性」などの機序的な副作用への理解
・患者への丁寧な情報提供と同意
・市販薬や健康食品との併用への注意
・薬歴や医薬品リスク管理(RMP)の活用
薬は「毒にも薬にもなる」存在であることを忘れず、その本質を理解することこそが薬害を防ぎ、未来の医療をより良くする第一歩です。




