記事
ワルファリンと緑黄色野菜の誤解を招く服薬指導
公開. 更新. 投稿者: 704 ビュー. カテゴリ:脳梗塞/血栓.この記事は約3分43秒で読めます.
目次
ワルファリンと緑黄色野菜
「ワルファリンを服用中の患者さんには、ビタミンKを含む食品を避けてください」
このフレーズは服薬指導の現場でよく耳にします。特に「納豆禁止」は薬剤師や患者の間でも有名です。
しかし、「緑黄色野菜は食べてはいけない」という説明をしてしまうと、患者は野菜を極端に制限し、栄養バランスを崩してしまうことがあります。実際には、「避ける」ではなく「食生活を一定に保つ」ことが重要です。
ワルファリンとビタミンK ― 基本のおさらい
・ワルファリンは ビタミンK依存性凝固因子(II, VII, IX, X) の産生を抑制することで抗凝固作用を発揮。
・ビタミンKを多く含む食品を摂取すると、ワルファリンの効果が弱まり、血栓リスクが高まる。
・代表例:納豆、クロレラ、青汁(特にケール)、緑黄色野菜(ほうれん草、小松菜、ブロッコリーなど)。
ポイントは 「摂取量の変動がPT-INRを不安定にする」 ことであり、「食べてはいけない」わけではない。
患者像
・70代男性、心房細動でワルファリン服用中。
・健康志向が強く、毎日野菜ジュースを飲んでいる。
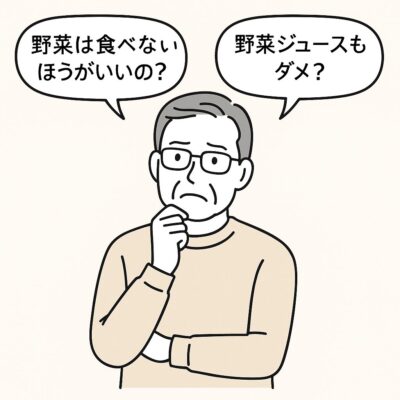
「野菜は食べないほうがいいんですか?」
「緑黄色野菜はビタミンKが多いので控えてください。」
その後、患者は真面目に指示を守り、ほうれん草や小松菜を避けるように。
→ 野菜不足により便秘や栄養不良を起こし、生活の質が低下。
→ 家族からも「食事制限が厳しすぎる」と不満の声。
必要以上の制限を伝えたことで、患者の生活が不健康になった。
「食べすぎなければ大丈夫ですよ」
その後、患者は「野菜は特に制限しなくてもいい」と受け取り、青汁を毎日飲み始めた。
→ PT-INRが大きく変動し、出血リスクが上昇。
誤解を解かず、うやむやにしたために患者が自己判断で危険な行動を取った。
バランスの取れた服薬指導とは?
誤解を避けるための服薬指導の工夫は以下の通りです。
「禁止」ではなく「一定に」
NG:「緑黄色野菜は食べないでください」
OK:「毎日同じくらいの量を食べるようにしてください」
大切なのは「摂取量の安定」であり、ゼロにする必要はない。
食事例を具体的に
「小鉢1つのほうれん草おひたしを毎日食べるのはOK」
「今日は食べないけど、明日はたっぷり、のように量を変えると薬の効き目が不安定になります」
禁止食品は明確に
「納豆・青汁・クロレラ」は明確にNG。
理由:ビタミンK含有量が突出して多く、少量でもINRを乱す。
安心感を添える
「普段の食生活を急に変えなければ大丈夫です」
「野菜を食べること自体は健康に良いので、バランスよく続けてください」
実際の声かけ例(シミュレーション)
患者:「野菜は食べないほうがいいんですか?」
薬剤師:「いいえ、野菜は健康に大切です。食べないと逆に体に悪いですよ。」
薬剤師:「大事なのは“量を安定させる”ことです。毎日同じくらい食べる分には問題ありません。ただし、納豆や青汁のようにビタミンKがすごく多い食品は避けてください。」
患者:「なるほど、食べちゃいけないんじゃなくて、量を変えないのが大事なんですね。」
薬剤師:「その通りです。今までと同じ食事を続けてもらえれば大丈夫です。」
まとめ
・ワルファリンと緑黄色野菜の関係は「禁止」ではなく「一定」。
・誤解を招く服薬指導は、患者の生活の質を下げたり、服薬中止に繋がる危険がある。
・納豆・青汁・クロレラなど「明確に避ける食品」と「量を安定させれば問題ない食品」を区別して伝えることが重要。
・薬剤師は「伝える義務」と「患者に続けてもらう意義」のバランスを常に意識する必要がある。
服薬指導は「患者に誤解させないこと」がゴールではなく、「納得して続けてもらうこと」 が最も大切です。




