記事
前立腺癌の待機療法とは?すぐに治療しなくていい?
公開. 更新. 投稿者: 2,389 ビュー. カテゴリ:癌/抗癌剤.この記事は約5分19秒で読めます.
目次
前立腺がんの待機療法とは?
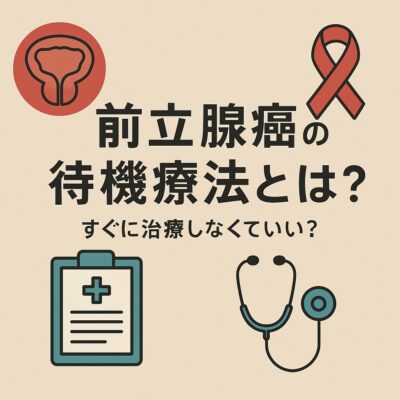
前立腺がんは、男性特有のがんの中でも罹患率が非常に高い疾患です。特に高齢の男性では、他の臓器に転移するまでに長い年月がかかる場合が多く、診断されても治療を急がず、経過観察を選ぶケースが増えています。
前立腺がんの「待機療法(アクティブサーベイランス)」を中心に、その背景、治療の選択肢、最新の薬物療法などを勉強します。
前立腺がんとは?
前立腺がんは、男性の膀胱の下にある「前立腺」という臓器に発生する悪性腫瘍です。日本では高齢化の影響もあり、患者数は年々増加しています。厚生労働省の統計によると、男性のがんの中で罹患数は上位に位置しています。
特徴的なのは、がん全体の中でも進行が極めて遅いものが多いことです。
実際、70歳以上の男性を亡くなった後に解剖すると、2〜3割、報告によっては5割以上に小さな前立腺がんが見つかるといわれています。しかし、これらの大半は症状を出さず、他の病気で亡くなるまで問題にならないことも少なくありません。
前立腺がんの進行と分類
前立腺がんはすべてが同じではありません。進行度・悪性度・広がりにより治療方針が変わります。
PSA値
PSA(前立腺特異抗原)という血液検査が、前立腺がんのスクリーニングや経過観察で中心的な役割を果たします。高値の場合、がんの存在が疑われます。
グリソンスコア
針生検で採取した組織を顕微鏡で観察し、がんの悪性度を示す評価スコアです。
・6点以下:低リスク
・7点:中間リスク
・8〜10点:高リスク
低リスクの場合、進行はきわめて遅いことが多いです。
待機療法(アクティブサーベイランス)とは
進行が遅いがんに対しては、診断後ただちに手術や放射線治療を行わず、計画的に定期検査をしながら経過を観察する方針が選択肢となります。
これが「アクティブサーベイランス(Active Surveillance)」、いわゆる待機療法です。
背景
かつて前立腺がんは「見つかれば治療すべき」と考えられていました。
しかし欧州を中心に、低リスクのがんでは治療を急がなくても死亡率は上がらないという研究が多数発表され、エビデンスが蓄積されました。
2011年、米国の総合癌センターネットワーク(NCCN)はガイドラインで、
・PSA値が低い
・グリソンスコアが低い
・腫瘍の大きさが限定的
・余命が十分長い
これらの条件を満たす場合、待機療法を推奨する方針を打ち出しました。
待機療法の利点と注意点
メリット
・手術や放射線治療による副作用を回避できる
・生活の質(QOL)を維持しやすい
・治療費用が抑えられる
前立腺がんの治療では、排尿障害、性機能障害(勃起不全)、尿失禁などが起こりやすいことが知られています。進行が遅いがんを無理に治療してこれらを抱えるより、経過観察を優先するほうが理にかなうケースも多いのです。
注意点
・経過観察のための定期検査(PSA、MRI、生検)が不可欠
・がんが進行してきたら治療への切り替えが必要
・心理的負担(「がんが体内にある」不安)
待機療法の適応
待機療法は「すべての前立腺がん」に適応されるわけではありません。
以下の条件を満たす場合に選択されます。
・PSA値が10ng/mL以下
・グリソンスコア6点以下
・臓器に限局(ステージT1c、T2a程度)
・腫瘍の占める割合が小さい
・定期フォローアップに通院可能
これらを満たさない場合(中リスク以上)では、治療を優先するほうが望ましいとされています。
「早期でも治療しなくても死亡率に差はない」という研究
有名なのが、米ミネソタ大学などが行ったPIVOT試験です。
早期前立腺がん患者を「手術群」と「経過観察群」に分け、長期的に追跡した結果、全体の死亡率に有意差は認められなかったというものです。
読売新聞やニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシンでも取り上げられ、この研究は待機療法の有効性を裏付ける重要な根拠の一つになりました。
ただし、これは「低リスクの早期がん」が対象であり、全てのケースに当てはまるわけではありません。
前立腺肥大症との関係
前立腺がんと混同しやすいのが「前立腺肥大症」です。
・前立腺肥大症は良性疾患で、排尿障害の原因になります。
・50歳代男性の約40〜50%に認められ、80歳以上では80%以上が発症します。
・PSA値も上昇するため、がんとの鑑別が重要です。
前立腺肥大症だけであれば命に関わることはほとんどなく、薬物治療や手術で対応可能です。
前立腺がんの薬物療法
前立腺がんはホルモン依存性のがんです。
男性ホルモン(アンドロゲン)ががんの増殖を促すため、ホルモン療法が中心となります。
ホルモン療法の種類
●LH-RHアゴニスト
・リュープロレリン(リュープリン)
・ゴセレリン(ゾラデックス)
下垂体から性腺刺激ホルモンを抑制し、精巣でのテストステロン分泌を止めます。
●LH-RHアンタゴニスト
・デガレリクス(ゴナックス)
アゴニストと異なり、投与初期に一過性のテストステロン上昇(フレアアップ)が起こらず、急速に効果が現れます。
●抗アンドロゲン薬
・フルタミド(オダイン)
・ビカルタミド(カソデックス)
・酢酸クロルマジノン(プロスタール)
・エンザルタミド(イクスタンジ)
テストステロンが細胞の受容体に結合するのを阻害します。
●CYP17阻害薬
・アビラテロン(ザイティガ)
副腎でのアンドロゲン合成も阻害します。副作用としてコルチゾール低下があるため、ステロイド併用が必須です。
去勢抵抗性前立腺がん(CRPC)
ホルモン療法を数年続けると、やがて去勢抵抗性前立腺がん(CRPC)と呼ばれる段階に進行します。この状態ではPSAが再上昇し、ホルモン療法が効かなくなります。
この場合は次の治療が検討されます。
・エンザルタミド(新規アンドロゲン受容体拮抗薬)
・アビラテロン(アンドロゲン合成阻害薬)
・ドセタキセル(タキサン系抗がん剤)
・カバジタキセル(新規タキサン系抗がん剤)
これらの薬剤は延命効果がありますが、副作用も強いため、患者の全身状態や希望を踏まえた選択が大切です。
経過観察と治療のバランス
前立腺がんを診断されたとき、最初に感じるのは「がん=すぐに治療しなければ死ぬ」という強い恐怖心です。しかし実際には、
・高齢の低リスクがんは進行がきわめて遅い
・早期治療と経過観察で死亡率に差がないケースもある
というデータが蓄積されています。
一方で、全てのがんが無害ではなく、若い患者や高リスクがんでは早期治療が不可欠です。
治療をしない選択は「何もしない」ことではなく、「定期的にしっかり見守ること」です。これを理解し、納得できるまで主治医と相談することがとても大切です。
まとめ
前立腺がんは、男性が高齢になるほど発生頻度が上がる「ありふれたがん」であり、進行が非常にゆっくりなことが多い疾患です。
そのため、近年では「待機療法」が標準治療の一つとして確立されてきました。
・PSAやグリソンスコアでリスクを正確に評価する
・リスクが低ければ治療を急がず、経過観察を選ぶ
・定期検査で進行を見逃さない
・高リスクがんでは積極的治療を行う
「癌=すぐ治療」と決めつけず、ライフスタイルや年齢、価値観に応じた最適な治療選択をしていくことが、これからの前立腺がん診療の大切な考え方です。





2 件のコメント
80歳の男性です。PSA4.1、生検の結果16検体中4検体が高リスク群グリソンスコア9に該当する「前立腺がんで悪質なもの」と宣告され、MRI検査と骨シンチ検査を行い、その結果治療方針を決めるとのお話でした。
生検後の血尿が1カ月程続き精神的負担からやっと開放された結果、今度は、多分放射線治療(外照射法)となることを示唆されています。
挙げられている副作用を考えますと、高齢でもあり老い先を考慮しても治療リスクを背負っていくのは選択し難いのですが、もし適切なご意見を賜れれば幸甚です。よろしくお願いします。
2013.1.16
コメントありがとうございます。
私のような若造が、このような重要な判断にアドバイスをするというのも、恐れ多いのですが。
もし自分がそのような診断をされたなら、と考えますと、手術はやはり避けたい。
しかし、放射線治療であれば、侵襲も少ないので、やってもいいかな、と思います。
放射線治療の副作用は比較的軽微なものでしょうし。
放射線治療もしない、という選択をしたとしても、定期的に通院することにはなると思いますし。
専門的な知識もない若造の意見で、何の参考にもならないかも知れませんが、少しでもお役に立てれば。