記事
COPD患者にβ遮断薬は禁忌じゃない?
公開. 更新. 投稿者: 5,620 ビュー. カテゴリ:喘息/COPD/喫煙.この記事は約5分5秒で読めます.
目次
COPDと心不全におけるβ遮断薬の使い方
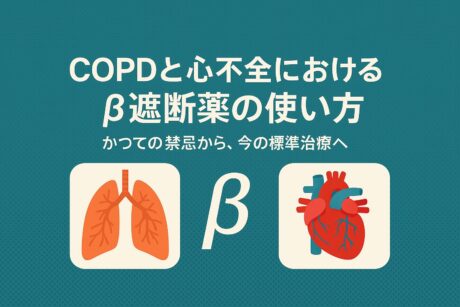
慢性閉塞性肺疾患(COPD)は、喫煙などを主な原因とする進行性の呼吸器疾患で、慢性的な咳嗽や痰、労作時呼吸困難を特徴とします。一方、心不全もまた息切れや呼吸困難を呈するため、両者は症状が類似し、かつしばしば同時に発症・進行します。
かつて、COPD患者にはβ遮断薬(βブロッカー)の投与は禁忌に近い扱いでした。これは、β2受容体を遮断することで気管支収縮が起こり、呼吸苦が増悪するリスクが懸念されていたからです。しかし、近年はβ遮断薬が心不全治療の第一選択薬として位置づけられ、COPDとの併存例でも安全かつ有効に使えるというエビデンスが蓄積されてきました。
COPDと心不全におけるβ遮断薬使用の変遷と、現在の臨床的知見を勉強します。
COPDと心不全の合併の背景
COPDと心不全は、共通のリスク因子を多く抱えています。
・喫煙:COPD発症の最大の原因であり、同時に冠動脈疾患や心筋梗塞、心不全の主要な危険因子。
・加齢:いずれも高齢者に多い。
・慢性炎症:全身性の炎症が動脈硬化・心血管障害を進展させる。
・低酸素血症・肺高血圧:COPDによる低酸素は右心負荷を増加させ、右心不全を合併しやすい。
欧米の疫学調査では、COPD患者の約30%が心不全を合併するとされ、両者の併存は予後を著しく悪化させることがわかっています。
β遮断薬はなぜ禁忌と考えられていたのか
β遮断薬は交感神経β受容体を遮断しますが、β受容体には主に以下の2種類があります。
・β1受容体:心臓に多く分布し、心拍数増加や収縮力亢進を担う。
・β2受容体:気管支平滑筋や末梢血管に多く、気管支拡張・血管拡張を担う。
非選択性β遮断薬(プロプラノロールなど)はβ1・β2を両方抑制するため、気管支収縮を誘発する恐れがあります。過去には、この作用によりCOPDや喘息患者に投与すると急性増悪を引き起こすと考えられ、教科書にも「原則禁忌」と記載されていました。
特に気管支喘息(気道可逆性の高い閉塞性障害)では、わずかなβ2遮断でも致命的な発作を誘発するため、現在でもβ遮断薬は原則禁忌です。
COPDに対する考え方の変化
しかし、近年の研究では、COPD患者においてもβ遮断薬が意外に安全に使用できる可能性が示されてきました。いくつかの要因が考えられます。
気管支喘息ほど強い気道可逆性がない
COPDは主に末梢気道の慢性閉塞であり、β2受容体刺激による気道可逆性は喘息ほど顕著ではありません。つまり、気管支収縮のリスクは限定的です。
β1選択性薬の普及
カルベジロールなど非選択性β遮断薬を除き、メトプロロールやビソプロロール、ネビボロールは高いβ1選択性をもちます。これらはβ2への影響が少なく、COPD患者にも比較的安全です。
慢性心不全の予後改善効果の大きさ
慢性心不全においてβ遮断薬は死亡率を20~35%減少させる唯一の薬剤群の一つです。この有用性がCOPDの潜在的リスクを上回ると評価されるようになりました。
β遮断薬使用の安全性を示すエビデンス
代表的な研究をいくつか紹介します。
絶対禁忌ではないとするメタ解析
2011年のBMJ誌に報告されたメタ解析(Salpeterら)では、COPD患者のβ遮断薬使用は肺機能の有意な低下を認めず、COPD増悪リスクも増加しないことが示されました。
死亡率低下の報告
複数の観察研究で、心不全や虚血性心疾患をもつCOPD患者にβ遮断薬を投与した場合、全死亡率・心血管死亡率・COPD増悪入院がむしろ減少する傾向が認められています。
β1選択性β遮断薬の有用性
特にビソプロロール・メトプロロールなどβ1選択性の薬は、気管支収縮の副作用が少ないとされています。欧州心臓病学会(ESC)や米国心臓病学会(AHA)のガイドラインでも、COPDにβ遮断薬を投与する際はこれらを選択することが推奨されています。
実臨床での投与判断
COPD患者にβ遮断薬を使う場合、次のポイントを考慮します。
疾患の重症度
中等度以下のCOPD(FEV1 >50%)では投与が比較的安全。重症COPDでは呼吸機能への影響に注意しつつ、必要に応じて段階的に増量します。
薬剤選択
・ビソプロロール
・メトプロロール徐放剤
・ネビボロール
など、β1選択性の高い薬剤を選ぶ。
気管支拡張薬の併用
COPD治療ではLABA(長時間作用型β2刺激薬)、LAMA(長時間作用型抗コリン薬)の吸入治療が標準です。β遮断薬併用下でもLABAは有効かつ安全に使用可能とされています。
開始用量と漸増
心不全治療の原則に従い、極低用量から開始し、患者の状態を確認しながら徐々に増量する。
喘息との鑑別
喘息併存が疑われる場合は、β遮断薬は避けるか、慎重に検討する。
COPDと心不全の両面からのアプローチ
COPD患者が息切れを訴えると、呼吸器疾患だけが注目されがちですが、実際には心不全が顕在化していることが少なくありません。心不全に適切にβ遮断薬を導入することで、心拍数制御や心筋リモデリング抑制が得られ、長期予後が改善します。逆にβ遮断薬を恐れて使用をためらうことで心不全の進行を許すのは、患者利益を損なう結果になります。
欧州のガイドラインでは、COPD併存心不全でもβ遮断薬が標準治療であることが強調されています。むしろ積極的に導入し、慎重に経過をみながら最適用量に増量するアプローチが望ましいとされています。
COPD治療中のβ遮断薬の位置づけ
2023年現在のエビデンスでは、COPD単独患者に心血管リスクが高い場合でもβ遮断薬投与は一定の有用性が示唆されています。ただしCOPD増悪リスクとのバランスや心拍数低下のデメリットは個別に評価が必要です。
・心不全を合併する場合:β遮断薬は明確に推奨。
・冠動脈疾患や心筋梗塞後:二次予防としてβ遮断薬推奨。
・高血圧単独:他薬剤で代替可能なら、無理に使用しなくても良い。
β遮断薬がもたらすCOPDへの副次的メリット
興味深いことに、いくつかの研究でCOPD患者におけるβ遮断薬の以下の効果が報告されています。
・肺高血圧の進行抑制
・不整脈の発症抑制
・急性冠症候群リスク低減
・安静時交感神経過活動の緩和
COPDは慢性低酸素による交感神経活性化が顕著で、このことが心血管イベントや予後不良に関連するため、β遮断薬が間接的に有益となる可能性も指摘されています。
まとめ
かつて「呼吸器疾患には禁忌」と考えられてきたβ遮断薬ですが、近年はCOPDにおいても心不全や虚血性心疾患の治療薬として安全性・有効性が確認され、ガイドラインでも使用が推奨される時代になりました。
もちろん、投与に際しては疾患の重症度、呼吸機能、気道可逆性、併用薬、心機能などを総合的に評価する必要があります。β1選択性薬を低用量から慎重に導入することで、COPD患者でも心血管イベント予防に貢献できる可能性が高いといえます。
今後もさらなる知見が集積され、より安全で効果的な治療戦略が確立されることが期待されます。




