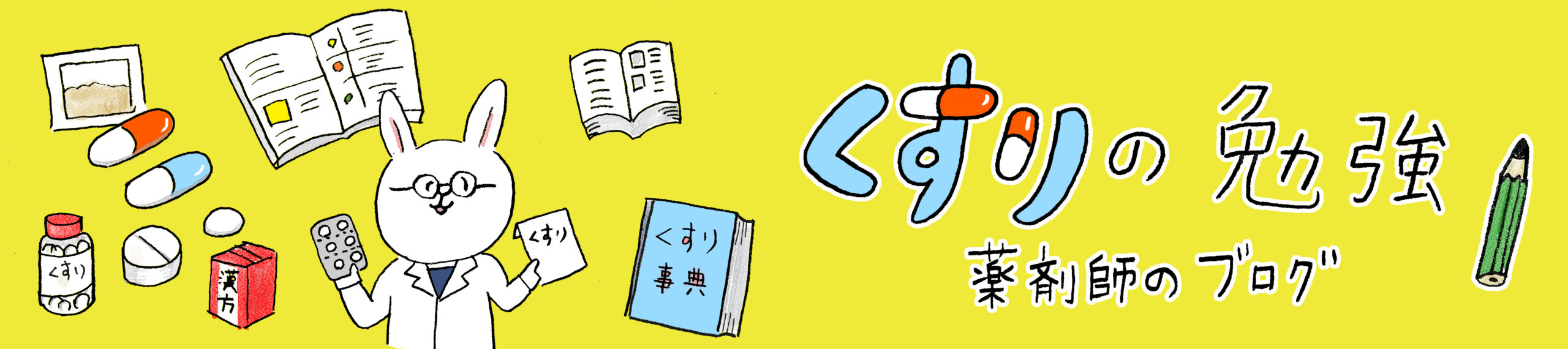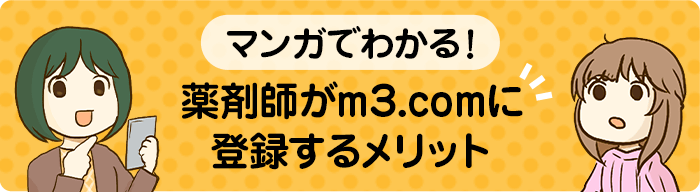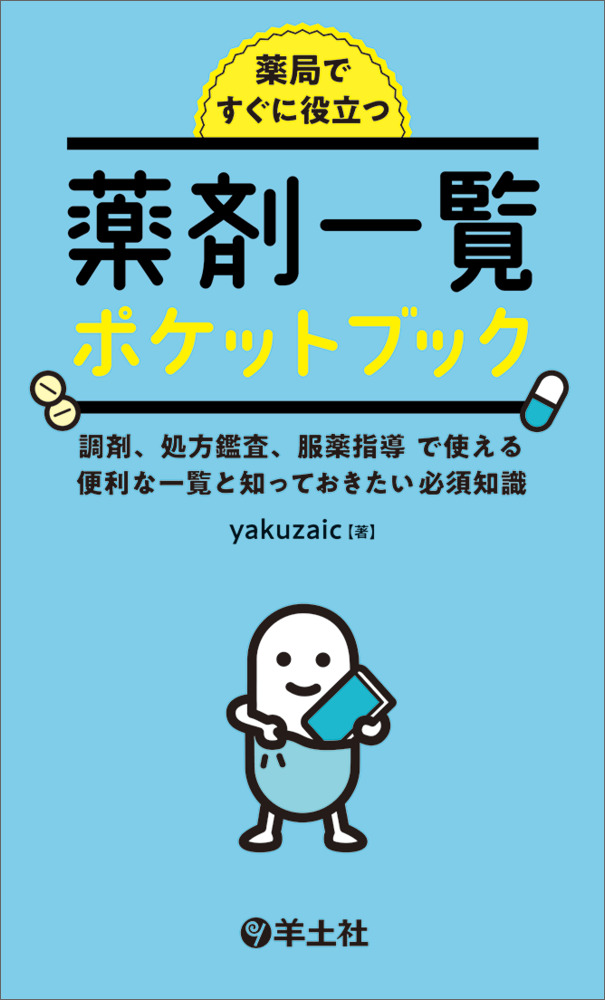記事
ニトロールとニトロペンの違いは?
公開. 投稿者: 18,815 ビュー. カテゴリ:狭心症/心筋梗塞.この記事は約3分54秒で読めます.
ニトロールとニトロペンの違いは?
ニトロールは硝酸イソソルビド。
ニトロペンはニトログリセリン。
硝酸イソソルビドとニトログリセリンの違いは?
ニトログリセリンは比較的、効果発現時間が早く、持続時間が短く、降圧作用が強い。
イソソルビドは比較的、効果発現時間が遅く、持続時間が長く、降圧作用が弱い。
硝酸薬の特徴
冠血管拡張と、末梢血管(動静脈)拡張による前および後負荷の軽減による心仕事量の軽減。
労作性および冠動脈攣縮による狭心症に有効。
ニトログリセリンは狭心症発作の特効薬である。
ニトログリセリンは心筋梗塞超急性期にも利点がある。
経口、注射、外用の各種製剤が発売されている。
口腔内が乾いている者(高齢者など)は口腔内噴霧がよい。
経皮製剤は肝での初回通過効果を受けないので、安定した血中濃度が得られる。
この場合テープはフィルムに硝酸薬を配合した粘着剤を塗布したものであるのに対して、パッチ剤は貯蔵層にニトログリセリンを貯めて皮膚との間に放出制御膜粘着剤を配置している。
発作発現時間や誘発因子に合わせて投薬時間を調節する。
速効製剤は発作寛解、持続製剤は狭心発作の予防に用いる。
経口硝酸薬の慢性投与は、必ずしも長期予後に好影響を与えていない。
漫然とした長期間の持続使用は耐性を生ずる。
注射剤は速効性を期待できるのと同時に持続点滴による長時間の効果維持が可能で、不安定狭心症の治療に有用である。
高用量持続点滴は不安定狭心症の治療に有用。
副作用に、頭痛、顔面紅潮、めまい、動悸、血圧低下など。
PDE-5阻害薬服用後、緑内障には禁忌。
硝酸薬は、①静脈を拡張し左室拡張期圧を低下させるとともに冠動脈を拡張し心筋酸素供給を増加させ、②血圧を低下させ心筋酸素需要量を減少させることにより虚血発作を寛解する。
舌下錠や噴霧液により発作を寛解する。
通常、数分で自覚症状は消失する。
ニトログリセリンの特徴
・使用後に頭痛・火照りを生じ、血圧低下を来すこともある。
・通常では消失する症状が寛解しない場合や通常より効果が低いときなどは、ACSへの移行を疑い専門医にコンサルトする。
・ニトログリセリンはいつも携帯し、すぐに使えるようにしていてください。
・ニトログリセリンが通常より効かない(1錠で症状がとれない)場合は、心筋梗塞の心配があるので、救急受診してください。
長時間作用型硝酸薬
抗狭心症作用や運動耐容能増加作用を有するが、生命予後改善や心血管イベント予防効果は証明されていない。
・長時間作用型の硝酸薬を使用する場合には耐性を予防するため、数時間薬剤が血中にない時間を設けることが推奨される。
・PDE5阻害薬との併用は禁忌である。
ニトログリセリンで頭痛?
硝酸薬は、冠血管のみならず頭蓋内血管も拡張するため約20%の頻度で頭痛が起きます。
これは薬理作用による副作用で、常にあらわれる可能性があるので、初回投与時には「頭が痛くなっても7~10日間程度でなくなるので服用を続ける」ことを患者さんに伝える必要があります。
剤形に限らず共通する副作用は、頭痛のほか血圧低下、めまい、顔面紅潮などがあります。
ニトログリセリンはダイナマイトの原料?
狭心症の治療に使うニトログリセリンですが、ダイナマイトの原料としても有名です。
よく爆発するのではと心配される方がいると思いますが、 含有量が少ないので、火の中に入れても爆発することはありません。
ニトログリセリンは甘い?
その昔、山の中のダイナマイト作業の現場に寝泊りしていた人たちが、甘味のあるニトログリセリンを酒のつまみにしていたという話。
本当か嘘かわかりませんが。
戦後の食糧難の時代には甘味料として使用され、多くの中毒者を出したという話も。
現在ニトログリセリンが甘味料として使われることはありませんが、グリセリンは甘味料として使われます。
グリセリンは、ギリシャ語のγλυκυς(glykys、甘い)にちなんで名づけられました。

勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。
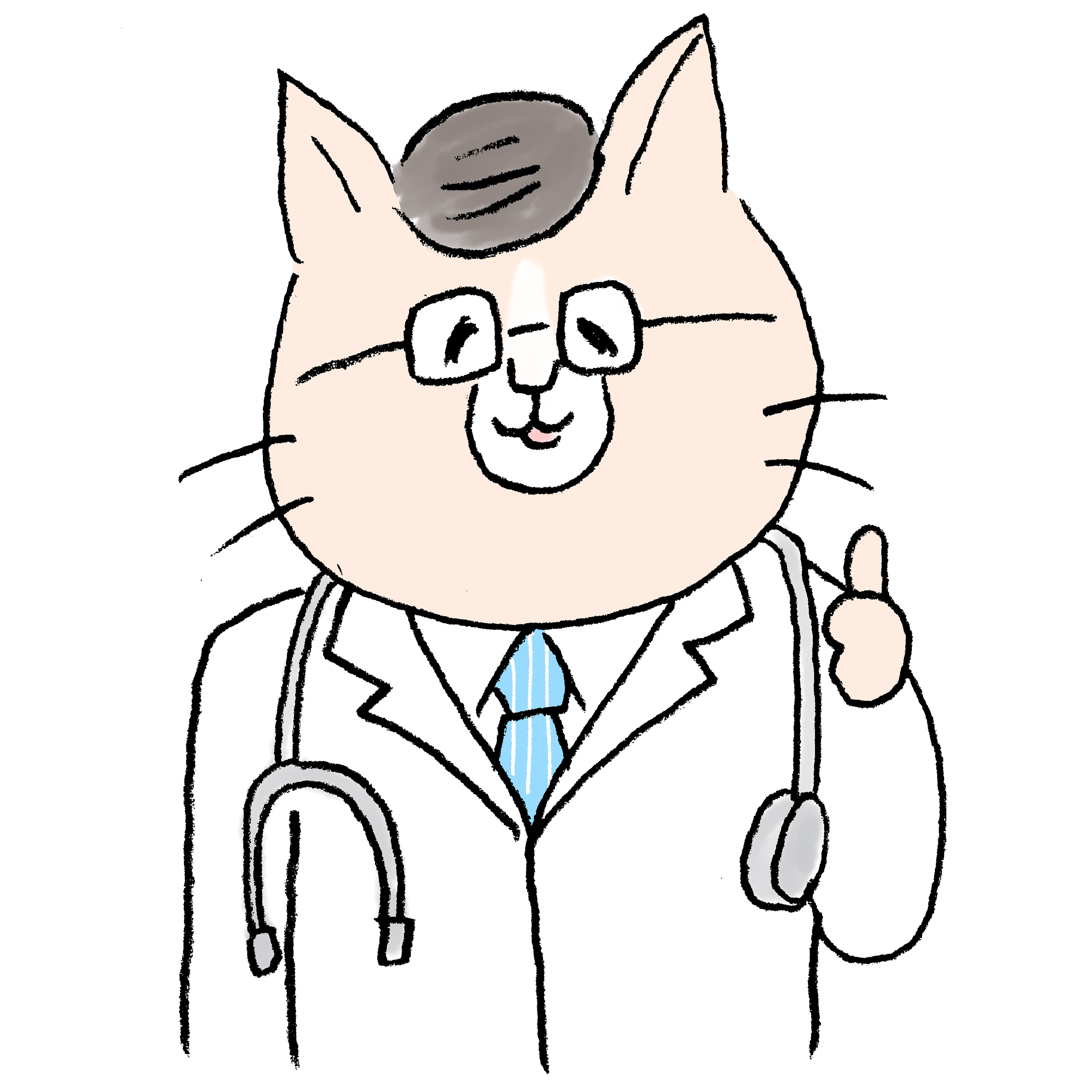
そんな薬剤師には、m3.com(エムスリードットコム)の、【PR】薬剤師のための「学べる医療クイズ」がおすすめ。